
結論「血液中のビタミンCが多い人ほど「眠れない悩み」が少ない――そんな驚きの関係が、3,000人以上の大規模調査から明らかになりました。」
この記事はこんな方におすすめ
✅「最近眠れない…」が日常になりつつある人
✅できれば薬に頼らず、自然な方法で眠れるようになりたい人
✅睡眠の質と栄養の“見えないつながり”に興味がある人
✅ストレスが多く、生活習慣を整えたいと感じている人
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:「最近、なんだか寝つけない…」それって、もしかして栄養不足かも?
🟡結果:血中ビタミンCが多い人は、睡眠トラブルの訴えが20〜30%少ない傾向がありました
🟢教訓:「眠りの質」が気になるなら、まず“毎日のビタミンC”を見直してみて
🔵対象:アメリカの成人約3,200人のデータを解析。日本人にも応用できる内容です
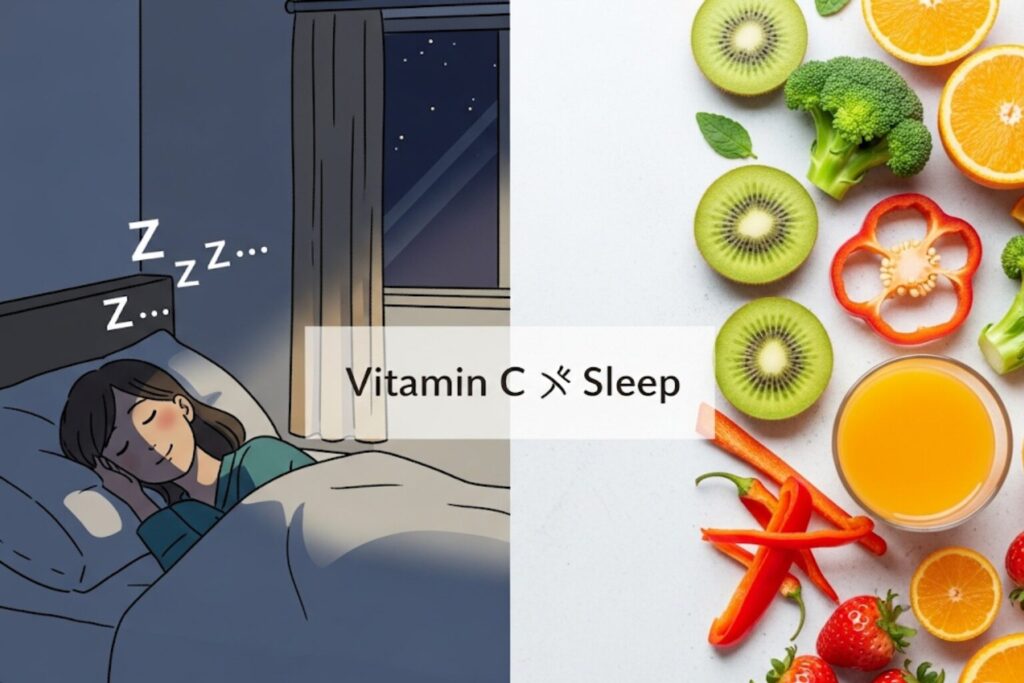
※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
寝ようと思っても寝つけない夜って、ありますよね。
ホットミルクを飲んでみたり、アイマスクをつけてみたり。
その場しのぎの対処法はいろいろあるけれど、
「じゅうぶん眠れなかったなあ」って朝を迎える日も、正直あります。
「眠りが浅いタイプ」や「寝付きが悪いタイプ」の方々もいますが、
もしかしてこれって、“体質”じゃなくて“栄養素”の問題なんじゃないか?
もし、ある栄養素が足りないことで「眠れない体」になっているのだとしたら――
それを補うだけで、ぐっすり眠れるようになるかもしれない。
そう考えると、ちょっとワクワクしませんか?
今回ご紹介するのは、まさにそうした視点で行われた最新の研究。
「血液中のビタミンCの量と睡眠の質の関係」をアメリカの大規模調査データから検証した、とても興味深い内容です。
この論文は、イギリス発の科学雑誌『Scientific Reports』に掲載されたもの。
信頼性の高いデータとともに、わたしたちの睡眠と栄養の「見えないつながり」を明らかにしてくれます。
今回はこの研究をもとに、「ビタミンCと眠り」の関係について、できるだけわかりやすくお届けしていきますね。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Association between vitamin C in serum and trouble sleeping based on NHANES 2017-2018”
(2017~2018年のNHANES調査に基づく、血清中ビタミンCと睡眠障害の関連性)
Sci Rep. 2024 Apr 27;14(1):9727.
PMID: 38678062 DOI: 10.1038/s41598-024-56703-0
掲載雑誌:Scientific Reports【イギリス:IF 3.9(2024)】 2024年4月
研究の要旨
研究目的
血清中のビタミンCと、睡眠障害の自己申告との関連性を調査する
研究方法
アメリカの健康調査NHANES(2017〜2018年)のデータから3,227人を対象に、血清ビタミンCと睡眠障害(医師に相談したことがあるか)を比較し、統計解析を行った
研究結果
ビタミンCの血中濃度が高い人ほど睡眠障害のリスクが低い。特に女性や65歳以下、コレステロール値が高い群で有意だった
結論
ビタミンCは睡眠の質を向上させる可能性がある
考察
抗酸化作用や神経伝達物質の合成に関与するビタミンCが、睡眠の質に好影響を及ぼす可能性が示唆された。今後の介入研究が必要。
研究の目的
この研究が目指したのは、
「血液中のビタミンCの量が、睡眠の質と関係しているのか?」
という疑問を科学的に検証することです。
ビタミンCは、私たちの体にとって欠かせない栄養素の一つであり、
免疫や抗酸化作用に加えて、神経伝達物質の合成にも関与し気分や睡眠にも影響しうることが知られています。
一方で、睡眠障害は多くの人が抱える悩みであり、生活の質を損なうだけでなく、糖尿病や高血圧などの慢性疾患とも関わっています。
しかし、「ビタミンCの量と睡眠の悩みに関連があるか?」という点についての研究は、これまでほとんど行われていませんでした。
そこで本研究では、アメリカの大規模調査(NHANES)のデータをもとに、血清ビタミンCと睡眠障害との関連性を調査することで、この疑問に答えようとしました。

研究の対象者と背景
この研究は、アメリカで実施されている国民健康栄養調査(NHANES)のデータをもとに行われました。

使用されたのは2017〜2018年分の調査データです。
対象となったのは、調査項目がすべてそろっていた3,227人の成人(男女とも)です。
このNHANES調査は、アメリカ全体を代表するような構成でランダムに選ばれた国民を対象としており、
人種や年齢、健康状態などが幅広く含まれています。
この研究はアメリカのデータに基づいていますが、
「ビタミンCは食事からしか摂取できない」という点は日本人にも共通しています。
生活習慣の違いはあるものの、「栄養と睡眠のつながり」を考えるうえで、日本人にも十分参考になる内容です。

研究の手法と分析の概要
この研究は、横断的観察研究の形式で行われました。
一度の健康調査のタイミングで「血液中のビタミンCの量」を測定し、同時に「これまでに睡眠の悩みで医師に相談したことがあるか」を質問しました。
つまり、“今の体の栄養状態”と“これまでの睡眠の困りごと”に、何か関係があるのか?” を調べるスタイルです。
長期間にわたる追跡調査ではなく、ある時点の情報をもとに「傾向」を探る観察研究として行われました。
調査対象と期間
対象人数:3,227人(18歳以上のアメリカ成人)
調査期間:2017年〜2018年(NHANESデータより)
年齢層:若年〜高齢まで幅広くカバー

測定された情報
睡眠の問題:
参加者に「これまでに睡眠の悩みを医師に相談したことがありますか?」と質問
→ 回答は「はい」または「いいえ」の二択
ビタミンC:
血液検査により、血清中のビタミンC濃度をmg/dL単位で測定
使用された分析手法
・多変量ロジスティック回帰分析
・四分位分析(Quartile Analysis)
・非線形モデル(RCSモデル)
【補足:各種用語】
多変量ロジスティック回帰分析
複数の要因(例:年齢、性別、持病など)を同時に考慮しながら、
「AがあるとBが起こりやすいか?」を数値で表す分析です。
今回は、「ビタミンCが多い人は、睡眠障害を持ちにくいのか?」という関係を確認するために使われました。
四分位分析(Quartile Analysis)
参加者をビタミンCの血中濃度の順に並べて、4つのグループ(四分位)に分け、
最も少ないグループを基準として、他のグループと比べることで傾向を可視化します。
非線形モデル(RCSモデル)
RCSとは “Restricted Cubic Spline” の略。
単純な「直線的な関係」ではなく、ある値を境に急に効果が現れるなどのカーブ状の関連を調べる手法です。
この研究では、「ビタミンCがどれくらいの濃度を超えると、睡眠障害のリスクが下がるのか」を見るために用いられました。

研究結果
ビタミンCが多い人ほど、睡眠の悩みが少ない
血液中のビタミンC濃度が高い人は、「過去に睡眠の悩みで医師に相談したことがある」と答える割合が明らかに少ないことがわかりました。
この関係は、年齢や性別、体型、持病、心理状態など、さまざまな条件を考慮しても統計的に有意でした。
つまり、偶然ではなく、明確な傾向があるということです。
また逆に、実際に睡眠障害があると回答した人たちの方が、血液中のビタミンC濃度が平均して低いという結果も出ています。
このことから、「眠れないからビタミンCが減る」可能性も含め、双方向のつながりがあるのかもしれません。
一定の濃度を超えると、睡眠障害のリスクが下がる
血中ビタミンCの量と睡眠障害のリスクは、直線的ではなく“カーブ”を描くような関係がありました。
とくに0.9mg/dLを超えたあたりから、睡眠障害のリスクが急激に減少するという特徴が確認されています。
この数値はひとつの“しきい値”として考えることもでき、
最低限このくらいのビタミンC濃度を保つことが、睡眠にとって重要なのかもしれません。
こんな人ほど効果がはっきりしていた
ビタミンCが多いほど睡眠の悩みが少ない、という効果は、以下のグループで特にはっきり見られました。
| 対象グループ | 睡眠障害のリスクの変化 |
| 女性 | 約29%低下 |
| 65歳以下の人 | 約23%低下 |
| 高コレステロールの人 | 約26%低下(健康リスクの高い人ほど明確) |
いずれも、他の要因をすべて調整した後でも有意な結果となっています。
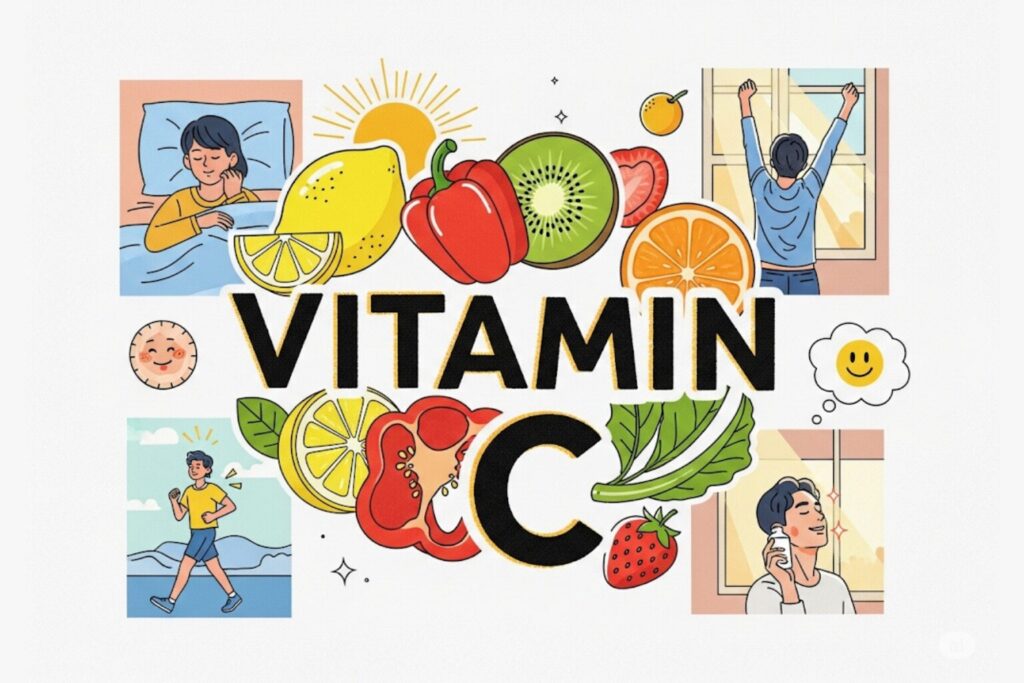
効果が明確でなかった人たち
一方、男性や65歳以上の高齢者では、この傾向は明確には見られませんでした。
ただし、これは「効果がなかった」というより、統計的に有意な差が確認されなかったという意味です。
悪化したわけではありません。
ビタミンCが少ない人では、睡眠トラブルが多かった
調査対象者を血中ビタミンCの量で4つのグループ(四分位)に分けて比較したところ、
最も少ないグループ(Q1)では、他のどのグループよりも睡眠障害を訴える割合が高かったことがわかりました。
| 四分位グループ | 血清ビタミンC濃度(mg/dL) |
| Q1(最も少ない) | 0.45未満 |
| Q2 | 0.45〜0.85 |
| Q3 | 0.85〜1.20 |
| Q4(最も多い) | 1.20より多い |
このように、ビタミンCが1.20以上ある人たち(Q4)は、0.45未満の人たち(Q1)と比べて明らかに睡眠トラブルが少ない傾向が見られました。
実際、Q2〜Q4のいずれのグループでも、Q1よりも20〜30%ほど睡眠障害のリスクが低いという結果が示されています。
このことから、一定量以上のビタミンCを保つことが、良質な睡眠の鍵になる可能性があると考えられます。
睡眠とつながる、他の健康状態にも差が
この研究では、睡眠障害がある人ほど、
体重・BMI・ウエストサイズ・うつ傾向・糖尿病・高血圧・コレステロール異常・喫煙・アルコール摂取など、
生活習慣や健康状態においても悪化傾向が見られました。
これらの要素はすべて、ビタミンCの不足ともつながる可能性があり、
「睡眠・栄養・生活習慣」が密接に関係していることが示唆されます。
つまり、「睡眠が乱れている=生活習慣も乱れやすい=ビタミンCも足りなくなりがち」という“負のスパイラル”がある可能性も。
一つの改善(たとえば栄養を見直すこと)が、連鎖的に他の不調を軽減するヒントになるかもしれません。
信頼性の高い分析が行われた
今回の分析では、性別・年齢・人種・糖尿病や高血圧の有無、血中コレステロール、体格指数(BMI)など、
考えられる限りの条件を統計的に調整したうえで結果が導かれています。
そのため、「ビタミンCと睡眠のつながり」には十分な信頼性があるといえる内容です。
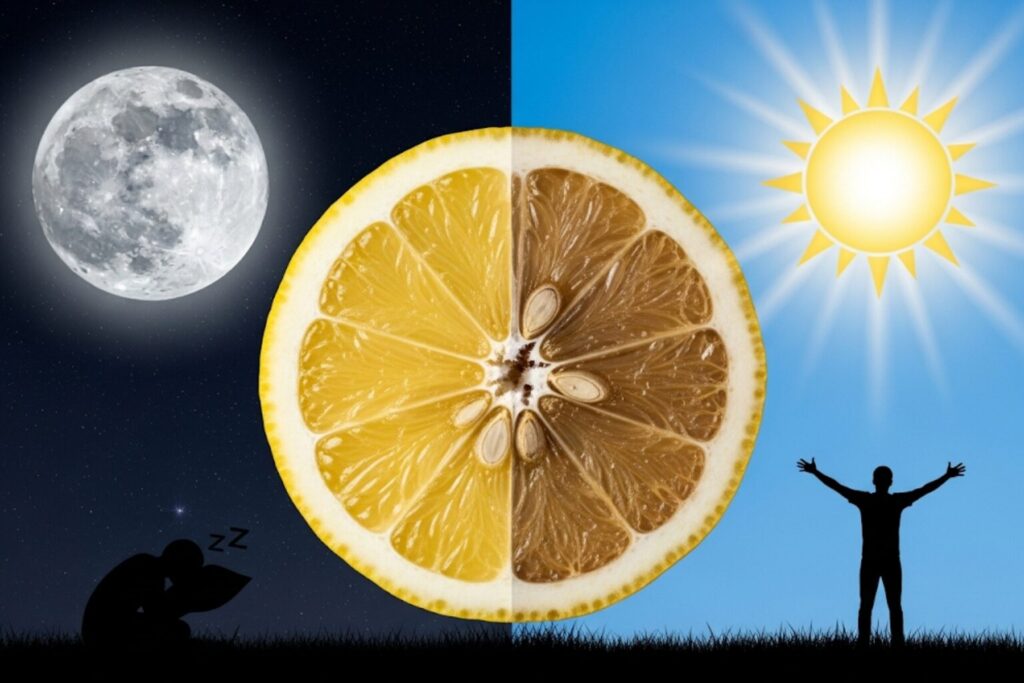
研究の結論
この研究からわかったのは、血液中のビタミンC濃度が高い人は、睡眠障害のリスクが明らかに低いということです。
とくに血中濃度が0.9mg/dL以上の人では、睡眠の悩みが少ない傾向がはっきり見られました。
この関係は、年齢や性別、体格、健康状態などの違いをすべて調整した上でも成り立っており、
単なる偶然ではなく、信頼性のある関連性といえる結果でした。

【礼次郎の考察とまとめ】
なぜ、ビタミンCが睡眠と関係するのか?(論文著者の考察)
ビタミンCは、体内で神経伝達物質を作る働きに関わっていると考えられています。
特に「セロトニン」や「ドーパミン」といった物質は、気分の安定や睡眠のリズムを整えるうえで重要です。
ビタミンCが不足すると、こうした神経系のバランスが崩れ、
不安感やイライラ、寝つきの悪さにつながる可能性があると著者らは指摘しています。
また、ビタミンCには強い抗酸化作用もあります。
慢性的なストレスや炎症があると眠りが浅くなるといわれており、
ビタミンCがそのストレスを緩和することで、睡眠の質を高める可能性も示唆されています。

わたしたちが今日からできること
今回の研究結果は、「サプリを飲めば眠れるようになる」と断言するものではありません。
ただし、「ビタミンC不足が体や心にさまざまな影響を与えるかもしれない」という視点は、日々の生活を見直すヒントになりそうです。
研究では、血中濃度が0.9mg/dLを超えるあたりから、睡眠障害のリスクが下がっていました。
この数値を達成するための1日のビタミンC摂取量の目安は、概ね100〜150mg程度と考えられます。
日本の「推奨摂取量」は1日100mgですが、ストレスが多い人や喫煙者はそれ以上の補給が推奨されています。
この量は、以下のような食品で無理なく摂取できます。
ビタミンCが豊富な身近な食品(摂取目安つき)
| 食品・飲み物 | ビタミンC量(目安) | ひとこと |
| キウイ1個(約100g) | 約70mg | フルーツで手軽に! |
| 赤ピーマン1個(約80g) | 約110mg | 野菜の中でもトップクラス |
| ゆでブロッコリー1皿(約70g) | 約50mg | 加熱してもある程度残る |
| いちご5〜6粒(約100g) | 約60mg | 朝食やおやつにぴったり |
| オレンジジュースコップ1杯(約200ml) | 約100mg | 飲み物で補給したいとき |
| 市販のビタミンCサプリ1粒(500〜1000mg) | 約5〜10倍分 | 飲みすぎには注意! |
生活にどう取り入れる?
たとえば――
・朝にキウイ1個+オレンジジュースをコップ1杯
・夜ご飯にブロッコリーと赤ピーマンの炒め物
こんな簡単な組み合わせで、1日150mg以上のビタミンCはあっという間に達成できます。
もちろん、サプリメントで補うのも選択肢のひとつ。
ただし、サプリは摂りすぎに注意が必要なので、基本は食事中心+必要に応じて補助的に使うのがおすすめです。
気づかない「不足」があるかも?
一度に大量に摂取しても、わたしたちの体はビタミンCを体内にためておけません。
しかも、ストレスが多かったり、外食や偏食が続いたり、喫煙している人は消耗が早くなります。
「栄養は足りてるはず」と思っていても、知らないうちに足りていない可能性も。
「最近ちゃんと眠れてないな」と感じたら、まずは毎日の食事に色の濃い野菜や果物を――
そんな小さな意識の積み重ねが、やがて深い睡眠につながるかもしれません。
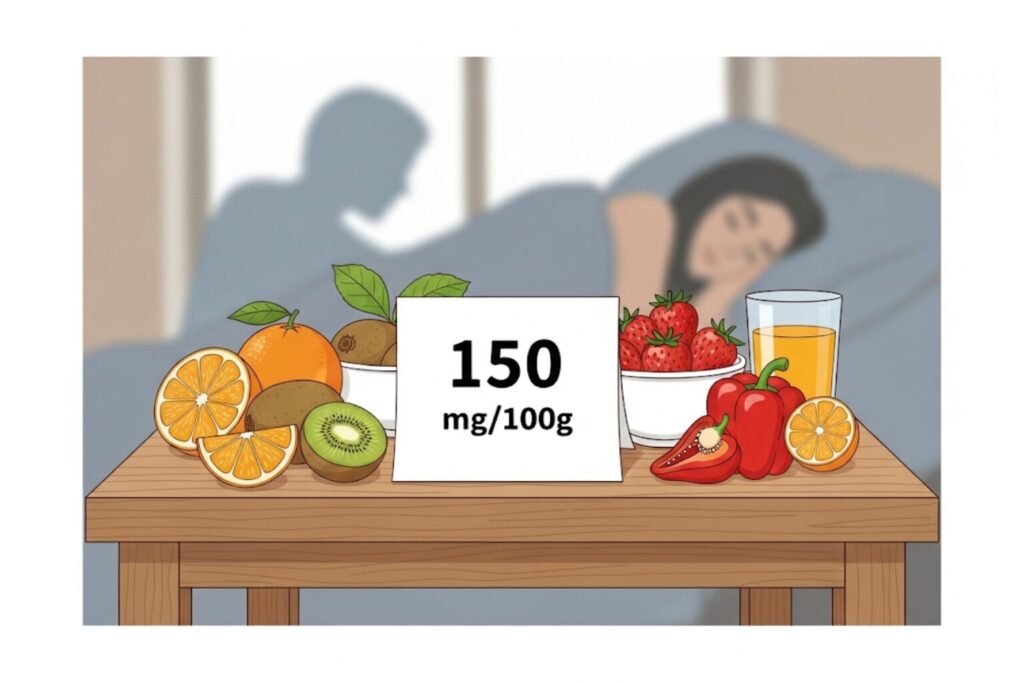
おまけ:実生活に役立つ・自分専用AIプロンプト
『ビタミンC×睡眠セルフチェック』
ChatGPTやGeminiなどのAIに入力して、自分の『ビタミンCと睡眠の関係』を自動でチェック&改善アドバイスできるプロンプトを作りましたので掲載させていただきます。
コピペ→ 部分に入力するだけで結果が得られますのでよかったらご活用ください!
以下をそのままAIに入力してください。
⚠注意事項
本ツール(プロンプト)は生成AIを利用しています。AIの出力には不正確・誤解を招く表現が含まれる場合があります。
提供される内容は厳密な結論ではなく参考情報であり、ジョークアプリ程度の娯楽的ツールとしてご利用ください。
医療・健康に関する最終判断や治療方針の決定には使用せず、必要に応じて医師など専門家にご相談ください。
ご利用は自己責任でお願いいたします。
【入力用AIプロンプト】
あなたは健康管理に詳しいAIアドバイザーです。
以下の質問に対するユーザーの回答をもとに、「血中ビタミンC濃度と睡眠の質の関連」について、信頼性の高い疫学研究に基づいてフィードバックを行ってください。
この評価は、アメリカの大規模国民健康栄養調査(NHANES 2017–2018)データを用いた以下の研究結果に基づきます:
◎論文タイトル:Association between vitamin C in serum and trouble sleeping based on NHANES 2017–2018
発表年:2024年
掲載誌:Scientific Reports(Nature Publishing Group, 英国)
研究概要:約4,500人の成人を対象に、血液中のビタミンC濃度と「睡眠の悩み(寝付きの悪さや不眠)」の関係を分析した。結果、血中ビタミンC濃度が高い人は、睡眠障害を訴える割合が20〜30%低く、特に0.9mg/dL以上の濃度がひとつの目安とされた。この結果は、年齢・性別・体格・心理状態・喫煙歴などの影響を調整したうえでも、統計的に有意であった。
◎【以下の質問項目にユーザーが回答】
・最近1ヶ月で「寝付きの悪さ」や「眠れない夜」があった頻度(例:週3回以上、毎日、たまに、ない):
・ビタミンCが豊富な食品(例:キウイ・いちご・ブロッコリー・赤ピーマンなど)をどれくらいの頻度で食べていますか?
→ A. ほとんど食べない / B. 週1〜2回 / C. 1日1回 / D. 毎日2種類以上:
・オレンジジュースなどビタミンC入りの飲み物を飲む頻度は?(例:A.毎日・B.たまに・C.飲まない):
・サプリメントでビタミンCを摂っていますか?(例:毎日1000mg・週に数回・摂っていない):
・年齢: 歳
・性別:
・喫煙の有無(喫煙者はビタミンCの消耗が早いため):
・1日におおよそ摂っている野菜と果物の合計量(g)(例:100g、300g、500gなど):
◎【AIが行う出力の指示】
・入力情報をもとに「ビタミンC摂取状況」と「睡眠の質のリスク傾向」を判定
・NHANESベースの研究結果(高ビタミンC=不眠のリスクが約30%低下)を用いて、改善の可能性を簡潔に示す
・食品で摂るならどんなものが効果的か(キウイ、ブロッコリーなど)具体例を2〜3紹介
・サプリの活用については安全な範囲で補助的に、と助言する
・最後に「この結果は、2023年にScientific Reports誌に掲載された米国の疫学研究に基づく内容です」と必ず明記
◎このプロンプトで得られること:
・自分の生活にビタミンCがどれくらい足りているかの感覚がわかる
・「眠れない夜」の原因を“体質”だけでなく栄養面からも見直せる
・具体的な行動(食事や習慣)のヒントが得られる
私もAIにチェックしてもらいました!✌️
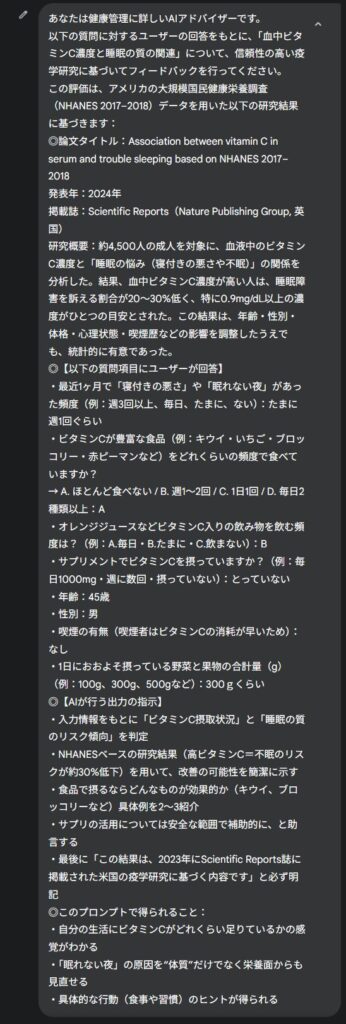
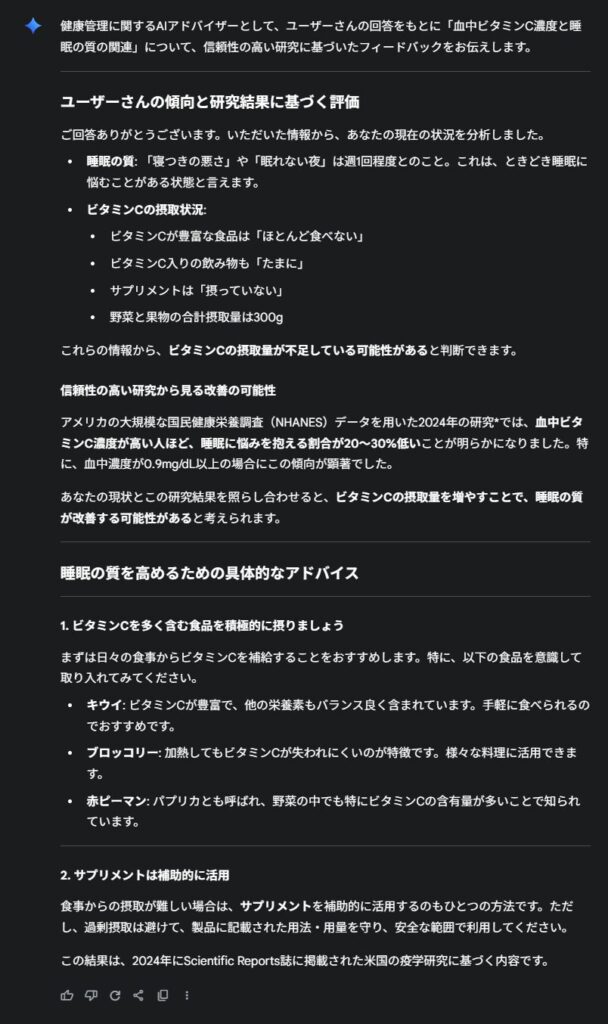
ビタミンC🍋不足してるそうです笑
締めのひとこと
ビタミンCは、『ぐっすり』のやさしい味方

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント