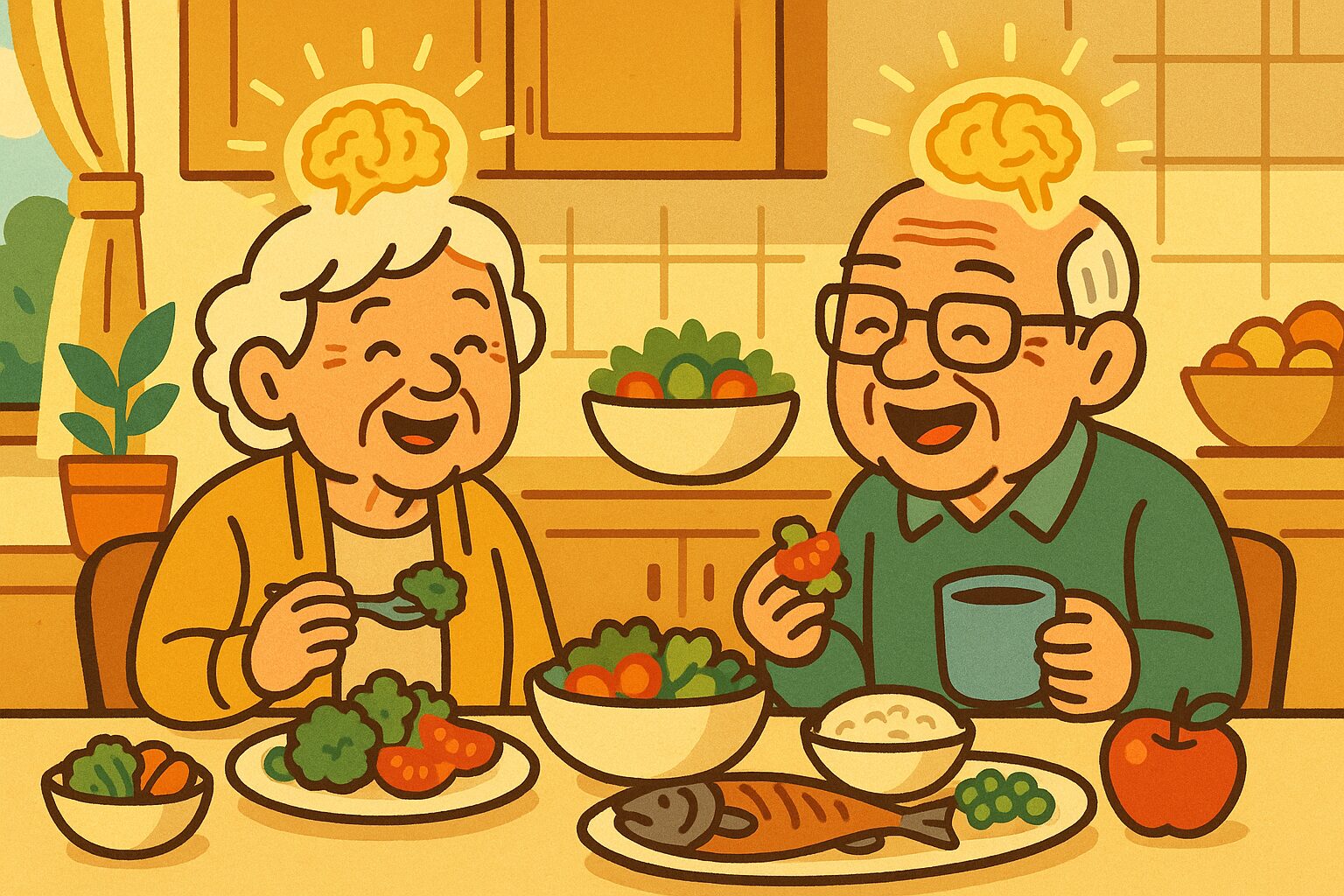
結論「野菜や果物が多いアルカリ寄りの食事は、高齢になっても記憶力や思考力を守るカギになる可能性があります」
この記事はこんな方におすすめ
✅「最近、物忘れが気になる…」と感じ始めた60代以上の方
✅「親や家族の認知症予防につながる食事を知りたい」と思う方
✅「健康寿命をのばして、いつまでも元気に過ごしたい」中高年世代
✅「食事で脳の健康を守る方法」を知りたいすべての方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:どうすれば高齢になっても記憶力や思考力を若々しく保てるの?
🟡結果:野菜や果物を多く食べる「アルカリ寄りの食事」をしている人は、スーパーエイジャー(80歳以上で記憶力が若い人並み)である確率が高かった。酸負荷が1単位下がるごとに確率は約3〜4%上昇。
🟢教訓:毎日の食事に「もう一品の野菜や果物」を加えることが、認知症予防にもつながるヒントかもしれません。
🔵対象:アメリカの60歳以上を対象にした大規模調査。日本人でも食生活の工夫として応用できると考えられます。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
みなさん、こんにちは!
みなさんは「物忘れが増えたな」と感じることはありませんか?
わたし自身40代も半ばを過ぎ、昨日の晩ごはんですら思い出せないことがしばしば。
そんなとき、「このまま20年、30年先はどうなってしまうのだろう…」と戦々恐々とする毎日です(笑)
一方で、世の中には「スーパーエイジャー」と呼ばれる人たちがいます。
80歳を超えても若い人並みの記憶力を持ち、いきいきと暮らしている方々だそうです。
今回ご紹介するのは、フランスで発刊されている高齢医学系の専門誌『The Journal of Nutrition, Health and Aging(栄養・健康・加齢ジャーナル)』に掲載された研究です。
テーマは「スーパーエイジャーの記憶力の秘密と食事との関係」。
わたしたちが毎日の食卓で選ぶ一皿が、将来の脳の健康を守るヒントになるかもしれません。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“The impact of dietary acid load on super-agers with exceptional cognitive abilities: a propensity score analysis of national health and nutrition examination survey (NHANES) 2011-2014”
(超高齢で卓越した認知能力を示す“スーパーエイジャー”における食事性酸負荷の影響:NHANES 2011–2014を用いた傾向スコア解析)
Chen-Ying Lin, Fang Li, Hao-Hua An et al.
J Nutr Health Aging. 2024 Jun;28(6):100238.
PMID: 38663039 DOI: 10.1016/j.jnha.2024.100238
掲載雑誌:The Journal of Nutrition, Health and Aging【フランス:IF 4.0(2024)】 2024年6月
研究の要旨
研究目的
80歳以上で若い人並みの記憶力を保つ「スーパーエイジャー」と、食事によって体にかかる酸性やアルカリ性の負荷との関係を明らかにすること。
研究方法
アメリカの国民健康・栄養調査(NHANES 2011–2014)に参加した60歳以上の985人を対象に、食事の酸負荷を算出し、統計的に交絡を調整して分析した。
研究結果
果物や野菜の多いアルカリ性寄りの食事をしている人ほど、スーパーエイジャーである可能性が高く、とくに70歳以上で記憶力や認知スコアの低下が少なかった。
結論
アルカリ性寄りの食事は、高齢者の認知機能を保つことに役立つ可能性がある。
考察
加齢による腎機能の変化が酸負荷の影響を強める可能性があり、因果関係を確かめるためには今後の介入研究が必要である。
研究の目的
この研究の目的は、80歳を超えても若い人と同等の記憶力を保つ「スーパーエイジャー」と呼ばれる人たちに注目し、日々の食事による酸性・アルカリ性の負荷が、彼らの認知機能にどのように関係しているのかを明らかにすることです。
特に、年齢層ごとに食事の酸負荷が記憶や注意力など異なる認知機能領域に及ぼす影響を検討することで、加齢と食生活の関わりを理解することを目指しました。

研究の対象者と背景
調査に使われたデータ
この研究は、アメリカ疾病対策センター(CDC)が実施している全国規模の健康・栄養調査(NHANES 2011–2014)のデータを利用しました。

対象となった人数
最初に60歳以上の3,632人が候補となり、条件を満たさない人を除いた結果、985人が主な分析に使われました。
さらに確認のため、2,522人を対象に追加分析も行われています。
スーパーエイジャーの定義
「スーパーエイジャー」とは、80歳以上で、記憶力が20〜30歳若い人と同等レベルを維持し、注意力や処理速度なども同年代の平均を保っている人と定義されました。

研究の手法と分析の概要
研究デザイン
研究は横断研究です。ある時点での食事内容と認知機能を調べ、その関係を統計的に分析しました。
食事の酸負荷(DAL:Dietary Acid Load)の計算
参加者の食事調査から栄養素を集計し、次の3つの指標で「体にかかる酸・アルカリの負荷」を算出しました。
・PRAL(潜在的腎酸負荷)
・NAEes(推定正味酸排泄量)
・NEAP(内因性酸産生量)
数値が高いほど体を酸性に傾ける食事、低いほどアルカリ性寄りの食事を意味します。
評価された内容
身体測定
・血圧、腹囲など、生活習慣病に関連する数値を測定しました。
認知機能テスト
・記憶力(単語を覚える・思い出すテスト)
・処理速度(数字や記号を対応させるテスト:DSST)
・言語流暢性(動物名を挙げるテスト:AFT)
これらを使って、高齢者の認知機能を多面的に評価しました。

統計的な工夫
生活習慣や年齢などの違いが結果に影響しないように、次の方法で調整しました。
・傾向スコアマッチング(似た条件の人を比較する方法)
・逆確率重み付け(偏りを均す方法)
・多変量ロジスティック回帰(複数の要因を同時に調整する方法)
年齢ごとの比較
さらに、60〜69歳、70〜79歳、80歳以上に分けて分析し、年齢による違いを検討しました。
【補足:各種用語】
PRAL(潜在的腎酸負荷)
食べ物が体に入ったあと、腎臓にどれくらい酸の負担を与えるかを計算した数値です。
肉やチーズなどは酸性寄り、野菜や果物はアルカリ寄りになります。
NAEes(推定正味酸排泄量)
尿を通じて体の外にどれだけ酸が排出されるかを推定した数値です。
体にたまる酸の量を間接的に示しています。
NEAP(内因性酸産生量)
食べ物から体の中でどれくらい酸がつくられるかを推定する計算式です。
たんぱく質やカリウムの摂取量から導かれます。
傾向スコアマッチング
年齢や性別など条件が似た人同士を比較することで、「食事の影響」だけをなるべく公平に比べられるようにする方法です。
逆確率重み付け
一部の条件に偏った人が多い場合でも、全体がバランスよくなるように重みを調整して分析する方法です。
多変量ロジスティック回帰
年齢や生活習慣など複数の要因を同時に計算に入れながら、どの要素が「スーパーエイジャーかどうか」に影響しているかを分析する統計手法です。

研究結果
スーパーエイジャーの特徴
スーパーエイジャーは他の高齢者に比べて食事の酸負荷(PRAL, NAEes, NEAP)が低く、アルカリ寄りの食事をしていました。
血圧や腹囲も低めで、全体的に健康的な背景を持っていました。
つまりスーパーエイジャーは、食事だけでなく全体的に生活習慣病のリスクが低い体格的特徴も持っていました。
記憶力テストでは優れていましたが、処理速度や言語流暢性は同年代と大きな差はありませんでした。

数値での関連性
統計的に調整した分析でも一貫して、
・PRALが1単位下がるとスーパーエイジャーの可能性が約3%上昇
・NAEesが1単位下がると約3.9%上昇
が確認されました。NEAPは明確な関連を示しませんでした。これらは対象を2,522人に広げた追加解析でも同じ傾向が確認されています。
| 指標 | 酸負荷が下がるとどうなるか | 最も影響が強かった年齢層 |
| PRAL | スーパーエイジャー確率+約3% | 70歳以上、特に80歳以上 |
| NAEes | スーパーエイジャー確率+約3.9% | 70歳以上、特に80歳以上 |
| NEAP | 関連なし | – |
年齢別の違い
・60〜69歳:酸負荷と認知機能に関連はなし。
・70〜79歳:酸負荷が高いほど記憶テストの点数が低下(逆相関)。
・80歳以上:記憶だけでなく、処理速度や全体の認知スコアも酸負荷と逆相関を示しました。
陰性所見
動物名を答える言語流暢性のテスト(AFT)には関連が見られず、すべての認知機能が酸負荷の影響を受けるわけではないことも示されました。
つまり酸負荷は特に記憶や処理速度に関わる一方、言語能力には影響が少ない可能性があります。

研究の結論
アルカリ寄りの食事と脳の健康
野菜や果物を多く含むアルカリ寄りの食事をしている高齢者は、記憶力や思考力を保つ可能性が高いことが示されました。
年齢による影響
特に70歳以上でその効果が強く、80歳を超えると記憶だけでなく処理速度や全体の認知機能にも関連が見られました。
結果の一貫性
PRALやNAEesという指標では安定した関連が確認され、対象を広げた解析でも結果は揺らぎませんでした。

【礼次郎の考察とまとめ】
論文著者による考察
年齢と腎機能の低下
高齢になると腎臓の酸を排泄する力が低下し、酸性寄りの食事の影響を受けやすくなる。
そのため70歳以上で食事の酸負荷と記憶力の関連が強まった可能性がある。
酸塩基バランスと脳機能
酸塩基バランスは脳の働きに影響する。
血中の重炭酸濃度が高い人は認知機能が良好であることが別の研究で示されており、逆に酸性に傾くとシナプスの働きや血流、血液脳関門が損なわれ、神経毒性のリスクが高まると考えられる。
分子レベルの仕組み
脳内の炭酸脱水酵素(CA)は記憶形成に関与しており、その働きが悪くなると認知症や加齢による記憶低下に関連する。
また酸感受性イオンチャネル(ASICs)はpH変化に反応して記憶や学習を左右し、アルツハイマー病の進行とも関わるとされる。
栄養素との関連
DALは「タンパク質、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン」などの栄養素から計算される指標であり、これら個々の栄養素が認知機能に影響することは既に複数の研究で示されている。
例えばカリウムはアルツハイマー病モデルマウスで病変を軽減し、カルシウムやマグネシウムも記憶機能の維持に関係する。
食事パターンと文化的背景
アメリカの高齢者は動物性タンパクや穀類が多く、野菜や果物が不足しがちな「西洋型食生活」を送る傾向がある。
そのため酸負荷が高くなりやすいが、スーパーエイジャーは逆にアルカリ寄りの食事(野菜果物が多く肉が少ない)をしていることが際立っていた。
研究の限界
この研究は横断研究であり因果関係を証明できない。
さらにNHANESのデータでは80歳以上の年齢幅が細かく分かれていないため、詳細な分析に限界がある。今後は縦断的研究が必要とされる。

日常生活へのヒント
この研究は「認知症の特効薬」を示すものではありませんが、毎日の食事を工夫することで脳の健康を支えられる可能性を示しています。
野菜と果物をもう一品
食事の酸負荷を下げる最もシンプルな方法は、野菜や果物を取り入れることです。
特に緑黄色野菜や柑橘類はアルカリ寄りで、体の酸性を和らげる助けになります。
毎日の食卓に「もう一皿サラダ」や「デザートに果物」を加えることから始めましょう。
肉と加工食品をとりすぎない
肉やチーズ、加工食品は酸性寄りになりやすい食品です。
完全に避ける必要はありませんが、摂りすぎには注意が必要です。
たとえば「肉料理は一日一回に抑える」「ベーコンより魚や豆腐を選ぶ」といった工夫が役立ちます。
魚や大豆製品を活用する
日本の伝統食である魚や大豆製品(豆腐、納豆、味噌など)は、良質なたんぱく源でありながら酸負荷が比較的低めです。
欧米型の食事に比べて体にやさしく、脳の健康にもプラスになると考えられます。
水分をしっかりとる
体内の酸塩基バランスを保つためには水分補給も大切です。
高齢になると喉の渇きを感じにくくなるため、意識的にお茶や水をこまめに摂る習慣が役立ちます。
続けやすい工夫を
「酸性・アルカリ性を意識した完璧な食事」をいきなり目指す必要はありません。
むしろ「今日の献立に野菜を一品増やす」「週に2回は魚を食べる」といった小さな習慣が、将来の脳の健康につながります。
こうした小さな習慣が、将来の「もの忘れ予防」につながると科学が示してくれました。
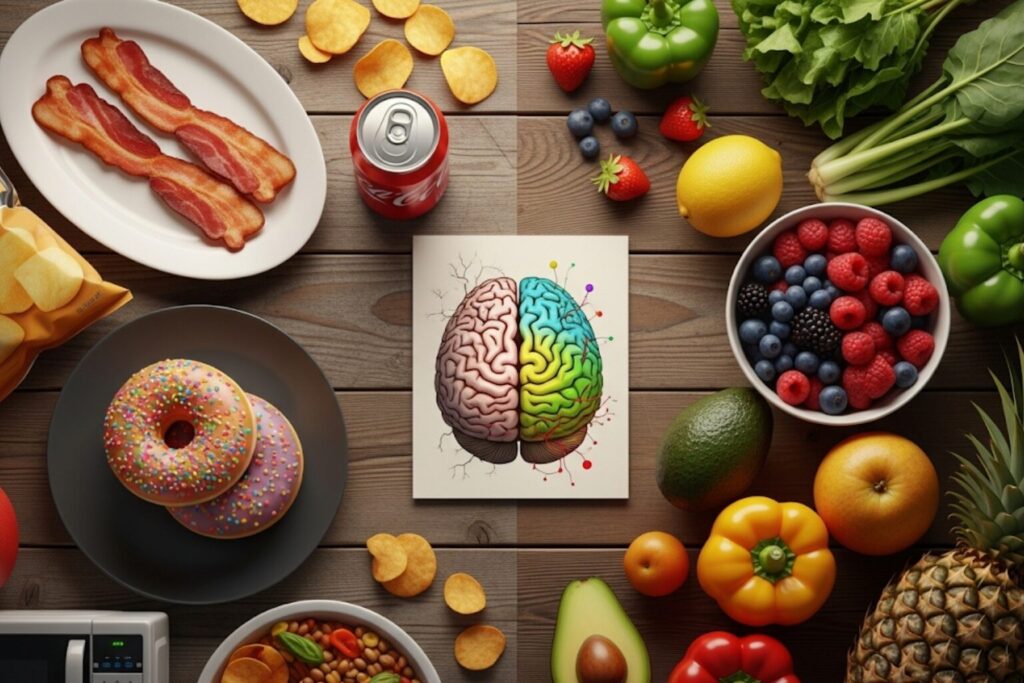
脳を元気にする秘訣は、薬ではなく毎日の食卓にあるようです。
無理のない範囲で続けていけるといいですね。
締めのひとこと
野菜や果物は、未来の脳へのプレゼント

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント