
結論「『長年にわたって砂糖入り飲料をよく飲む人は、たとえ運動していても、心臓病や脳卒中のリスクが高くなる』ことが、大規模な研究で明らかになりました。」
この記事はこんな方におすすめ
✅健康のために運動をしているが、甘い飲み物も好きな方
✅「ゼロカロリー飲料」なら安心と思っている方
✅食生活を見直したいけど、何から始めればいいかわからない方
✅ご家族の健康が気になる方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:運動していれば、ジュースやゼロカロリー飲料を飲んでも大丈夫?
🟡結果:毎日2回以上ジュースを飲む人は、心臓病や脳卒中のリスクが約20%高かった。運動していても帳消しにはならなかった。
🟢教訓:運動だけで安心せず、飲み物の“習慣”も見直すことが大切。たまの楽しみはOKでも、毎日のジュースは要注意。
🔵対象:アメリカの医療従事者 約10万人が30年以上にわたり追跡された研究。日本人にも参考になる内容です。

はじめに
皆さん、こんにちは!
「運動した日は、ちょっとくらい甘い飲み物を飲んでもいいよね…?」
そんなふうに思うこと、ありませんか?
わたしもランニングや筋トレを終えたあとに、「汗もかいたし、これくらい大丈夫」と思って、ついスポーツドリンクやフルーツジュースを手に取っていました。
運動で消費した分を、少しだけご褒美感覚で補っていたんです。
でも最近、ある研究を読んでその考えが一変しました。
本日ご紹介するのは、アメリカの臨床栄養学専門誌『The American Journal of Clinical Nutrition』に掲載された研究です。
アメリカで約10万人を30年以上追跡した大規模な調査から、「運動をしていても、砂糖入り飲料は心臓病リスクを高める」という、見過ごせない結果が明らかになったのです。
今回は、その研究をもとに、「飲み物の選び方が健康に与える影響」について、わかりやすくお伝えしていきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Sugar-sweetened or artificially-sweetened beverage consumption, physical activity, and risk of cardiovascular disease in adults: a prospective cohort study”
(砂糖入り飲料または人工甘味飲料の摂取、身体活動と心血管疾患リスクとの関係:前向きコホート研究)
Am J Clin Nutr. 2024 Mar;119(3):669-681.
PMID: 38185281 DOI: 10.1016/j.ajcnut.2024.01.001
掲載雑誌:The American Journal of Clinical Nutrition(アメリカ臨床栄養学雑誌)【アメリカ】 2024年1月
研究の目的
この研究では、普段よく飲む甘い飲み物——たとえば清涼飲料水や“ゼロカロリー”と書かれた人工甘味飲料——が、心臓病や脳卒中といった病気のリスクにどのような影響を与えるのかを詳しく調べています。
特に注目したのは、「たとえ運動をしっかりしていたとしても、甘い飲み物の影響を帳消しにできるのか?」という点。
これまでの研究では、運動は“その他の影響要因”として扱われることが多く、本当に「飲み物と運動の組み合わせ」でどんな健康リスクが生まれるのかは、よくわかっていませんでした。
そこでこの研究では、甘い飲み物の摂取量と運動量を組み合わせて分析し、それぞれの影響を独立して、そして重ね合わせた場合にどうなるかを明らかにしようとしています。
また、人工甘味飲料のリスクについても、砂糖入り飲料とは別に検証することで、「ゼロカロリー飲料なら安心なのか?」という疑問にも答えようとしています。
研究の対象者と背景
今回の研究は、アメリカで長年続けられている2つの大規模な健康調査データを活用しています。対象となったのは、以下の2つのグループです:

・看護師健康調査(NHS:Nurses’ Health Study):1980年から開始、対象は30〜55歳の女性看護師 約6.5万人
・医療従事者追跡調査(HPFS:Health Professionals Follow-up Study):1986年から開始、対象は40〜75歳の男性医療従事者 約3.9万人
この2つのグループを合わせた、合計約10万5千人が、最大36年間にわたり追跡調査されました。
彼らは定期的に「食生活」「運動習慣」「健康状態」などを自己申告で記録しており、それをもとに研究者が病気の発症状況を分析しています。
対象者はアメリカの白人が中心で医療知識がある職業層ではありますが、飲料の摂取や運動習慣に関する結果は日本人にも十分参考になります。

研究の手法と分析の概要
この研究は「前向きコホート研究」と呼ばれる方法で、参加者の生活習慣と病気の発症を長期にわたって追跡しました。
分析の流れは以下の通りです。
主な研究デザイン
・調査期間:NHSは1980年〜2016年、HPFSは1986年〜2016年
・対象者数:女性65,730人、男性39,418人(合計105,148人)
・除外基準:調査開始時にがん、糖尿病、心臓病などを持っていた人は除外
データ収集
・飲料の摂取頻度:4年ごとに、ジュースや人工甘味飲料などの摂取頻度を自己申告
・運動習慣:2年ごとに、ウォーキングやランニングなどの活動時間を記録
・心血管疾患の診断:自己報告と医療記録から、心臓病・脳卒中の発症を確認
統計解析
・「砂糖入り飲料の摂取量」「運動量」と「心血管疾患の発症リスク」の関係を、コックス比例ハザードモデルという方法で解析
・「飲み物だけ」「運動だけ」「両方組み合わせた場合」の3パターンでリスクを算出

【補足:使われた統計手法】
前向きコホート研究
長期間にわたり、人々の生活と病気の関連を観察する研究法。
因果関係のヒントを探るのに向いている。
コックス比例ハザードモデル
生活習慣と病気リスクとの関係を統計的に算出する手法。
リスクを「ハザード比(HR)」という数値で表現。
ハザード比(HR)
発症リスクの高さを示す指標。
1.0が基準で、それ以上ならリスクが高い、未満なら低い。
このように、長期・大規模・詳細なデータを用いたことで、信頼性の高い結果が得られたと評価されています。
【補足:各種用語】
・SSB(Sugar-Sweetened Beverage)=砂糖入り飲料
→ 一般的な清涼飲料水、炭酸飲料、フルーツジュース、エナジードリンク、スポーツドリンクなど。砂糖が加えられていて、カロリーもある飲み物を指します。
例:コーラ、オレンジジュース、ミルクティー、スポーツドリンクなど
・ASB(Artificially Sweetened Beverage)=人工甘味飲料
→ 砂糖の代わりに人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)を使って甘みを出し、カロリーを抑えた飲み物。ゼロカロリーやダイエット飲料とも呼ばれます。
例:ダイエットコーラ、ゼロカロリーサイダー、無糖エナジードリンクなど
研究結果:運動しても“ジュース”の影響は消せない——心臓と脳に潜むリスク
最も衝撃的だったのは、たとえ運動をしっかりしている人でも、砂糖入り飲料(SSB)をよく飲む人は心臓病や脳卒中のリスクが確実に高くなっていたという事実です。
研究では、SSBを1日2回以上飲む人は、ほとんど飲まない人に比べて心血管疾患の発症リスクが21%高いという結果が出ました。
これは運動の有無にかかわらず当てはまり、「運動していれば甘い飲み物も大丈夫」という考え方が通用しないことが示されました。
また、運動をしていない人がSSBをよく飲む場合は、さらにリスクが高く(47%増)、日常的な飲み物の選択が将来の健康に大きく影響することが浮き彫りになりました。
| 身体活動の有無 | SSB摂取量 | 心血管疾患リスク(HR) |
| 運動している | ほとんど飲まない(<1回/月) | 1.00(基準) |
| 運動している | よく飲む(≥2回/日) | 1.21(21%増) |
| 運動していない | よく飲む(≥2回/週) | 1.47(47%増) |
その他の注目ポイント
・人工甘味飲料(ASB)と病気の関係は限定的
ASBについては、全体として明確なリスク上昇は見られませんでした。
ただし、脳卒中の一部では、軽度のリスク上昇の傾向(P=0.07)も確認されており、完全に無害とは言い切れません。
・運動そのものは心血管リスクを下げる効果がある
飲み物の悪影響を打ち消せるわけではありませんが、運動をしている人の方が全体的にリスクは低かったという結果も出ており、運動習慣の大切さも同時に示されています。
・男女ともにリスク上昇の傾向は一貫していた
男性・女性いずれにおいても、SSBの多量摂取でリスクは上昇していました。
・心臓だけでなく脳にも影響
SSBの多量摂取は、心筋梗塞などの冠動脈疾患だけでなく、脳卒中のリスクも高めることが明らかになっています。
このように、飲み物の選び方は心臓と脳、両方の健康に直結することが分かりました。

研究の結論
この研究が伝えていることは、
✅どれだけ身体を動かしていても、長期的に砂糖入り飲料(SSB)を多く飲み続けると、心臓や脳の病気のリスクは確実に高くなる
という明確な結果です。
ただし、ここで誤解してはいけないのは、「1回飲んだだけで体に悪い」という話ではないということです。
問題なのは、“日常的な習慣として”甘い飲み物を長年飲み続けることです。
一方で、人工甘味飲料(ASB)に関しては、今回の研究では明確なリスク上昇は確認されなかったものの、脳卒中に関してわずかにリスクが高まる傾向が見られたという指摘もありました。
この点について著者らは、「ASBは安全であると結論づけるには、まださらなる研究が必要」としています。
したがって、現時点では「ASBなら安心」と言い切ることはできません。
人工甘味飲料をどう捉えるかは、今後の研究を踏まえながら、個人の判断とバランス感覚に委ねられている段階です。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点
日本でも、甘い飲み物はとても身近な存在ですよね。
つい気分転換に買ってしまったり、運動後のご褒美として飲んだりする人も多いと思います。
わたし自身も「頑張ったからこれくらい」と思って飲んでいた時期があります。
でもこの研究は、「どれだけ運動していても、日常的に砂糖入り飲料をたくさん飲んでいるとリスクがある」という、少しショッキングな事実を教えてくれました。
だからといって、「ジュースは絶対ダメ!」という話ではありません。
たまの楽しみや嗜好品として飲むことまで否定されているわけではなく、日常的な飲み過ぎに気をつけましょう、というメッセージです。
また、人工甘味飲料については「明確な悪影響は示されなかったけれど、安心して無制限に飲んでいいとは言えない」という中立的な結果が出ています。
著者らも「今後さらに研究が必要」としており、わたしたちも“安全だと信じて大量に飲む”というよりは、「控えめに、必要に応じて」くらいの姿勢がよいのではないかと思います。
結局のところ、甘い飲み物とどう付き合うかは、自分自身の健康観と生活スタイルに合わせた“バランス”が大切。
この研究は、その判断材料として非常に有益なヒントを与えてくれます。

まとめ
今回紹介したのは、アメリカで約10万人を30年以上追跡した大規模な研究です。
その結果、たとえ運動をしていたとしても、砂糖入り飲料を日常的にたくさん飲んでいる人は、心臓や脳の病気のリスクが高まることが明らかになりました。
一方で、人工甘味料入り飲料については明確な悪影響は示されませんでしたが、「安心してたくさん飲んでよい」とは言えない段階です。
どちらの飲み物も、「毎日・何年も続けて摂取すること」が問題であり、たまの楽しみとして味わう分には、過度に心配する必要はありません。
この研究を通してわたしが感じたのは、「飲み物の選び方も、健康を守るひとつの習慣」だということ。
特別な日にはジュースを楽しんで、普段は水やお茶でリフレッシュする。そんな無理のない“ゆるやかな選択”が、心と体の健康につながるのだと思います。
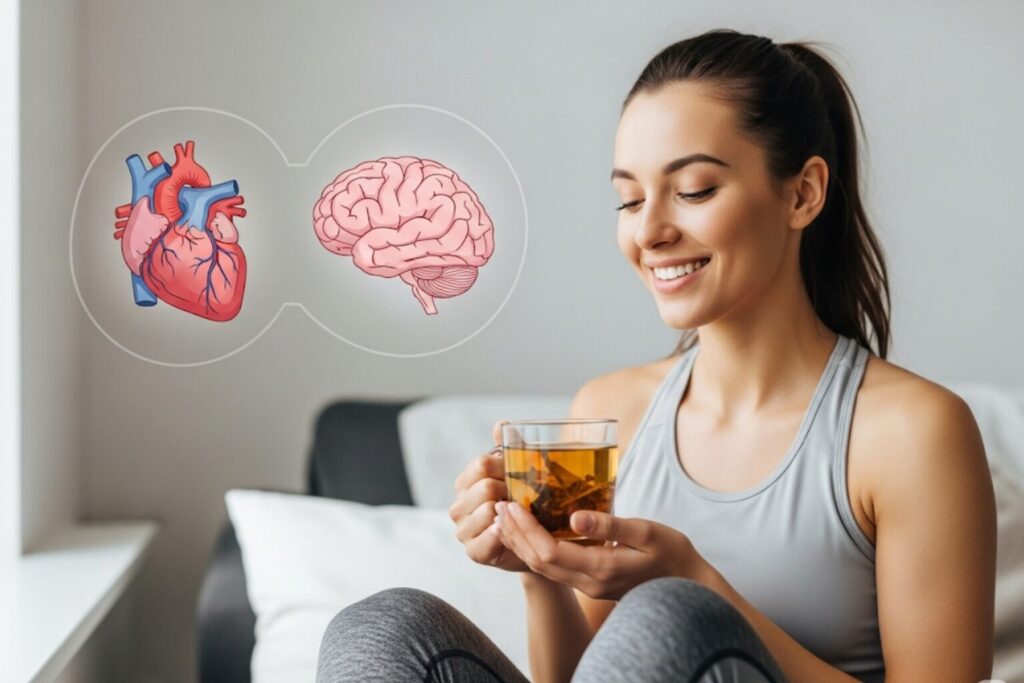
締めのひとこと
“今日なにを飲むか?”小さな選択が、大きな未来をつくります。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント