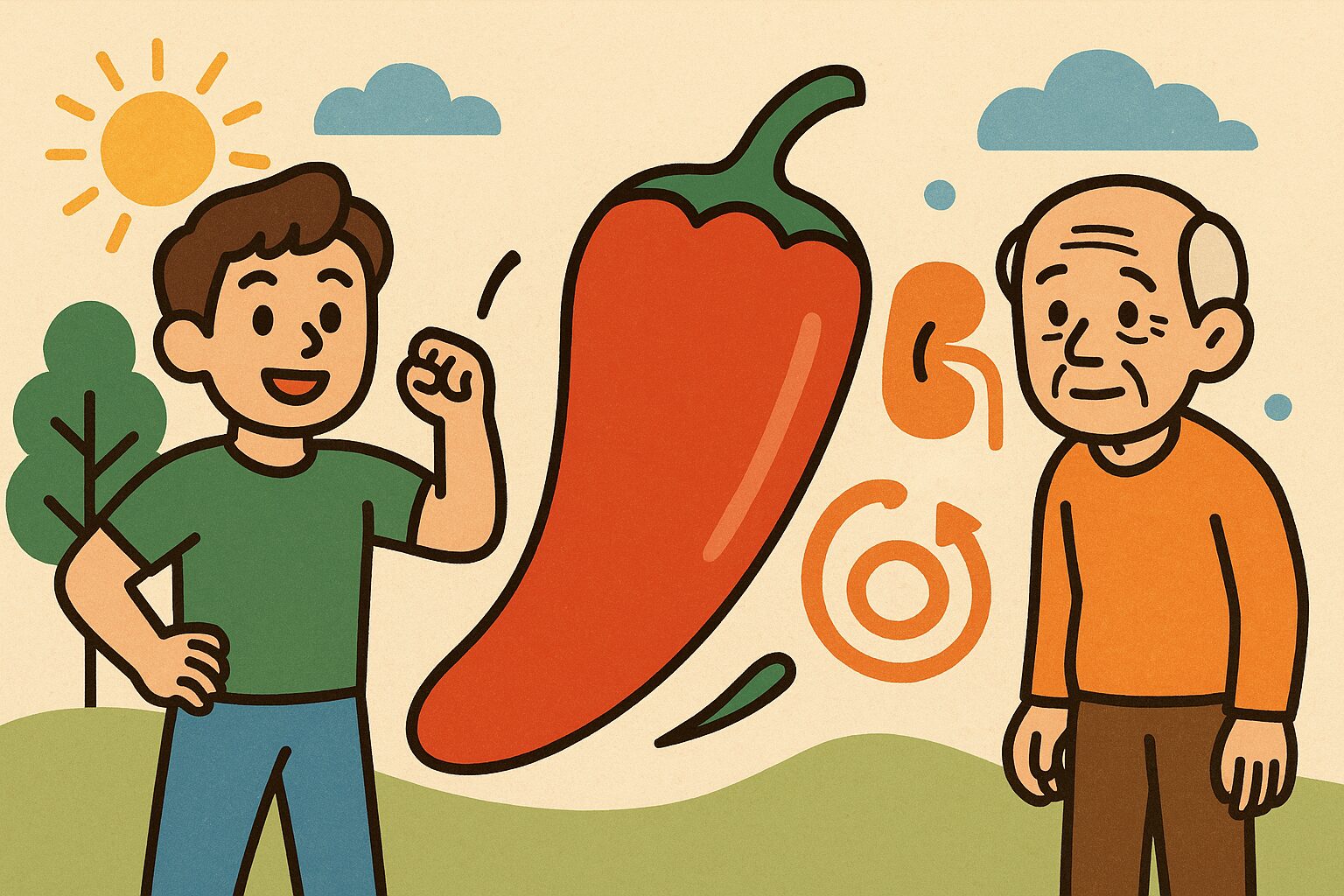
結論「週3〜5回の辛い食品の摂取は、生物学的老化をゆるやかにし、とくに腎臓と代謝の健康に良い影響を与える可能性がある」
この記事はこんな方におすすめ
✅辛い物や唐辛子が好きで、体に悪くないか心配な方
✅年齢とともに代謝や腎臓の健康が気になっている方
✅健康寿命を少しでも延ばし、若々しさを保ちたい方
✅食事でアンチエイジングを取り入れたい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:辛い物って体にいいの?
🟡結果:週3〜5回の摂取で体の老化が約0.7年遅く、腎臓では約1.9年も若い傾向
🟢教訓:辛すぎや毎日よりも「ほどほど」がポイント。食べすぎは逆効果の可能性も。
🔵対象:中国の30〜80歳の約7,800人を追跡。日本人でも一部は応用できるが、辛さへの耐性や胃腸の違いに注意。
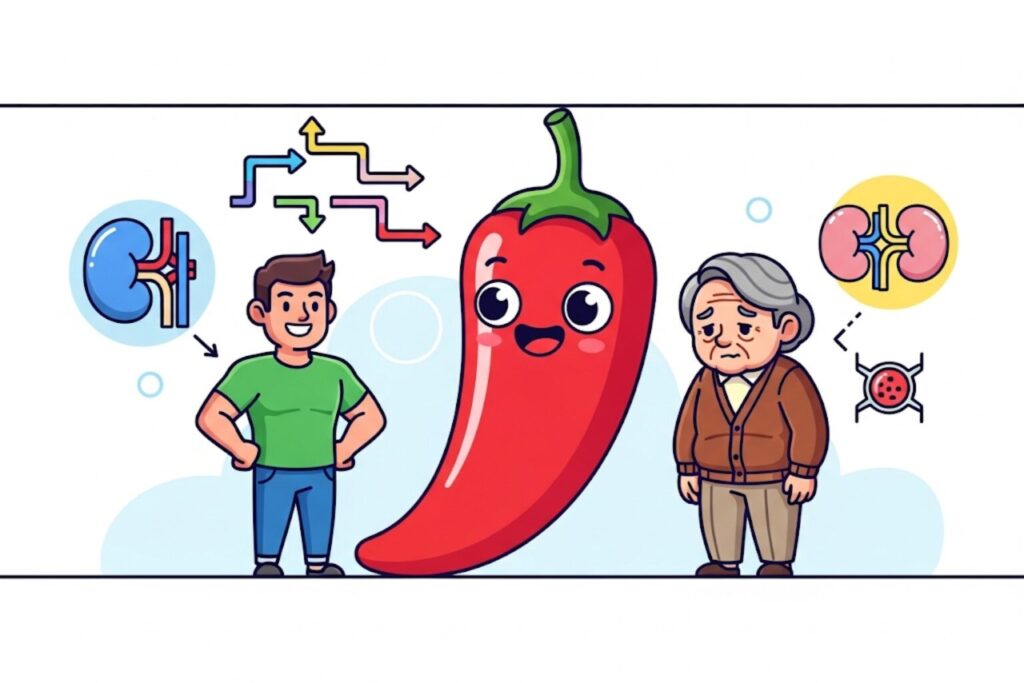
※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
みなさん、辛い食べ物はお好きですか?
わたしは辛いもの大好きなんです
例えば、ラーメン屋さんに行くとつい辛い系のメニューばかり頼んでしまいます。
そのせいで、お店の看板メニューを一度も食べたことがない、なんてこともしばしば。
以前に「辛い食べ物をよく食べる人は心筋梗塞や脳卒中のリスクが下がる」という研究をご紹介しました。
今回はさらに夢のあるテーマです。
なんと「辛い物好きは体の年齢まで若くなるかもしれない」というお話。
この研究は、イギリス発の栄養学専門誌『Nutrition Journal(栄養学ジャーナル)』に掲載された、中国で行われた大規模な疫学調査の結果です。
今回はその内容を、一緒に読み解いていきましょう。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Spicy food consumption and biological aging across multiple organ systems: a longitudinal analysis from the China Multi-Ethnic cohort”
(辛い食品の摂取と複数臓器系にわたる生物学的老化:China Multi-Ethnic Cohort を用いた縦断解析)
Ning Zhang, Feng Hong, Yi Xiang et al.
Nutr J. 2025 May 23;24(1):86.
PMID: 40410899 DOI: 10.1186/s12937-025-01147-z
掲載雑誌:Nutrition Journal【イギリス:IF 4.4(2024)】 2025年5月
研究の要旨
研究目的
辛い食品を食べる頻度と、体の実際の老け具合(生物学的な老化)の関係を調べた。
研究方法
中国西南部の30〜80歳・7,874人を対象に、2018〜2021年に辛い食品の摂取頻度と血液・体の検査結果を分析した。
研究結果
週3〜5回食べる人は老化が約0.7年遅れ、特に腎臓では1.9年若い傾向がみられた。
結論
辛い食品を適度に食べると、老化の進み方が緩やかになる可能性がある。
考察
効果は週3〜5回が最も強く、食べすぎても頭打ち傾向で、今後は因果関係の検証が必要。
研究の目的
この研究は、「辛い食べ物を食べる習慣が、体の老化の進み方を緩やかにするのかどうか」を確かめることを目的としています。
老化は多くの病気の出発点ですが、生まれてからの年数だけでは本当の老け具合を表せません。
血液検査や体の機能から算出できる臓器ごとの“体内の年齢”と、辛い食品の摂取頻度の関係を調べました。
さらに、唐辛子の成分であるカプサイシンが炎症や代謝の異常といった老化の特徴に関わる可能性があることから、
「辛い食品が老化を遅らせるかもしれない」という仮説を立て、その検証に挑んだものです。
研究の対象者と背景
この研究は、中国西南部で行われている大規模調査「中国多民族コホート研究(China Multi-Ethnic Cohort)」の一部として実施されました。

対象者の特徴は以下の通りです。
基本情報
・人数:7,874人
・年齢:30〜80歳
・性別:男性 61%(4,844人)、女性 39%(3,030人)
民族構成
・漢民族:65%(5,115人)
・少数民族:35%
※生活習慣が大きく異なるチベット族は除外
居住地
・都市部:38%
・農村部:62%
社会背景
・教育歴:中学・高校卒業 42%、大学卒 12%
・婚姻状況:約90%が既婚
生活習慣
・喫煙:吸わない人 76%、現在喫煙中 19%
・飲酒:ほとんどしない人が多数
・食生活:健康的な食事パターンをとる人が43%

研究の手法と分析の概要
この研究は、人々の食習慣と健康状態を時間を追って追跡しています。
研究デザイン
・研究方法:前向きコホート研究(一定の集団を長期間追跡して観察する方法)
・期間:初回調査 2018〜2019年、追跡調査 2020〜2021年
食習慣の評価
・方法:質問票で「辛い食品を食べる頻度」を調査
・分類:
1.食べない
2.週1〜2回
3.週3〜5回
4.週6〜7回
注意点:辛さの「強さ」や「量」は定量化されておらず、例えば「激辛を少量」でも「中辛を多め」でも同じカテゴリーに入ってしまいます。
人によって辛さへの耐性も異なるため、この点は今後の研究課題とされています。

老化の評価
測定内容
血液検査や身体測定から得られる15種類の指標を使用
・腎臓機能(クレアチニン、尿酸)
・肝臓機能(ALT、AST)
・代謝状態(血糖値、脂質、尿酸)
・肺や心臓の機能(肺活量)
・その他(血圧、BMI、血中アルブミン)
👉 見た目ではなく臓器や代謝のデータから「体の年齢」を推定している。
算出方法
15の指標を統計モデル(Klemera–Doubal法)に入力し、実年齢との差から「老化の加速度」を算出。
例:50歳の人が48歳相当なら「老化が遅い」、53歳相当なら「老化が早い」。
👉 つまり、この研究では「血液や体の検査15項目を総合して“体の健康年齢”を出し、実際の年齢との差を見る」という仕組みです。
統計的な分析
この研究では 多変量線形回帰分析 を用い、年齢、性別、体格指数(BMI)、喫煙や飲酒、教育歴、居住地、食生活などを同時に調整し、辛い食品の摂取と老化の進み方の関係を評価しました。
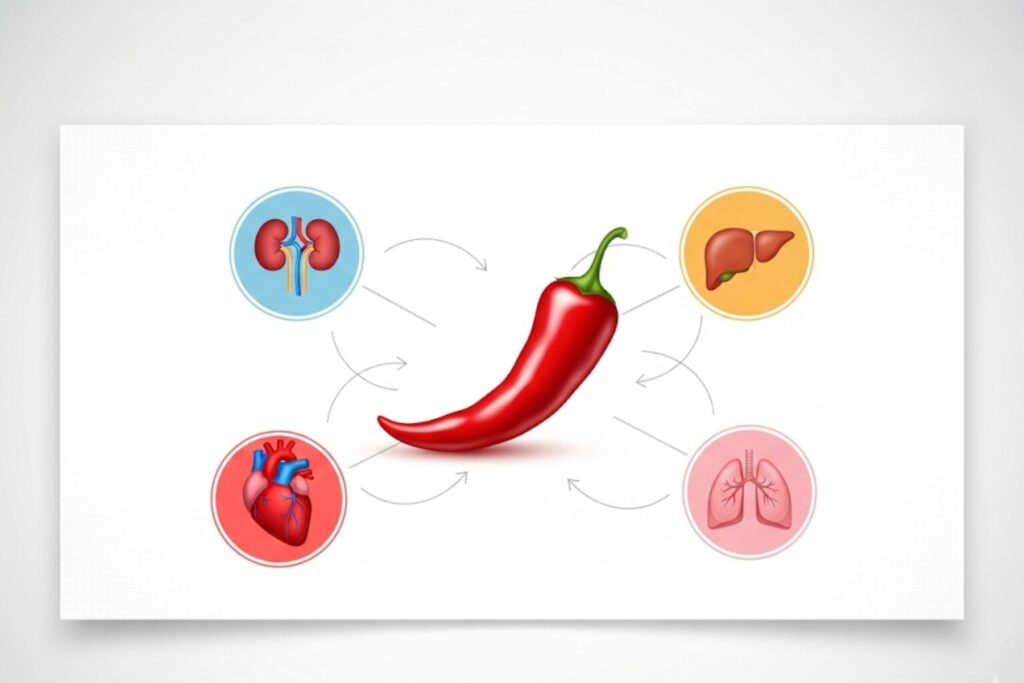
研究結果
全体の傾向
辛い食品を食べる人は、食べない人に比べて「体の年齢(生物学的老化)」が若い傾向にありました。
最も効果が強かったのは 週3〜5回 食べる人です。
数値で見た変化
| 辛い食品の頻度 | 体の年齢の変化(実年齢との差) |
| 食べない | 基準 |
| 週1〜2回 | 約0.23年 若い |
| 週3〜5回 | 約0.69年 若い |
| 週6〜7回 | 約0.32年 若い |
👉 効果は「週3〜5回」で最大。
毎日食べても直線的に良くなるわけではなく、むしろ弱まる傾向がありました。

臓器ごとの結果
・腎臓:週3〜5回で約1.9年分 若い
・代謝機能:同じく約0.76年分 若い
・心臓・肺・肝臓:大きな差はなく、統計的に有意でない場合もあった(=悪化はしていない)
個人や背景による違い
・女性は男性よりも効果が強い
・漢民族は非漢民族よりも効果が強い
・健康的な食生活をしている人ほど効果が大きい
結果の信頼性
病歴のある人を除外した場合や、食事評価の基準を変えても結果はほぼ同じで、一貫した傾向が確認されました。

研究の結論
主な結論
✅️辛い食品を食べる頻度が高い人ほど体の年齢が若い傾向にあり、とくに 週3〜5回食べる人は実年齢より平均0.7年若い ことがわかりました。
臓器ごとの特徴
✅️腎臓は最大で約1.9年若い
✅️代謝機能は約0.8年若い
一方で心臓・肺・肝臓では有意な差はみられませんでした
辛い食品を「週に数回」食べることで、体の年齢を1年前後若く保てる可能性があると結論づけられました。

【礼次郎の考察とまとめ】
著者による考察のポイント
著者らはこれらの結果について以下のように考察しています。
効果が強かった臓器(腎臓・代謝系)
腎臓や代謝系は体の恒常性を保つ重要な役割を担い、老化の影響を受けやすい。
辛い食品が作用する「TRPV1」という受容体は腎臓や脂肪組織、血管内皮などに分布し、ナトリウム排泄促進、脂質の蓄積抑制、血管の拡張改善などをもたらすため、腎臓や代謝の老化を緩める可能性がある。
性別・民族・食習慣による違い
女性、漢民族、健康的な食生活を送る人で効果が強かった。
これは遺伝的背景やホルモンの影響、食事の全体的な質との相互作用による可能性がある。
「週3〜5回」が最適な頻度
それ以上増やしても効果が強くならなかった。理由として、
① TRPV1受容体が辛味の刺激で慣れてしまう(脱感作)
② 有効成分の利用効率が飽和する
③ すでに辛い食品を常習的に食べている人は「頭打ち」状態になっている可能性がある
カプサイシンの作用メカニズム
抗炎症作用、血糖や脂質代謝の改善、腸内フローラの調整、抗酸化作用など。
「老化の特徴」とされる慢性炎症や腸内環境の乱れに働きかけることが考えられる。
研究の限界
辛さの強さや量を正確に定量化できていない点、自己申告によるデータゆえ誤差の可能性、多民族・多文化地域特有の食習慣の影響なども残る。

日常生活へのヒント
著者らは、唐辛子の成分カプサイシンが炎症を抑えたり代謝を改善したりする可能性を指摘しています。
とくに腎臓や代謝で効果が強かったのは、この成分が塩分の排出や脂肪のコントロールに関わるためだと考えられます。
こうした知見から、私たちの生活に活かせるポイントは次のとおりです。
適度な頻度がカギ
研究では「週3〜5回」で最も効果が強く、毎日食べても効果が頭打ちになっていました。
無理なく続けられる頻度で取り入れることが大切です。
取り入れ方の工夫
激辛料理に挑戦する必要はなく、普段の食事に唐辛子を少し加えるだけで十分です。
キムチやスープにひとふりなど、日常の延長で続けるのが一番です。
体調に合わせる
辛い食品は胃腸に負担になることもあります。
効果には個人差があるので、自分の体調に合わせて量や頻度を調整しましょう。
食事全体のバランス
辛い食品だけでなく、野菜や魚などを含むバランスのよい食事と組み合わせてこそ効果が期待できます。
辛さはあくまで健康を支える「スパイス」と考えるとよいでしょう。
👉「辛さはほどほどに、日常に無理なく取り入れる」ことが健康へのヒント。
辛さそのものよりも、バランスのとれた食生活の中で楽しむことが大切ですね。

締めのひとこと
ほどほど辛さで、簡単アンチエイジング!
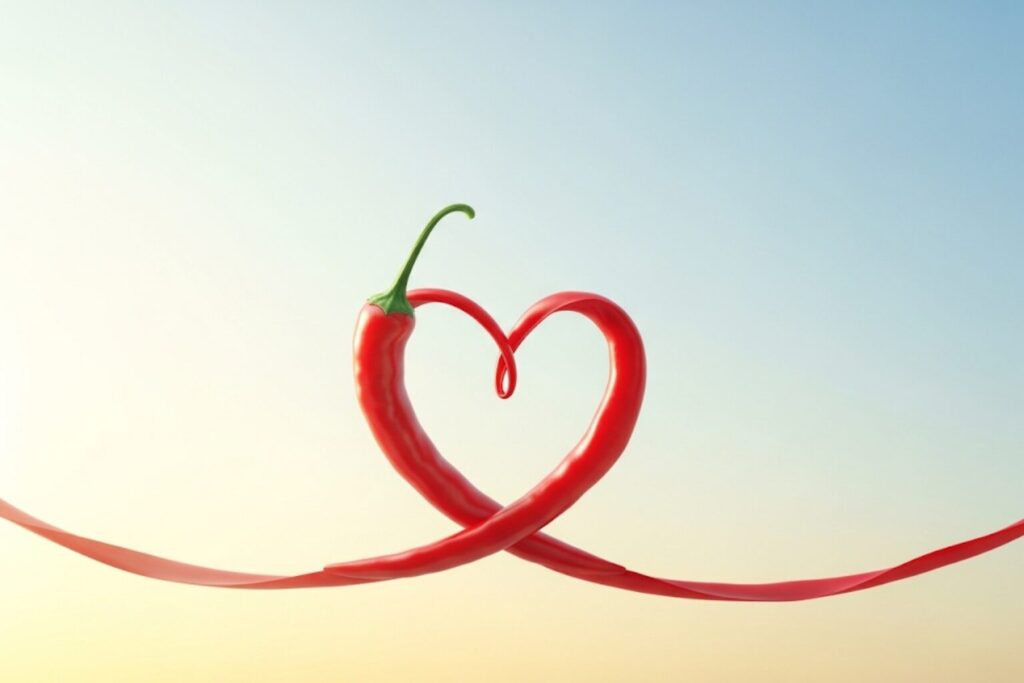
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。



コメント