
結論「『筋トレ=筋肉が増える』ではなかった!?“使っていない筋肉”は静かに減っていた──栄養不足が拍車をかける可能性も」
この記事はこんな方におすすめ
✅筋トレで「部分的に筋肉が落ちてる…?」と感じたことがある方
✅ダイエット中の筋トレ効果に不安がある方
✅特定の部位だけ鍛えるトレーニングをしている方
✅高齢者・リハビリ中の方の筋力維持に関心がある方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:筋トレしてるのに、筋肉が減ってる気がする…それってあり得る?
🟡結果:実際に“使ってない筋肉”は少しずつ減ることがあると分かりました。特に栄養が足りないとその傾向が強まります。
🟢教訓:筋トレ中は「鍛えてる筋肉だけでなく」「使っていない筋肉」にも目を向け、バランスよく動かし、十分な栄養を取ることが大切です。
🔵対象:ベルギーの若年成人21名が対象。日本人にも応用できる普遍的な現象です。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
筋トレを頑張っているのに「なんだか筋肉も減ってる気がする…」そんな違和感を覚えたことはありませんか?
実はわたしは以前、CMでもおなじみの某有名パーソナルジムに通い、糖質制限をしながら筋トレに励んでいた時期がありました。
そのとき、体組成計でチェックするたびに、脂肪は確かに減っているのに、筋肉量も一緒に減っていたんです。
とはいえ、しっかり痩せて結果が出ていたので「まあいいか」と深く考えずにいました。
でも最近、この論文を読んで数年越しにあの謎がようやく腑に落ちたんです。
本日ご紹介するのは、
筋トレ中に“使っていない筋肉”が実はひそかに減っている
──そんな驚きの事実を明らかにした最新の研究です。
この論文は、アメリカの運動医学専門誌『Medicine & Science in Sports & Exercise』に掲載され、ベルギーの研究チームによって行われたもの。
今回はその内容を、わかりやすく解説していきます!

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Evidence for Simultaneous Muscle Atrophy and Hypertrophy in Response to Resistance Training in Humans”
(レジスタンストレーニングに対する筋肥大と筋萎縮の同時発生に関するエビデンス(ヒトにおける観察))
Med Sci Sports Exerc. 2024 Sep 1;56(9):1634-1643.
PMID: 38687626 DOI: 10.1249/MSS.0000000000003475
掲載雑誌:Medicine & Science in Sports & Exercise【アメリカ】 2024年9月
研究の要旨
研究目的
レジスタンストレーニング中に非動員筋に何が起こるのかを明らかにする。
研究方法
21名のトレーニング未経験者に10週間の単関節トレーニングを実施。MRIにより17個の動員筋と13個の非動員筋の体積を測定。食事は自由摂取とし記録された。
研究結果
動員筋は全て有意に肥大。一部の非動員筋(大内転筋とヒラメ筋)は有意に萎縮。非動員筋の萎縮はエネルギー・タンパク質摂取と有意な関連。
結論
トレーニング中、筋量は動員筋で増加しつつ、非動員筋で減少する「筋量の再配分」が起こる可能性がある。
研究の目的
この研究の目的は、レジスタンストレーニング(筋トレ)をしているとき、鍛えていない筋肉(非動員筋)がどう変化するかを明らかにすることです。
筋トレをすると、使った筋肉(動員筋)が大きくなることはよく知られています。
でも、「じゃあ、それ以外の筋肉は?」という素朴な疑問には、これまでの研究ではほとんど答えがありませんでした。
また、筋肉を増やすには大量のエネルギーとタンパク質が必要ですが、もし栄養が十分に足りていなかった場合、
身体が限られた資源を“使った筋肉に集中させ”、使っていない筋肉を“減らす”のではないか?
という仮説が立てられました。
その“筋肉の再配分”が実際に起きているのかどうか
──今回の研究は、そんなこれまで見過ごされてきた疑問に初めて正面から挑んだものです。
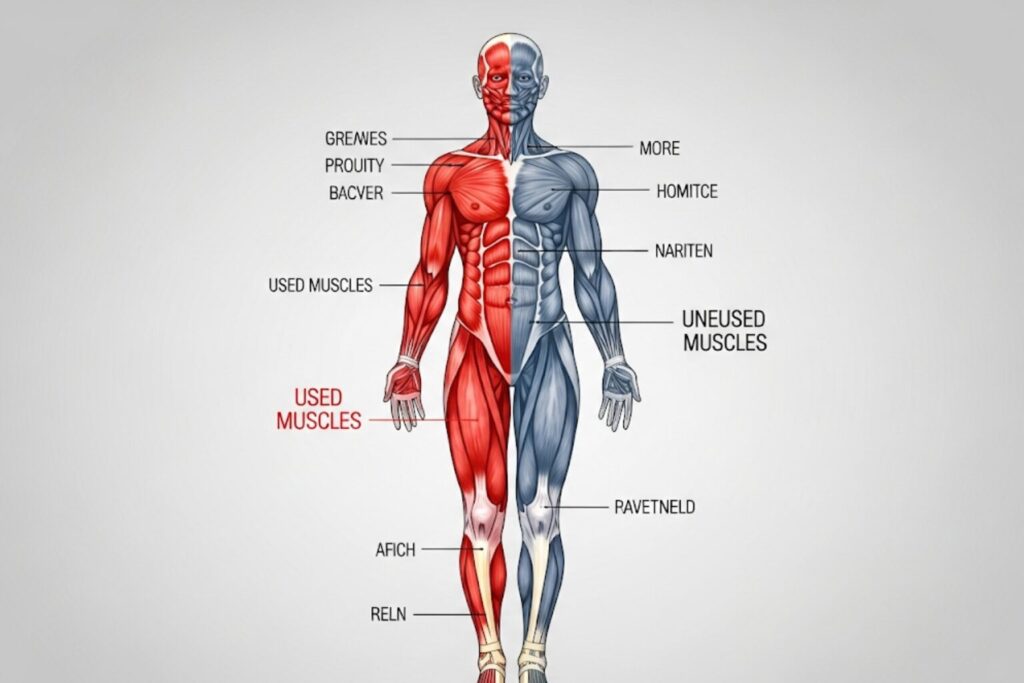
研究の対象者と背景
この研究は、ベルギーのゲント大学で行われ、21名(男性11名・女性10名)の若い成人(平均年齢22歳)が対象となりました。

全員が過去に本格的なレジスタンストレーニング(筋トレ)の経験がない初心者で、日常的な運動習慣もない一般的な健康成人です。
さらに、女性はホルモンバランスの影響を避けるため、経口避妊薬を継続的に服用している方のみが参加。
心臓病や神経疾患などの持病がある人、サプリや薬を常用している人は除外されました。
参加者は自由に食事を摂ってよく、特にエネルギー制限や高タンパク食などの制限はされていません。
そのため、「普段どおりの生活でトレーニングを始めた場合にどうなるか?」という実態に近い条件で観察されています。
今回の対象者はヨーロッパの若年成人であり、体格や筋肉量の平均はやや高めです。
ただし、「使っていない筋肉が減るかも」というメカニズム自体は人種を問わず起こり得る普遍的な現象と考えられます。
特に、筋肉量が少なめな傾向にある日本人では、より一層注意が必要ともいえるでしょう。

研究の手法と分析の概要
この研究は、10週間にわたる介入型の実験研究です。
参加者は週2〜3回、単関節のレジスタンストレーニング(例:腕の曲げ伸ばし、脚の曲げ伸ばし)を行いました。
特徴的なのは、左右の手足を別々の頻度(週2回 vs 週3回)で鍛えるという工夫です。
これにより、より多くの筋肉の変化を1人の中で比較できる設計になっています。
筋肉の変化は、トレーニングの開始前と10週間後の2回だけMRIで計測。
トレーニングごとの変化ではなく、全体を通してどれだけ筋肉が増減したかを評価しています。
トレーニング内容
・上腕(腕)と大腿(脚)の単関節トレーニングを実施
・ダンベルでのアームカール、レッグエクステンションなど
・毎回60%の最大負荷(1RM)で、筋肉が疲れるまで3〜4セット
・セット間の休憩は2分、運動間の休憩は3分
栄養の記録
・期間中、日常の食事内容を3回にわけて自己記録(日記形式)
・摂取したカロリー・タンパク質・炭水化物・脂肪を、ベルギーの公式栄養ソフトで分析
分析方法
・筋肉は30部位(上肢と下肢)を個別に測定
・鍛えた筋肉(動員筋)、その周辺の筋肉(補助筋)、鍛えていない筋肉(非動員筋)に分類
・MRI画像から筋肉の体積変化をAIと手作業の組み合わせで高精度に算出
・栄養摂取と筋肉変化の関係も、相関分析で評価

【補足:各種用語】
レジスタンストレーニング(Resistance Training)
筋肉に負荷をかけて鍛える運動のこと。ダンベルやマシンを使う筋トレが代表例です。
単関節運動(Single-joint exercise)
ひざやひじなど、1つの関節だけを動かすトレーニング。対象の筋肉が明確に分かるメリットがあります。
1RM(ワンレップマックス)
1回だけ上げられる最大重量。たとえば「30kgを1回だけ持ち上げられる」なら1RMは30kgです。
MRIによる筋体積の測定
MRI画像を用いて、筋肉の大きさ(断面積や体積)を立体的に可視化します。とても精度が高く、実際の筋肉の増減を正確に把握できる方法です。
研究結果
筋トレして増えた筋肉の影で、“減っていた筋肉”もあった
この研究では、トレーニングで使った筋肉はしっかり増えていた一方で、
使わなかった筋肉が同時に減っていた
という、意外な現象が明らかになりました。
筋肉の使われ方と変化量
筋肉は「どれだけ使われたか」によって以下のように分類されました:
| 筋肉の分類 | 平均の変化量 | 内容 |
| 動員筋(積極的に使った) | +6.5% | 上腕二頭筋、大腿四頭筋など |
| 補助筋(少し動いた) | +2.4% | 間接的に関与 |
| 非動員筋(使われなかった) | -1.9% | 明確な活動なし |
これらの変化は統計的に有意であり、筋肉は“使ったかどうか”で明確に変化したことが示されました。
拮抗筋(反対の筋肉)はどうなっていたのか?
例えば、上腕二頭筋を鍛えると、反対の上腕三頭筋がどうなるかは気になるところですが、
この研究では、拮抗筋が特に減少したとは明記されていません。
ただし、“使わなかった筋肉は全体的に減っていた”という結果があり、
拮抗筋も含め、意識的に動かしていない筋肉は静かに減っていく可能性があることが示唆されました。
栄養状態が影響していた
参加者の平均的な栄養摂取状況
| 栄養指標 | 平均値 | 解説 |
| エネルギー摂取量 | 約31 kcal/kg/日 | 筋肥大にはやや不足傾向 |
| タンパク質摂取量 | 約1.1 g/kg/日 | 推奨量(1.6〜2.2 g/kg/日)を下回る |
これにより、摂取量が少ない人ほど非動員筋の減少が大きいことが示されました。
さらに興味深いことに、もともと筋肉量が多かった人ほど、“使わなかった筋肉”の減少が大きいという傾向が見られました。
これは、「身体が不要と判断した筋肉は優先的に減らす」ような、“省エネの仕組み”が働いている可能性を示しています。
頻度より“使われたかどうか”が重要
左右で週2回と週3回のトレーニングを比較しても、明確な差は見られませんでした。
これは、「週に何回鍛えたか」よりも、「その筋肉を実際に使ったかどうか」が変化を左右するという重要な示唆です。
つまり、“トレーニング頻度が多い=必ずしも効果的”とは限らず、筋肉がどれだけ刺激を受けたか(動員されたか)がカギだったということ。
この視点は、「量より質」を意識したトレーニング設計の重要性を裏付けています。
個人差も大きかった
全体的な傾向としては“使わない筋肉が減る”という結果でしたが、
中には非動員筋が減らなかった人や、微増していた人も存在しました。
栄養・初期筋量・日常の動作のクセなどの個人差が影響していたと考えられます。
減量していないのに筋肉が減っていた
この研究では、食事制限や減量プログラムはありませんでした。
それでも、体重が変わらずとも筋肉が局所的に減っていたというのは重要な発見です。
つまり、体重や筋肉量の合計だけではわからない“中身の変化”が起きていたのです。
加齢による筋力低下(サルコペニア)と似た傾向
筋肉が“使わない部位から減っていく”という現象は、サルコペニアの初期段階でも見られるものです。
この研究結果は、若年者でも、減量していなくても、同様の現象が起こる可能性を示しています。
実践的な気づき
✅️見た目が変わらなくても、使っていない筋肉は減っているかもしれない
✅️拮抗筋や体幹など、意識しにくい筋肉も使う意識が大切
✅️栄養(特にたんぱく質)をしっかりとることも、筋肉を守るカギ
✅️トレーニングは「回数」より「全身のバランスと動員」を重視することが効果的

研究の結論
筋トレ中も筋肉は“増えるだけではない”
この研究で明らかになったのは、
✅️筋トレによって一部の筋肉はしっかり増える一方で、使っていない筋肉は同時に減っているという現象です。
これはつまり、筋トレ=すべての筋肉が強くなるわけではないということ。
“どこをどう使ったか”によって、増える筋肉と減る筋肉が体内で同時に存在するのです。
また、エネルギーやたんぱく質の摂取が少ないと、使っていない筋肉の減少がより顕著になるという傾向も見られました。
つまり、トレーニング効果を最大限にするためには、食事や筋肉の使い方に「偏りがないこと」が大切ということです。

【礼次郎の考察とまとめ】
“使わない筋肉”は、知らない間に減っていく
わたしがこの研究で最も印象に残ったのは、
「筋肉は全体で見てプラスでも、“中身”は足し引きされているかもしれない」
という事実です。
体重や筋肉量の合計では気づけない、“中身の入れ替わり”が体内で静かに進行しているというのは、
とくにトレーニーやボディメイクに励んでいる方にとって、見逃せない視点ではないでしょうか。
また、拮抗筋(反対側の筋肉)や体幹、日常で意識しにくい部位を使っていないと、
それらの筋肉が静かに衰えてしまうということにも、あらためて注意を向けるべきだと感じました。
日本人は欧米人と比べて、もともとの筋肉量が少ないとされます。
そのため、「使わない筋肉を守る」視点は、より重要になるかもしれません。
“好きな筋肉ばかりをひいきせずに、あまり注目しない筋肉や、苦手な種目ともちゃんと向き合うこと”
が、結局はカラダ全体を守り、強くする近道なのかもしれません。
この研究は、筋トレの“穴”に気づかせてくれるヒントに満ちた内容でした。
私自身も「満遍なく動かす」「栄養をきちんととる」という原点を、見直すきっかけになりました。

締めのひとこと
筋肉は裏切らない。でも“置いてけぼり”にされた筋肉もあなたを待ってます。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。
礼次郎のおすすめアミノ酸です!
筋トレ前に必須アミノ酸摂取しましょう!
トレーニングのパフォーマンスも上がりますし、筋肉痛も少なくなる感じがします!
プロテインとはまた違ったスッキリとした酸味が非常に美味しいです!
私の推しは「グリーンアップル味」🍏です!


コメント