
結論「緑茶を毎日5g以上飲む習慣があると、心臓病は約40%、脳卒中は約30%も減る可能性がある──糖尿病かつ肥満の人を対象にした信頼性の高い研究で判明しました。」
この記事はこんな方におすすめ
✅糖尿病や高血圧など、生活習慣病を予防・改善したい方
✅緑茶の「健康効果」を具体的に知りたい方
✅お茶習慣を無理なく続けたい方
✅家族や高齢の両親の健康を気づかっている方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:緑茶って本当に体に良いの?何に効くの?
🟡結果:1日5g以上の緑茶を飲んでいる人は、脳卒中が30%、心臓病が40%少なかった!
🟢教訓:少量でも効果あり。ペットボトルだけでは足りない可能性あり。急須や粉末茶の活用がおすすめ!
🔵対象:糖尿病かつ過体重・肥満の中国人患者(約4,700人)を6年以上追跡した信頼性の高い研究

はじめに
皆さん、こんにちは!
「お茶は健康にいいっていうけど、実際なにに効くの?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
わたしも毎日お茶を飲んでいますし、特保の“脂肪を減らす”って書いてあるペットボトルもよく買います。
でも、正直「本当に効いてるのかな?」って実感はあまりないんです。
とはいえ、いまのところ大きな病気にかかっていないので、悪いことはしていないんだろうなとは思っています。
今回ご紹介するのは、そんなモヤっとした疑問に“数字でしっかり答えてくれる”とても具体的な論文です。
ベルギーの医学雑誌『Archives of Public Health(公衆衛生アーカイブ)』に2024年に掲載された研究で、中国の糖尿病患者を対象に「緑茶の摂取量と心臓病・脳卒中の発症率」の関係を明らかにした内容です。
今回は、この最新の研究をもとに、緑茶の本当の効果と、どう飲めば良いかをわかりやすく解説していきます

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Green tea consumption and incidence of cardiovascular disease in type 2 diabetic patients with overweight/obesity: a community-based cohort study”
(緑茶の摂取と、過体重・肥満の2型糖尿病患者における心血管疾患発症との関連:地域ベースのコホート研究)
Arch Public Health. 2024 Feb 2;82(1):18.
PMID: 38308353 DOI: 10.1186/s13690-024-01242-3
掲載雑誌:Archives of Public Health(公衆衛生アーカイブ)【ベルギー】 2024年2月
研究の目的
この研究の目的は、緑茶を日常的に飲むことが、2型糖尿病をもつ過体重・肥満の人たちにおける心臓病や脳卒中のリスクを下げるのかを明らかにすることです。
糖尿病の方は、心臓や血管の病気にかかりやすいとされており、食事や生活習慣の改善が非常に重要になります。
その中で「緑茶」が注目されているのは、抗酸化作用や血糖の安定化などが期待されているためです。
しかし実際には、「どのくらいの量を」「どれくらいの期間」飲むことで、病気のリスクがどう変わるのか、科学的に示されたデータはこれまでほとんどありませんでした。
そこで本研究では、中国の大規模住民データを用いて、緑茶の摂取量と心血管疾患(CVD)発症リスクとの関連性を詳細に検証。
特に、過体重または肥満という条件を満たした糖尿病患者に限定し、よりリアルな生活背景に即した健康への影響を探っています。

研究の対象者と背景
この研究では、中国江蘇省の地域に住む住民の中から、以下の条件を満たした人が対象となりました。

・2型糖尿病の診断を受けている
・BMIが24以上(=過体重または肥満)である
・年齢や性別、喫煙、運動など、生活背景も把握済み
最終的に、4,756人(男女合計)が解析の対象となりました。
平均年齢は約62歳。研究は、彼らを平均6.27年にわたって追跡しています。
この対象設定は非常に重要で、「糖尿病かつ肥満」という高リスク層に絞ることで、生活習慣改善の効果をはっきりと測定できるようにしているのです。
なお、対象者は全員中国の住民ですが、日本人と同じアジア系であるため、体質や代謝に関する傾向も似ており、この研究結果は日本人にとっても一定の参考になる可能性が高いと考えられます。
研究の手法と分析の概要
この研究は「前向きコホート研究」という手法で行われました。
これは、ある時点で健康状態を把握した人たちを、その後の数年間にわたって追跡し、「どんな人が病気になるのか?」を観察する研究方法です。
研究の流れ
6つのステップで説明します
1.対象者を選ぶ
→ 中国・江蘇省に住む、過体重または肥満で、2型糖尿病の診断を受けた人の中から、4,756名を選びました。
2.開始時に健康状態を詳細に記録
→ 身長・体重(BMI)、血圧、血糖、血中脂質、生活習慣(運動・喫煙・飲酒など)、服薬状況など。
3.緑茶の飲用習慣を質問票で把握
→ 「1日どのくらいの量の茶葉を使っているか?」「それを何年くらい続けているか?」を自己申告で記録。
・0g/日:飲まない
・1〜4g/日:少量
・5g以上/日:多量(今回の注目群)
4.6年以上にわたって病気の発症を追跡
→ 主に、心血管疾患(脳卒中・心臓病など)が新たに発症したかを、健康保険記録や入院歴から確認。
→ 平均追跡期間:6.27年
5.緑茶の摂取量と病気の発症率を比較
→ 「どのくらいお茶を飲んでいた人が、どれくらい病気にかかったか?」を比べます。
6.統計的にきちんと差を確認する
→ Cox比例ハザードモデルという手法を使い、「年齢・性別・運動量・食事・喫煙・薬などの影響」を取り除いた上で、緑茶の影響だけを評価します。
なぜこの手法が選ばれたの?
・観察研究なので、実際の生活の中で起こる変化をそのまま記録できる
・時間経過による因果関係(飲んでいた→病気が起きたかどうか)を検討できる
・複数の要因(生活習慣など)を調整しながら「緑茶の効果」だけを見ることができる
このようにして、日常生活の中で緑茶をどれだけ飲むかが、病気の予防にどれくらい影響するのかを、信頼できる形で検証しているのが本研究の特徴です。

【補足:各種用語】
BMI
体重と身長から導かれる「体格指数」。
BMIが24を超えると「過体重」、28を超えると「肥満」とされます(中国の基準)。
前向きコホート研究
研究開始時点で対象者の状態を把握し、未来に向かって病気が起こるかどうかを観察していく方法。因果関係の示唆に適しており、医療分野でよく用いられます。
Cox比例ハザードモデル
たとえば「Aさんはお茶を毎日飲んでいた」「Bさんは飲まなかった」としたとき、その後の病気の起こりやすさを“確率の差”で数値化する手法です。
同時に年齢や性別、運動などの影響を調整して、「純粋に緑茶の影響はどうか?」を見ます。
研究結果:たった「1日5g以上の緑茶」で、心臓病や脳卒中のリスクがグッと下がった!
この研究では、緑茶を「どのくらいの量・期間で飲んでいたか」によって人をグループ分けし、心臓病や脳卒中などのリスクが実際にどれだけ減るのかを比較しました。
結果として、
1日あたり5g以上の茶葉を使って緑茶を飲んでいた人たちは、そうでない人と比べて明らかにリスクが低下している
ことが分かりました。
さらに注目すべき点として、
1〜4g/日という少量の緑茶摂取でも、心臓病のリスクが約20%低下する
などの効果が確認されており、“少しずつでも飲むこと”に意味があることが示されました。
つまり、「とにかく5gを超えないと無意味」というわけではなく、まずは日常的に少量から始めてみることでも健康への恩恵が期待できそうです。
数字で見る!緑茶の量によるリスクの違い
※すべて統計的に「有意な差(P<0.05)」が認められた結果です。
| 緑茶の飲用量 | 心臓病(狭心症・心筋梗塞など) | 脳卒中 | 心血管疾患全体 |
| 飲んでいない人 | リスク基準(1.00) | 基準値 | 基準値 |
| 1〜4g/日程度 | 約20%リスク低下 | 約15%低下 | 約10%低下 |
| 5g以上/日 | 約40%リスク低下 | 約30%低下 | 約29%低下 |

性別・年齢別に見ると「より効果が高い人」もいた!
この研究ではさらに、参加者を「男女別」「年齢別」に分けた追加解析も行われました。
その結果、ある特定のグループでは、緑茶の効果がさらに大きくなることが分かっています。
✅ 女性では、心血管疾患のリスクが最大で約50%も低下
→ 男性よりも明確な予防効果が見られました(統計的にも有意)。
✅ 60歳未満の人でもリスク低下が確認
→ 若年〜中年層でも「緑茶を飲む習慣」が将来の病気予防につながる可能性があります。
こうした結果から、「お茶の効果は高齢者だけのものではない」「とくに女性は恩恵を受けやすい可能性がある」といった示唆が得られました。
続けるほどリスクはさらに減少
さらに驚きなのは、緑茶を長く飲み続けていた人ほどリスクが減る傾向が強かったという点です。
✅ 緑茶を「10年以上飲み続けていた人」は、心臓病リスクが最も低かった
✅ 5〜10年の継続でも約26%リスクが低下しており、効果は明確
✅ 逆に、最近になって飲み始めた人では、効果が小さくなる傾向がありました
つまり、緑茶の効果は“今日だけ”“今月だけ”ではなく、“毎日コツコツ”がカギということです。
“長く続けるほど強くなる”──そんな実感のある結果です。

変化がなかった項目
すべての健康指標に変化があったわけではありません。
たとえば:
・緑茶の摂取と糖尿病そのものの数値(血糖コントロール)の改善との直接的な関係は確認されませんでした。
・つまり、緑茶は血糖値を下げる薬のような効果ではなく、「合併症(心臓・脳)の予防」に働くという理解が適切です。
また、今回の研究で扱われたのは“心血管疾患”に限定されたアウトカムであり、がんや全死亡率など、他の病気や死亡リスクとの関係は検討されていません。
「すべての病気を予防できる」と誤解せず、特定の予防効果に絞ったエビデンスであることを理解することが大切です。
背景の差にも注意が必要
今回の研究では、「緑茶をよく飲んでいた人」は、そうでない人と比べて喫煙率が低く、運動量が多い、教育水準が高いといった特徴が見られました。
これらの影響は統計モデルで調整されていますが、「健康意識が高い人ほど緑茶をよく飲む」という傾向が、結果にある程度影響している可能性も否定はできません。
この点をふまえて、「お茶を飲みさえすれば万事OK」とは考えず、生活習慣全体の中で緑茶を活用することが大切です。
この研究は、わたしたちの日常にある「緑茶」という飲み物が、実はとても強力な“未来の健康を守るツール”になりうることを示しています。
しかも、その効果は「高価なサプリ」や「特別な習慣」ではなく、たった5gを、毎日続けるだけで発揮されていました。
そして何より、女性・若年層・5年以上続けている人にとっては、さらに大きな恩恵がある可能性も示されています。
研究の結論
この研究から導き出された結論は、以下の通りです。
✅️2型糖尿病かつ過体重・肥満の人々において、毎日5g以上の緑茶を継続的に摂取することが、心臓病や脳卒中などの心血管疾患のリスクを有意に低下させる可能性がある。
さらに注目すべきは、飲む年数が長いほどその効果がはっきり表れていたことです。
つまり、緑茶の健康効果は“気が向いたときにちょっと飲む”程度ではなく、「毎日コツコツ続ける」ことに意味があると読み取れます。
「5gの緑茶」って、どう飲めばいいの?
5gというのは、具体的には急須で1回〜2回淹れるくらいのごく自然な量です。
✅茶葉5g=だいたい急須1〜2回分
✅️小さじ山盛り2杯 ≒ 5g
✅️ティーバッグなら約2〜3袋分
ただし、ここで重要な注意点があります。
ペットボトル緑茶でも“ゼロ”ではないけど…
市販のペットボトルのお茶(500ml)に使われている茶葉の量は、1本あたり約0.6〜1g程度とされています。
つまり、1日5gの摂取を目指すには、5〜8本も飲む必要があるという計算になります。
さすがにこれを毎日続けるのは現実的ではありませんが、
今回の研究では「1〜4g/日」でも心疾患や脳卒中リスクが有意に低下することがわかっています。
つまり、ペットボトル緑茶を2〜3本飲むだけでも、ある程度の健康効果は見込める可能性があるということです。
ただし、それだけでは“十分な量”には届きにくく、効果を最大限に引き出すためには、
やはり 急須で淹れる・濃いティーバッグ・粉末茶などの工夫を加えることが推奨されます。

毎日5gを無理なく摂取する方法【おすすめ3選】
| 方法 | 1日の目安 | 特徴 |
| 急須で淹れる | 1〜2回 | 香り・味を楽しみたい人向け |
| 水出しティーバッグ | 2〜3袋 | 夏でも手軽。習慣化しやすい |
| 粉末緑茶・抹茶 | 小さじ2〜3杯 | 成分を無駄なく摂れる◎ |
【礼次郎の考察とまとめ】
この研究を読んで、わたしがまず感じたのは「お茶ってやっぱりすごい」という素朴な驚きでした。
毎日飲んでいた緑茶に、こんなにもはっきりとした“守る力”があるなんて、思ってもみなかった人も多いのではないでしょうか。
でも、それは高価な健康食品やハードな運動ではなく、ただ「いつものお茶を、ちょっとだけ意識して飲み続ける」だけで得られるかもしれない効果なんです。
そして今回あらためて思ったのが、「お茶は“薬”だった」という歴史の重みです。
古代や中世の中国・日本では、お茶は非常に高価であり、ときには薬として扱われていた時代もあります。
もしかするとそれは、今回のような健康効果の“経験的な裏づけ”が、当時からすでに感じられていたからなのかもしれません。
現代の科学がそれを数値で証明しはじめた、ということなのではないでしょうか。
私たち日本人と食生活や体質も近いアジア圏の研究という意味でも、この論文はとても示唆に富んでいます。
急須やティーバッグを使って、1日5gを目指す。
その習慣を長く、ゆるやかに続ける。
それが心臓や脳を守る“お守り”になる可能性がある——
一見地味だけど、すごく大切なことだと感じました。
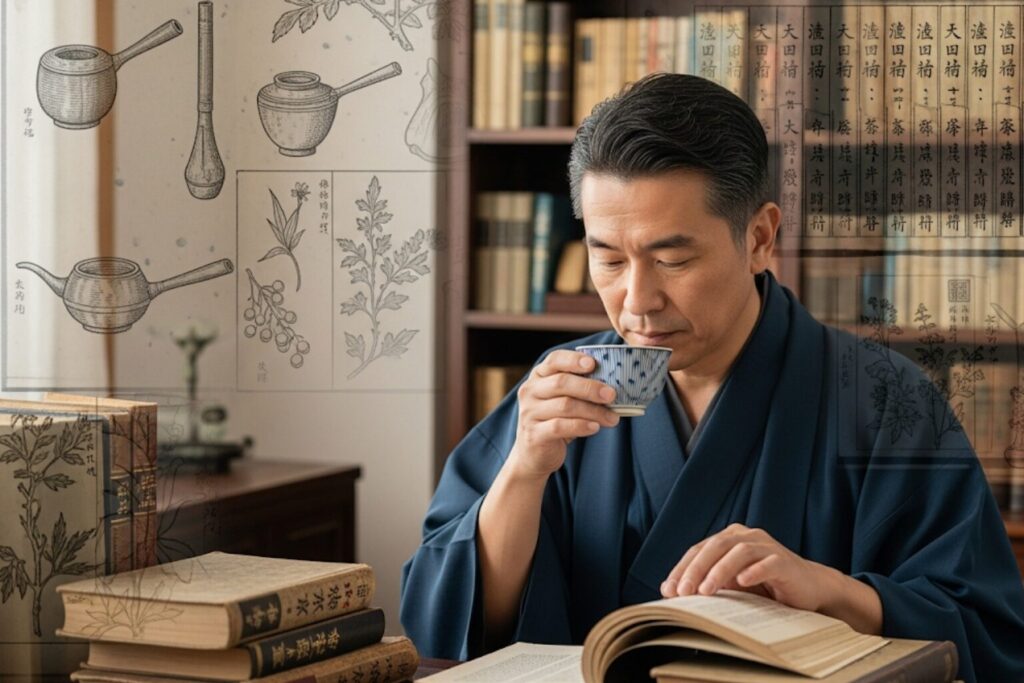
締めのひとこと
“お茶を淹れる”という行為が、未来の自分をいたわる時間になる。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント