
結論「週3回の“体力向上を目的としたトレーニング”で、眠れない夜と不安感が見違えるほど改善されました!」
この記事はこんな方におすすめ
✅眠れなくて毎晩スマホを見ながら時間をつぶしている方
✅ストレスや不安で夜が落ち着かない方
✅運動不足だけど、激しすぎる運動には自信がない方
✅生活の中で「睡眠」と「心の安定」を同時に整えたい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:眠れない夜、どうしたらぐっすり眠れるようになる?
🟡結果:週3回、1時間の“体力向上を目的としたトレーニング”が最も効果的。不眠スコアは約3ポイント改善、不安も9ポイント低下!
🟢教訓:スポーツの種類よりも、継続できる「全身を動かす習慣」が心と体を整えるカギ。
🔵対象:中国の大学院生160人を対象とした研究で、日本人にも応用可能な内容です。

はじめに
皆さん、こんにちは!
夜、布団に入ったのに目が冴えてしまって、気づけばスマホをいじって何時間も経っていた…。そんな経験、ありませんか?
つい先日、学生時代の友人から「最近まったく眠れなくて、気づいたら夜中の3時。朝も疲れが取れないんだよね…」と相談を受けました。
よく話を聞いてみると、寝る前のスマホ習慣と、日中の運動不足が原因かも?という気づきがありました。
本日ご紹介するのは、まさにそんな「眠れない」「不安でいっぱい」と悩む人に向けたヒントとなる研究です。
イギリスの公衆衛生専門誌『BMC Public Health』に掲載されたこの論文では、バドミントンのトレーニングが睡眠と不安にどう効果をもたらすのかを、科学的に検証しています。
今回はこの研究をもとに、日々の生活の中で心と体を整える運動習慣について、わかりやすくお伝えしていきます。
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Effects of different types of badminton training on sleep quality, anxiety, and related baseline physiological markers in graduate students with sleep disorders: a randomized controlled trial”
(異なる種類のバドミントントレーニングが睡眠障害を有する大学院生の睡眠の質、不安、および基礎的生理指標に与える影響:ランダム化比較試験)
BMC Public Health. 2025 Apr 14;25(1):1390.
PMID: 40229718 DOI: 10.1186/s12889-025-22551-4
掲載雑誌:BMC Public Health(BMC パブリック・ヘルス)【イギリス】 2025年2月
研究の目的
この研究の目的は、「睡眠障害や不安に悩む大学院生に対して、どのような運動アプローチが最も効果的なのか?」という疑問に答えることです。
では、なぜバドミントンなのでしょうか?
バドミントンは、持久力を高める有酸素運動の要素と、瞬発力を使う無酸素運動の要素を兼ね備えたユニークなスポーツです。
さらに、動きが比較的コンパクトで屋内でも行えるため、参加のハードルが低いという特徴があります。
研究チームは、大学生にとって実施しやすい運動形態として「バドミントン」をベースに、3種類のトレーニング(基礎スキル・上級スキル・体力重視)を設計。
その中で「運動の目的や内容の違いが心身に与える影響」に注目し、検証を行いました。
今回の研究で使われたのはバドミントンですが、本質的には“どのような運動目的(技術習得か体力向上か)で身体を動かすか”によって効果がどう異なるかを比較するものであり、必ずしもバドミントンそのものの効果を評価した研究ではありません。
研究の対象者と背景
この研究で対象となったのは、中国の曲阜師範大学に在籍する大学院生160名。

全員が、「最近1ヶ月間の睡眠の質が悪い」とされるPSQIスコアが5点以上という条件を満たしていました。
年齢は22〜35歳で、男女比はほぼ半々です。
大学院生というのは、学業や就職、将来への不安など多くのプレッシャーにさらされやすい層です。
この研究では、そんな「高ストレスな日常を送る若者たち」が、どのようにして睡眠や不安を改善できるかに焦点を当てました。
日本でも大学院生や若手社会人は、同じように睡眠障害や不安感を抱えている人が多いはずです。
生活環境や文化が比較的似ているため、日本人にも参考になる内容だといえます。
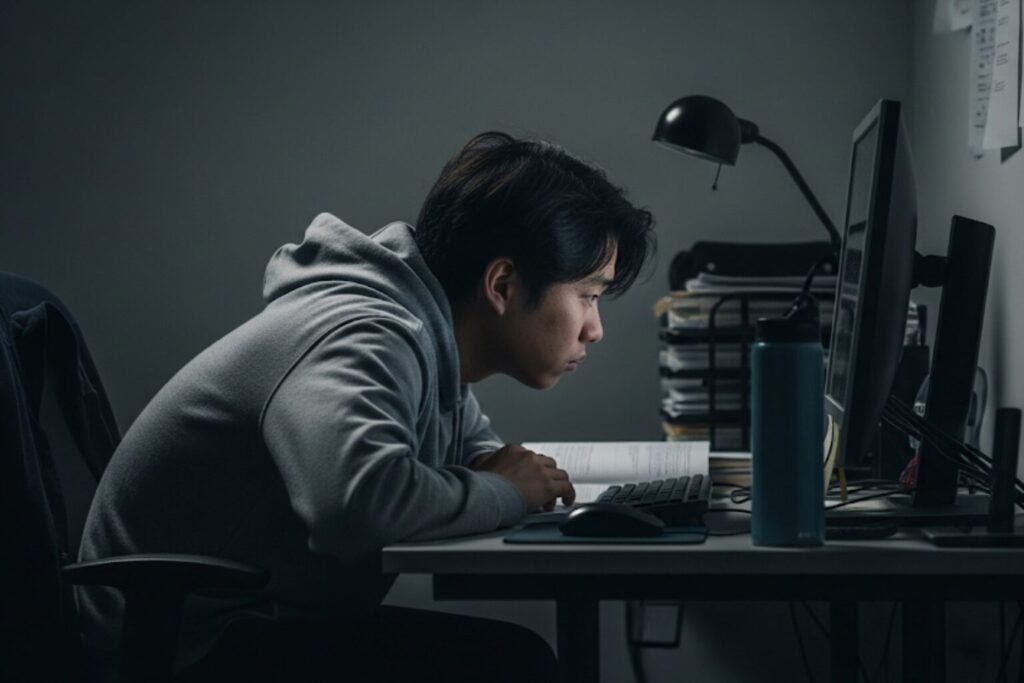
研究の手法と分析の概要
この研究は、ランダム化比較試験(RCT)という方法で行われました。これは医学研究の中でも信頼性が高いとされる手法で、研究対象者を無作為に複数のグループに分け、それぞれ異なる介入を行ったうえで効果を比較します。
●実施期間:2023年3月〜6月(12週間)
●対象:睡眠障害のある大学院生160名
●グループ分け(各40人):
1.BBSTG:基本スキル訓練群
2.BASTG:上級スキル訓練群
3.BSPTG:フィジカル重視訓練群
4.対照群:運動なし、生活習慣指導のみ
●トレーニング内容:週3回、1時間ずつのグループトレーニング
●評価タイミング:開始時・4週目・8週目・12週目の計4回
●評価項目:
・PSQIスコア(睡眠の質)
・SASスコア(不安レベル)
・安静時心拍数・血圧
研究チームは、心拍数やスコアだけでなく、統計的に有意かどうか(p値)や効果の大きさ(Cohen’s d)も分析し、結果の信頼性を高める工夫がされていました。
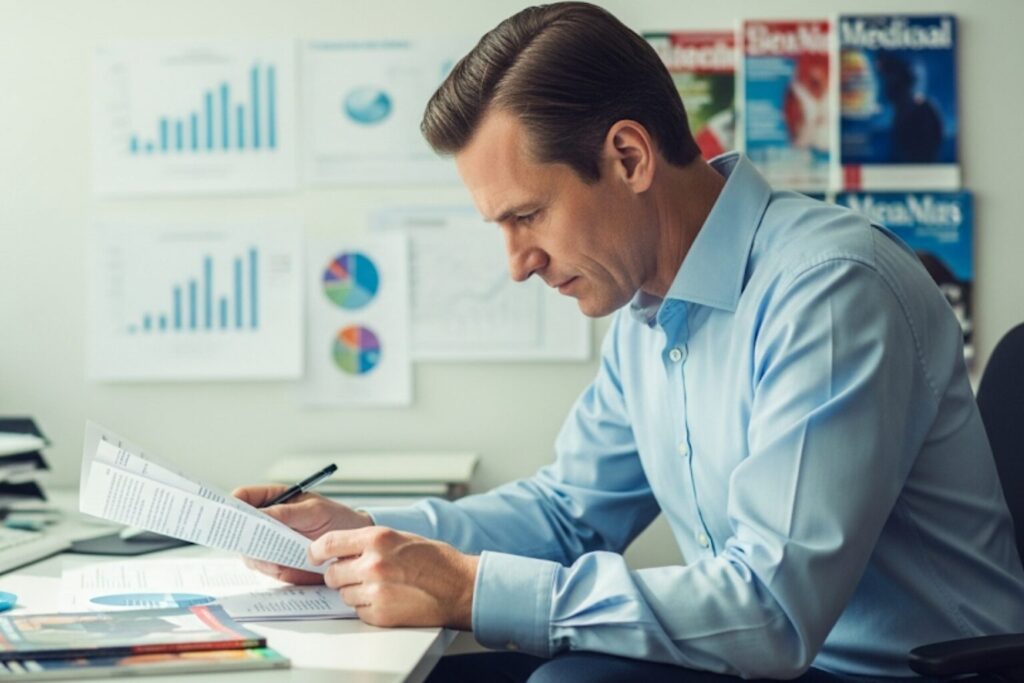
【各トレーニングの内容】
BBSTG(基本スキル訓練:Badminton Basic Skill Training Group)
・サービスやラリーの反復練習
・フォア・バックハンドのフォーム練習
・コート内の動きの練習(フットワーク)
→運動初心者にもやさしい、基礎を学ぶメニューです。
BASTG(上級スキル訓練:Badminton Advanced Skill Training Group)
・スマッシュ・カットなどの高度なショット練習
・実戦形式のプレー(ミニゲーム)
・ダブルスの動きと戦術理解
→実戦を意識した、技術と頭脳を使うトレーニングです。
BSPTG(特化型フィジカルトレーニング:Badminton-Specific Physical Training Group)=体力向上を目的としたトレーニング
・短距離ダッシュやジャンプなどの反復運動
・インターバルトレーニング(HIIT)
・筋力トレーニング(スクワットなど)
→体力や持久力を重点的に鍛える、汗だくメニューです。

【補足:各種用語】
ランダム化比較試験(RCT)
対象者をランダムに割り振り、異なる介入効果を比較する手法。バイアスを避けて、因果関係を明らかにしやすい。
PSQIスコア
0〜21点で評価され、数値が高いほど睡眠の質が悪いとされる。5点超で「睡眠障害」の可能性がある。
SASスコア
不安のレベルを数値化した指標。点数が高いほど不安が強い。
安静時心拍数
運動していないときの心拍数。体力や自律神経の状態を反映する。
研究結果:一番効果が高かったのは「体力向上を目的としたトレーニング」!
12週間にわたり3種類のバドミントントレーニングを比較した結果、体力アップを目的とした「BSPTG(特化型フィジカルトレーニング群)=体力向上を目的としたトレーニング」が、睡眠の質・不安・心拍数すべてにおいて最も顕著な改善を示しました。
これはバドミントンの試合や技術練習ではなく、ジャンプ・ダッシュ・スクワットなど“体力向上を目的とした基礎運動”を中心としたプログラムです。
| 評価項目 | トレーニング前 | トレーニング後 | 変化量 | 統計的有意性 |
| 睡眠の質(PSQI) | 8.6 ± 1.1 | 5.8 ± 0.8 | -2.8ポイント改善 | p < 0.001 |
| 不安(SAS) | 45.4 ± 5.3 | 36.3 ± 4.0 | -9.1ポイント改善 | p < 0.001 |
| 安静時心拍数 | 72.6 ± 6.4 bpm | 66.1 ± 4.8 bpm | -6.5 bpm低下 | p < 0.001 |
| 血圧(収縮期/拡張期) | 118.4/76.3 mmHg | 113.0/73.5 mmHg | 軽度低下 | 有意差なし |
グループ間の比較でわかったこと
・BSPTG(特化型フィジカルトレーニング):すべての指標で最も高い改善効果(睡眠、不安、心拍数)
・BASTG(上級スキル訓練):不安スコア(SAS)に改善効果あり(p < 0.05)が、他指標ではBSPTGに劣る
・BBSTG(基本スキル訓練):全体的に効果はあったが限定的
・対照群:ほぼ変化なし(生活指導のみでは効果がなかった)
【補足:統計的有意性とは?】
「p < 0.05」は、偶然ではなく“本当に効果があった”可能性が高いことを意味します。特にp < 0.001は信頼度が非常に高い結果を示します。
続けるほど効く!? 4週目からすでに変化が
興味深いのは、睡眠や不安の改善が「4週目からすでに現れ始め」、8週・12週目でさらに効果が強くなっていたこと。
つまり、「継続するほど良くなる」傾向が明らかになったのです。

研究の結論
この研究が明らかにした最大のポイントは、「継続的に取り組める体力向上型の運動が、睡眠の質と不安の軽減に明らかな効果をもたらす」ということです。
特に今回のような全身を使った反復的な運動を12週間続けた場合、睡眠スコアや不安スコア、安静時心拍数のすべてにおいて有意な改善が見られました。
これらの効果は、バドミントンでなくても、似たような運動負荷をかけられる他のスポーツやトレーニングでも再現可能と考えられます。
また、重要なのは、この運動が特別な道具や高度な技術を必要としない点。
誰でも取り入れやすい内容であり、週3回・1時間という現実的なスケジュールで行えたことも実践的です。
【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点
この研究結果から私たちが学べることは、「どんな運動をするかが、心と体にとって大きな違いを生む」ということです。
とくにBSPTG(特化型フィジカルトレーニング群)の効果が高かった理由には、論文でも次のようなポイントが挙げられています:
✅全身運動によって自律神経が整いやすくなる
✅運動による適度な疲労感が自然な眠りを引き出す
✅体力アップや継続による達成感や自己効力感の向上
✅セロトニンやメラトニンといった睡眠・気分に関係するホルモンの活性化
これは日本人にも通じるポイントです。
仕事や勉強、スマホや人間関係のストレスにさらされる私たちの生活でも、「意識して体を動かすこと」がどれほど重要かをあらためて気づかされます。
もちろん、いきなりハードな運動を始めるのが難しい方もいると思います。
そういう方は、まずは週に1〜2回でも「汗をかくレベルの全身運動」を意識してみるのがおすすめです。
重要なのは、「何をするか」よりも「どのような目的で、どう継続するか」です。
今回の結果が示すのは、“継続的な全身運動による体力向上”が、自律神経や睡眠ホルモンに良い影響を与え、心身を整えてくれるということ。
実際に行ったのはバドミントンをベースとしたトレーニングでしたが、ダンス・ジョギング・自重トレーニングなど、自分が取り組みやすいスタイルでも十分応用可能です。

まとめ
この研究から見えてきたのは、「眠れない」「不安でつらい」という悩みに対して、“技術より体力”の運動のほうが効果的だった、という少し意外な事実です。
体を動かすことで、ただ疲れるだけでなく、自律神経やホルモンが整い、心まで落ち着くというメカニズム。
睡眠薬やサプリに頼る前に、「まずは動いてみる」ことの価値を感じさせてくれます。
わたし自身も、仕事が忙しくなると寝つきが悪くなるタイプですが、軽くでも体を動かした日はやっぱり違います。
運動ってやっぱりすごい、と実感します。
締めのひとこと
眠れない夜は、まず昼の動き方を見直してみませんか?

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント