
結論「ドライアイの人は、入眠のしにくさや日中の眠気など、睡眠トラブルのリスクが大きく上昇していることがわかりました」
この記事はこんな方におすすめ
✅目の乾燥やゴロゴロ感が慢性化してつらい方
✅「寝ても疲れが取れない」「日中ぼんやりする」と感じる方
✅目薬や温めケアでもドライアイが改善しない方
✅睡眠と目の健康のつながりをきちんと知りたい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:目が乾燥してしょうがない!なにかできることはないの?
🟡結果:ドライアイの人は「眠りが浅い・寝不足・眠気」などのリスクが約2〜5倍に増加
🟢教訓:「眠れない」原因が“目”にあるかもしれない。目のケアと睡眠改善はセットで考えよう
🔵対象:世界13カ国・42万人を対象にした信頼性の高い大規模研究

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
「なんだか目が乾いている」「目がゴロゴロする」
――そんな不快感を感じたこと、ありませんか?
パソコンやスマホを長時間使った日の夕方、目の奥がズーンと重くなる…そんな経験、私もよくあります。
実際、わたしたち医師の仕事もパソコンに向き合うことが多く、診察の経過を電子カルテに記入したり、書類を作成したり、検査結果を確認して指示を出したり…
ほぼ1日中パソコン作業で、目を休める暇もないのが現実です。
気づけば目はパサパサ、しょぼしょぼ。
「目が乾いてるなあ…」と思うと同時に、
なんだか寝つきも悪いし、眠りも浅い気もする。
――これって、もしかして関係あるの?
今回ご紹介するのは、そんな疑問に答えてくれる最新の研究です。
イギリスの眼科専門誌『BMC Ophthalmology』に掲載された2024年の論文で、世界13カ国・42万人以上のデータから、ドライアイと睡眠の質の深いつながりを解き明かしています。
この研究をもとに、「目が乾く」と「眠れない」の意外な関係について、分かりやすく解説していきます!

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Association between sleep quality and dry eye disease: a literature review and meta-analysis”
(睡眠の質とドライアイ疾患との関連性:文献レビューとメタアナリシス)
BMC Ophthalmol. 2024 Apr 5;24(1):152.
PMID: 38581010 DOI: 10.1186/s12886-024-03416-7
掲載雑誌:BMC Ophthalmology【イギリス】 2024年4月
研究の要旨
研究目的
ドライアイ疾患と睡眠の質の関連を明らかにし、予防的介入の科学的根拠を提供すること。
研究方法
2023年4月以前に発表された観察研究21件(被験者計419,218人)を対象にメタアナリシスを実施。平均的な評価指標にはPSQIやESSなどの睡眠尺度を使用。
研究結果
ドライアイ患者は健康な人に比べて主観的な睡眠の質が劣り、入眠時間が長く、睡眠障害(RR = 2.20)、不十分な睡眠(RR = 3.76)、過剰な眠気(RR = 5.53)のリスクが有意に高かった。
結論
ドライアイ患者は睡眠の質が明らかに悪化しており、生活機能や精神的健康への影響が懸念される。
考察
睡眠障害がドライアイを悪化させる可能性もあり、双方向の関連が示唆される。今後は因果関係を明確にする前向き研究が求められる。
研究の目的
ドライアイの人が「なんとなく寝つきが悪い」「ぐっすり眠れない」と感じることは、これまでにも指摘されてきました。
しかし、それをきちんと数字で示した研究は少なく、あっても調査人数が少なかったり、病気の定義があいまいだったりと、信頼性に課題がありました。
そこで今回の研究では、過去に発表された世界中の研究データを一つにまとめて再分析(メタアナリシス)することで、
「ドライアイの人は本当に睡眠の質が悪いのか?」「その影響はどれほど大きいのか?」という疑問に、明確な答えを出すことを目指しました。
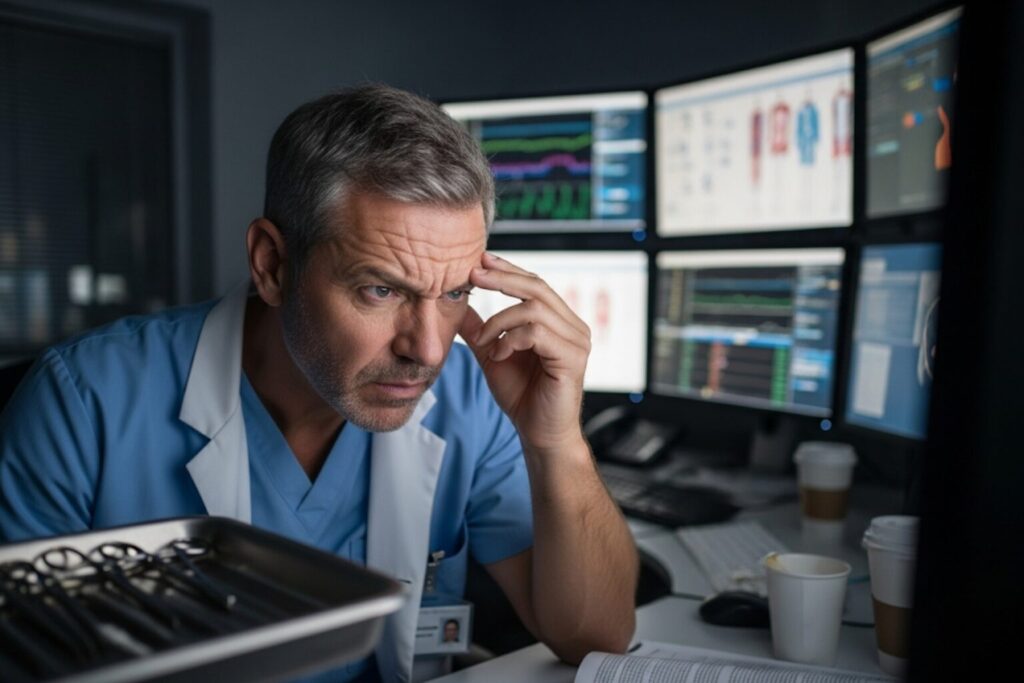
研究の対象者と背景
今回の研究では、世界13カ国・合計21件の観察研究から、計42万人以上のデータが分析に使われました。
参加者は主に以下の2つのグループに分かれていました:
・ドライアイの診断を受けた人(またはシェーグレン症候群の診断がある人)
・目に異常のない健康な人(対照群)
主な対象国
研究に含まれた国は、日本、韓国、中国、アメリカ、オーストラリア、イタリア、トルコ、オランダ、スウェーデン、イギリスなど多岐にわたります。

日本人にも当てはまる?
本研究には日本を含むアジア諸国のデータも多く含まれており、私たち日本人にも当てはまりやすい結果だといえます。
特に中高年女性では、ドライアイの発症が多く、睡眠の質の低下も同時に起こりやすいという背景があります。
研究の手法と分析の概要
この研究では、過去に発表された観察研究21件をまとめて再分析する、
「メタアナリシス」という方法が使われました。
これは、小さな研究を集めて大きなデータにし、より信頼できる結果を導き出すための手法です。
調査の流れ
対象とした文献
2023年4月までに発表された、18歳以上の成人を対象とした観察研究が選ばれました。
対象となった研究の種類は以下の3つです:
・コホート研究
・症例対照研究
・横断研究
評価された項目
分析では、主に以下のような睡眠の状態が比べられました:
・PSQI(ピッツバーグ睡眠の質指標)
→ 睡眠の質を質問形式で数値化するもの
・ESS(エプワース眠気尺度)
→ 日中の眠気がどのくらいあるかを評価
・その他の指標
→ 睡眠障害の有無、不眠の傾向、寝つきまでの時間、睡眠時間の長さなど
分析のしかた
使用した指標
・加重平均差(WMD):
スコアのような数値の差を比べるときに使います
・相対リスク(RR):
ある症状が「どれくらい起きやすいか」を比率で示すときに使います
分析時の工夫
・それぞれの研究結果をまとめて比較し、
「ドライアイの人の睡眠の質はどれくらい悪いのか?」を数値で検討
・統計的に意味のある差かどうか(有意差)も確認
・研究ごとに結果のばらつきがある場合は、その違いも考慮した調整を加えています

【補足:各種用語】
メタアナリシス
たくさんの小さな研究の結果をまとめて分析する方法です。
バラバラな情報を一つに集めることで、「本当にそうなのか?」を確かめやすくなります。
RR(Relative Risk:相対リスク)
たとえば「RR = 2.0」と書かれていれば、
ある症状(今回なら睡眠障害など)が健常者の2倍起きやすいという意味になります。
WMD(Weighted Mean Difference:加重平均差)
平均のスコア差を比べるときに使われる指標。
たとえば、ESSスコア(眠気の強さ)がどのくらい違うかを示すのに使われます。
研究結果
ドライアイの人は、眠りにトラブルを抱えやすい
今回の研究で明らかになったのは、
ドライアイの人は、健康な人よりも睡眠の質が明らかに悪い
ということです。
とくに、「寝つきが悪い」「眠りが浅い」「日中に強い眠気がある」といった問題が多く見られました。
また、自分自身で「睡眠の質が悪い」と感じている人の割合も、ドライアイの人で高い傾向があります。
「寝不足」や「寝すぎ」といった不健康な睡眠パターンも、ドライアイの人で起こりやすいことが示されました。
加えて、不眠症のリスクも1.5倍以上に上昇していることがわかり、
単なる不快感ではなく、医療的な睡眠障害としての影響も含んでいる可能性が示唆されました。
具体的な数値で見るリスクの違い
| 睡眠に関する問題 | 健康な人に比べてのリスク(目安) |
| 睡眠障害がある | 約2.2倍起こりやすい |
| 不眠症のリスク | 約1.5倍高い |
| 5時間未満の寝不足 | 約3.8倍起こりやすい |
| 9時間以上の過剰な睡眠 | 約5.5倍起こりやすい |
| 日中の眠気(ESSスコア) | 平均+1.29ポイント高い |
| ESSスコア11点以上の割合 | ドライアイ群で有意に高い傾向 |
| PSQI総合スコア(睡眠の質全体) | ドライアイ群で明確に悪化 |
| 入眠までの時間(Sleep Latency) | 平均して明らかに長くなっていた |
| 睡眠の質に対する満足度 | 明確に悪化している傾向あり |
特に悪化していた睡眠の側面
睡眠の質は「総合スコア」だけでなく、複数の観点から評価されます。
今回の分析では、ドライアイの人で以下の項目が特に悪化していました:
・主観的な睡眠の質(自分で「よく眠れた」と感じたか)
・PSQI総合スコア(睡眠の質を総合的に評価するスコア)が明らかに高かった
・入眠までの時間(Sleep Latency)が延びていた
・ESSスコア11点以上(日中の重度の眠気を示す)の割合が高かった
・夜間の中途覚醒や寝つきの悪さ(睡眠障害)
・日中の活動への悪影響(眠気や集中力の低下)
さらに、PSQIの構成要素である7項目のうち6項目で有意な悪化が見られ、全体的に幅広い睡眠の質の低下が示されていました。

逆に明確な差が見られなかった項目
一方で、以下の項目ではドライアイの有無による差は明確でなかったとされています:
・睡眠時間そのもの(長さ)
・睡眠効率(ベッドにいた時間のうち、実際に眠れていた割合)
・睡眠薬の使用頻度
これはつまり、ドライアイの人も「寝る時間は確保できている」ものの、眠りの質や満足感に問題があるということです。
長く寝ていても、「疲れがとれていない」「眠りが浅い」と感じてしまう
――そんな実態が浮き彫りになっています。
症状の重さと睡眠の質の関係
また、注目すべきポイントとして、ドライアイの重症度が高いほど、睡眠の質もさらに悪くなる傾向が見られました。
加えて、睡眠の質が悪い人ほどドライアイの発症率が高いという逆方向の関係もあり、
「目が乾くから眠れない」「眠れないから目が乾く」――双方向の悪循環がある可能性
が示されています。

研究の結論
ドライアイと睡眠の質は、深く関係していた
この研究の結論は明確です。
✅️ドライアイと睡眠の質の低下は、相互に強く関連している
ことが示されました。
ドライアイの人は、健常な人に比べて
「寝つきが悪い」
「眠りが浅い」
「日中の眠気が強い」
といった症状を抱えるリスクが高く、
さらに不眠症のような医療的なレベルの睡眠障害にもなりやすいことがわかりました。
また、この関係は一方通行ではなく、
睡眠の質が悪い人もドライアイを発症しやすい
という、双方向の関連性も確認されています。
つまり、
「目が乾くから眠れない」「眠れないから目が乾く」
――そのどちらも起こりうる、ということです。

【礼次郎の考察とまとめ】
なぜドライアイの人は眠りが悪くなるのか?
研究チームは、このような結果になった理由として、いくつかの可能性を挙げています。
・ドライアイによる違和感や痛みが、入眠や深い睡眠を妨げる
・慢性的な炎症や眼の不快感が、交感神経の緊張を高めてしまう
・目の乾燥が強い人ほど、夜間に無意識のうちに目を開けて寝てしまう「睡眠時開瞼(かいけん)」の傾向がある
今回、自己免疫疾患である「シェーグレン症候群」の患者を除外しても、ドライアイ単独で睡眠の質が悪化していたことから、
「ドライアイそのもの」が睡眠に直接的な影響を与える可能性も示唆されています。
また、睡眠が浅くなると「涙の分泌が減る」「目の表面の修復力が落ちる」といった変化が起き、ドライアイが悪化する
という悪循環につながっている可能性も指摘されています。
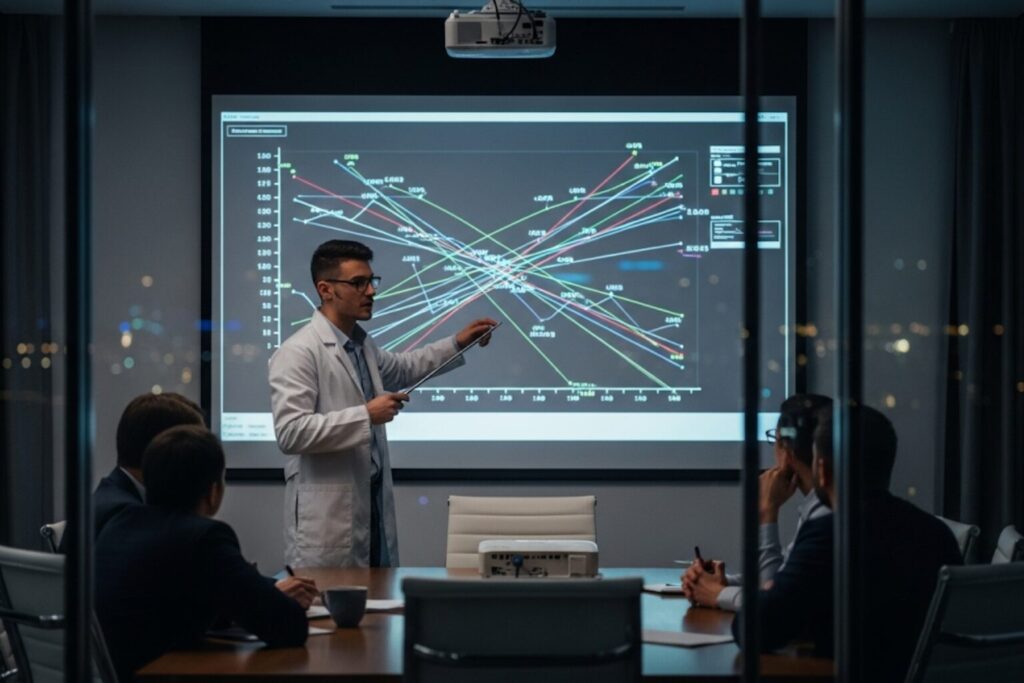
日常生活で私たちができること
この研究はあくまで「関連性」を示すもので、「原因と結果」を断定するものではありません。
でも、目と眠りがつながっているという事実は、私たちの生活に大きなヒントを与えてくれます。
たとえば…
・夕方以降はスマホやパソコンの使用時間を減らす
・お風呂上がりに目元を温めて血流をよくする
・寝る前に目薬やアイマスクで目を乾燥から守る
・睡眠の質が悪いと感じたら「実は目が原因かも?」と疑ってみる
というように、目のケアと睡眠の質の改善は、セットで考えることが大切です。
「眠れない」とき、心だけでなく「目」も一度いたわってあげてください。

締めのひとこと
目と眠り、どちらかが崩れると、もう一方もつらくなる

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント