
結論「甘いジュースを毎日飲んでいると、便秘になるリスクが1.5倍以上になる可能性があります。特に女性や高齢者は要注意です」
この記事はこんな方におすすめ
✅なかなか便秘が改善しない方
✅毎日ジュースや炭酸を飲む習慣がある方
✅40代以上で腸の調子が気になってきた方
✅「水分をとってるのに出ない…」と感じている方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:毎日飲んでる甘いジュースって、便秘に関係あるの?
🟡結果:砂糖入り飲料を1日500ml以上飲む人は、便秘リスクが約1.5倍に。女性や高齢者でさらに顕著!
🟢教訓:毎日のジュース、ちょっと控えるだけで腸の調子が整うかも。
🔵対象:アメリカの20歳以上・約8,000人の調査で明らかになった信頼性の高い結果です。
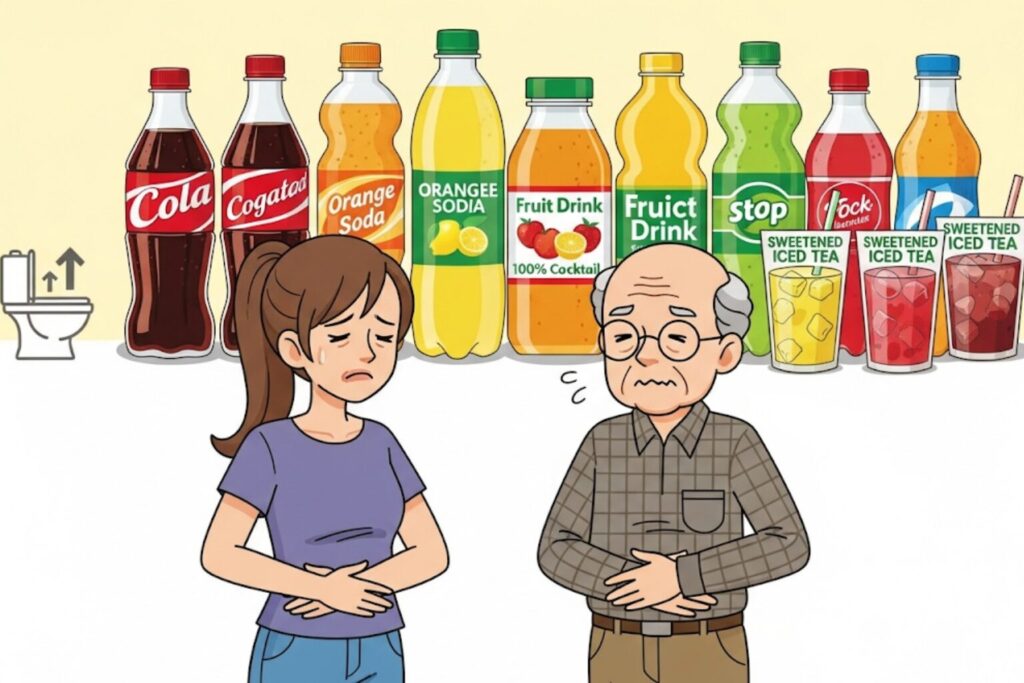
※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
毎日ほんとうに暑いですね。
こんな夏は、キンキンに冷えた甘いジュースが最高においしく感じますよね。
ついコンビニで買ってしまったり、家の冷蔵庫にストックしておいたり……
わたしも、気づけば毎日飲んでしまっていたりします。
「健康にはあまり良くないんだろうな〜」と思いつつ、じゃあ具体的に何に悪いの?と聞かれると、ちゃんと答えられない。
そんな“なんとなく”のまま、習慣になってしまっている人も多いのではないでしょうか。
本日ご紹介するのは、そんな日常の“甘い飲み物”が、もしかして便秘と関係しているのでは?という疑問からスタートして行われた研究です。
アメリカの大規模な国民調査のデータを使って分析され、イギリスの公衆衛生専門誌『BMC Public Health』に掲載された信頼性の高い論文。
今回はその研究をもとに、ジュースと便秘の意外なつながりについて、やさしく解説していきます!
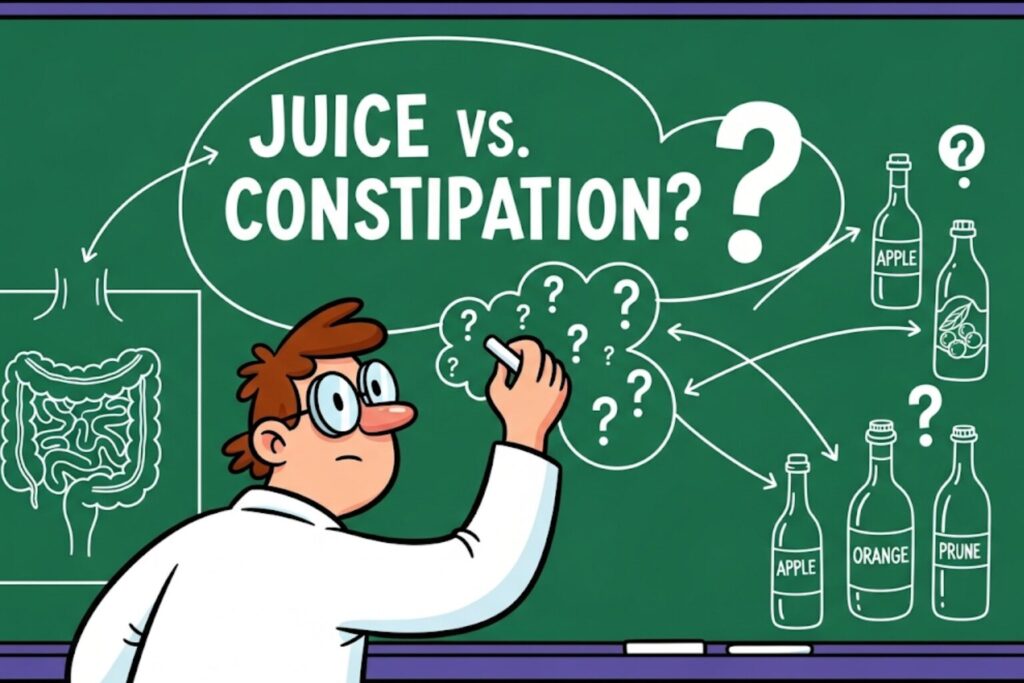
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“The impact of sugar-sweetened beverages consumption on constipation: evidence from NHANES”
(砂糖入り飲料の摂取が便秘に及ぼす影響:NHANESデータによるエビデンス)
BMC Public Health. 2025 Mar 24;25(1):1126.
PMID: 40128706 DOI: 10.1186/s12889-025-22265-7
掲載雑誌:BMC Public Health【イギリス】 2025年3月
研究の要旨
研究目的
砂糖入り飲料(SSBs:Sugar-Sweetened Beverages)の摂取が便秘に与える影響を検証。
研究方法
NHANES(2007〜2010年)の20歳以上7,979人を対象に、SSBsの摂取量(g・kcal)と便秘の関連を多変量ロジスティック回帰で分析。便秘はBristol便形状スケールで定義。
研究結果
SSBs摂取量が多い群で便秘の有病率が有意に高かった。特に20〜39歳、女性、アルコール摂取者で関連が強かった。
結論
SSBs摂取の増加は便秘リスクを上昇させる。
考察
SSBsによる腸の蠕動低下や腸内細菌叢の変化が便秘に関与している可能性。今後は因果関係の解明に向けた縦断研究が必要。
研究の目的
この研究が出発したのは、「甘い飲み物って、便秘にも関係しているのでは?」という素朴な疑問からでした。
便秘はとても身近な体の不調で、多くの人が悩まされていますが、
治療が難しく、日々の生活の質(QOL)を大きく下げる原因にもなります。
一方、砂糖入り飲料(ジュースや炭酸飲料など)は、肥満や糖尿病などのリスク要因として知られていますが、
「便秘」との関係についてはこれまで十分に調べられてきませんでした。
そこでこの研究では、アメリカの大規模な健康調査データを用いて、
砂糖入り飲料(SSBs:Sugar-Sweetened Beverages)をどれだけ飲んでいるかと便秘の頻度との間に、関係があるのかどうかを詳しく調べようとしました。
「本当に関係があるのか? あるとしたらどれくらい? どんな人に影響が大きいのか?」
を、統計的に明らかにしようとしたのが本研究の目的です。

研究の対象者と背景
アメリカの国民健康調査「NHANES」の2007〜2010年のデータをもとに、20歳以上の男女7,979人が対象となりました。

この調査では、食生活・生活習慣・健康状態などを含む多くの情報が収集されています。
対象者の特徴
年齢:20歳以上(平均年齢48.6歳)
男女比:ほぼ半々
調査地域:アメリカ全土
その他:食事内容や便通の自己申告あり
日本人にも当てはまるの?
直接的な対象はアメリカ人ですが、日本でも近年、甘い飲み物の摂取量が増えてきており、特に若年層では類似の傾向が見られます。
人種的な代謝の違いなどを考慮する必要はありますが、食文化が近づきつつある今、日本人にとっても十分参考になる内容といえるでしょう。

研究の手法と分析の概要
研究のデザイン
この研究は、アメリカの国民健康・栄養調査(NHANES)2007〜2010年のデータをもとにした、後ろ向きの横断的観察研究です。
研究者は、過去に収集された食事・生活習慣・排便状況などの情報を分析し、
「甘い飲み物(砂糖入り飲料)」と便秘との関係を明らかにしようとしました。
対象となった人たち
年齢:20歳以上のアメリカ人6,836人
除外:妊娠中の人、炎症性腸疾患など便通に影響する病気を持つ人は除外
条件:24時間食事調査と便通データが正確に報告されている人のみを対象
便秘の判定方法
便秘の判断には、「Bristol便スケール」という7段階の便の形を評価するツールを使用しました。
このうち、スコア1または2(硬くて出にくいコロコロ状の便)とされた人を「便秘」と定義しました。
砂糖入り飲料(SSBs)の分類と評価方法
参加者は、過去24時間に口にした飲み物の種類と量(ml)を報告。
研究では以下のような飲み物を「SSBs(砂糖入り飲料)」として分類しました:
・加糖炭酸飲料(例:コーラ、サイダーなど)
・果汁飲料(100%未満)(例:ネクター系ジュース)
・加糖紅茶・スポーツドリンク・エナジードリンクなど
⚠100%果汁ジュースや人工甘味料入り飲料(ダイエット飲料)は対象外です。
これらのSSBsの摂取量をもとに、参加者を摂取量の少ない順に4グループ(四分位)に分けて分析しました。

※砂糖の「グラム数」について
本研究では、「飲んだ砂糖の重さ(g)」は直接的には測定されていません。
というのも、商品や種類によって砂糖の濃度が異なるため、
より比較しやすい「飲料の量(ml)」を指標として評価しているためです。
分析方法
統計手法:
– 多変量ロジスティック回帰(複数の要因を調整してリスクを評価)
– RCS(Restricted Cubic Spline)法で非線形の傾向も可視化
調整因子(バイアス除去のために統計的に補正された項目):
年齢、性別、BMI、喫煙歴、飲酒、身体活動、食物繊維の摂取量など

【補足:各種用語】
Bristol便スケール
排便の状態を「便の形」で7段階に分類する評価法です。
イギリスのブリストル大学で開発され、世界中で使われています。
この研究では、便秘の定義として、「タイプ1またはタイプ2の便が週に3回未満」という基準が使われました。
| タイプ | 説明 | 意味合い |
| 1 | コロコロとした硬い粒状の便 | 重度の便秘を示す |
| 2 | ソーセージ状だが表面が凸凹で硬い | 便秘傾向 |
| 3〜5 | 理想的な便の形 | 健康的な排便 |
| 6〜7 | 水分が多く、柔らかすぎ/液状 | 下痢傾向 |
このスケールを使うことで、「何回出たか」だけでなく、便の“質”を客観的に把握することができます。
つまり、排便があっても便が硬くて出にくければ、それも便秘と評価されるというわけです。
横断的観察研究
ある特定の時点の情報を集めて、「ある要因(飲み物)とある結果(便秘)」が関係しているかを調べる手法です。
因果関係は証明できませんが、「関連性」を探るのに適しています。
多変量ロジスティック回帰
複数の影響要因(年齢や生活習慣など)を同時に考慮して、便秘のリスクがどのくらい高まるかを数値で示す分析方法です。
RCS(非線形スプライン解析)
飲み物の量が増えるほど「直線的に」リスクが上がるとは限らないため、変化点(しきい値)を含めた滑らかな曲線で関係性を描く手法です。
図として非常にわかりやすい特徴があります。
四分位
参加者を、摂取量が少ない順に4つのグループに分ける方法。
例えば、1日あたりのSSBs摂取量が「0ml〜50ml未満」「50〜200ml」「200〜500ml」「500ml以上」などに分類されるイメージです(※具体的数値は非公開)。
研究結果
甘い飲み物、どれが一番“便秘と関係していた”?
NHANESデータ全体では、便秘の有病率は約6.9%でした。
今回の分析では、
加糖炭酸飲料を毎日500ml以上飲む人は、ほとんど飲まない人に比べて便秘になる可能性が約1.55倍高い
ことがわかりました。
特に影響が大きかったのは、炭酸系の甘い飲み物(例:コーラ、サイダーなど)であり、
加糖紅茶やエナジードリンク、果汁飲料(100%未満のネクター系など)についても同様の傾向が見られましたが、
炭酸飲料が最もリスクを高めていました。
どのくらい飲むとリスクが上がるのか?
参加者は、飲んでいる量に応じて4つのグループ(四分位)に分けられ、各グループごとの便秘の発症率が比較されました。
| 飲料の種類 | 飲んだ量の目安(1日あたり) | 便秘リスクの変化 |
| 加糖炭酸飲料(コーラ・サイダー) | 約500ml以上 | 55%リスク増加(統計的に有意) |
| 果汁飲料(100%未満、ネクター系) | 同上 | 傾向はあるが有意差なし |
| 加糖紅茶・スポーツドリンク・エナジードリンクなど | 同上 | 有意な関連はなし |
特に加糖炭酸飲料では、飲む量が多いほど便秘のリスクが高くなるという“用量反応関係”が確認されました。
SSBsの摂取量と便秘リスクの関係は“直線的”ではなく、
ある量を超えると急にリスクが上がる“しきい値”のようなパターンが見られました(RCS解析による)。
つまり、「ちょっとくらい」では影響が小さくても、「毎日ペットボトル1本以上」のように習慣化すると急激にリスクが高まる可能性があるのです。
さらに、SSBsを多く摂っている人は、水やお茶といった“便通を助ける水分”の摂取が少ない傾向も見られました。
これは、結果として腸内の水分不足を招き、便秘を悪化させている可能性があります。

一方、リスクが高くなかった飲み物も
ネクターなどの果汁飲料や、スポーツドリンク・加糖紅茶などでは、摂取量と便秘リスクにはっきりした関連は確認されませんでした。
ただし、これらの飲料においても、炭酸飲料ほどではないものの、飲む量が多いと便秘との関連が強まる傾向はみられました。
明確なリスクとまでは言えないものの、摂取量には注意が必要かもしれません。
運動と食物繊維の「防御効果」
週に150分以上の運動をしている人では、炭酸飲料の影響はほとんど見られず。
また、食物繊維の摂取量が多い人も、便秘との関連が弱くなる傾向がありました。
これらは、生活習慣によって飲料の影響が大きく変わる可能性を示しています。
高齢者・女性・アルコール摂取により強く関連
さらに、分析を細かく分けた結果、次のようなこともわかりました:
65歳以上の高齢者では、同じ量の甘い炭酸飲料を飲んだ場合でも、便秘リスクは全体よりも高く、約1.78倍に。
女性の方が男性よりも影響を受けやすく、同じ摂取量でもリスクの上昇が目立っていました。
また、アルコールを日常的に飲む人では、便秘リスクが強く現れる傾向がありました。
これは、年齢や性別・アルコールによって腸の動きや代謝の影響が異なるためと考えられます。

影響がなかった飲料や項目も
逆に、100%の果汁ジュースやダイエット系飲料、無糖のお茶や水などには、便秘との有意な関連は見られませんでした。
つまり、「甘い飲み物」でも成分や砂糖の含有量が違えば、腸への影響も変わってくることが示唆されます。
高齢の方や、運動不足の方、食物繊維が少ない食生活をしている方には要注意な結果です。
研究の結論
甘い炭酸飲料の摂取と便秘には有意な関連がある
加糖炭酸飲料を日常的に飲んでいる人は、便秘になるリスクが明らかに高いことがわかりました。
特に、1日500ml以上飲んでいる人では、リスクが約1.55倍に上昇していました。
高齢者や女性では、影響がさらに強まる
年齢や性別によっても影響の度合いは異なり、高齢者や女性ではより強い関連が見られました。
たとえば、65歳以上の人ではリスクが約1.78倍にまで高まっていました。
食物繊維や運動がリスクを和らげる
一方で、十分な食物繊維を摂っていたり、運動習慣のある人では、加糖飲料の影響が目立たない傾向も確認されました。
これは、生活習慣の工夫で腸の健康を守れる可能性を示唆しています。

【礼次郎の考察とまとめ】
なぜ甘い炭酸飲料が便秘のリスクを高めるのか?
著者らは、加糖炭酸飲料に含まれる高濃度の糖分や添加物、カフェイン、炭酸ガスなどが腸の動きを乱す可能性があると述べています。
また、これらの飲料をよく飲む人は、水やお茶といった「便通を促す飲料」の摂取量が減る傾向もあるため、相対的に水分が不足しやすくなるとも指摘されています。
特に高齢者では腸の動きがもともと鈍くなっており、こうした要因の影響を受けやすいと考えられます。
日常生活ではどう気をつければいい?
便秘が気になる方は、まず「毎日ペットボトル1本分以上の甘い飲み物を飲んでいないか」をチェックしてみましょう。
もし習慣的に飲んでいるなら、水やお茶に置き換えることが腸の健康維持につながります。
また、野菜や海藻などの食物繊維を意識的に摂ることや、1日20分でも体を動かす習慣をつけることが便秘予防に効果的です。
特に女性や高齢の方は、飲み物の選び方や生活習慣の見直しが、より大きな違いを生むかもしれません。

締めのひとこと
ペットボトル1本が、あなたの腸に影響しているかもしれません

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント