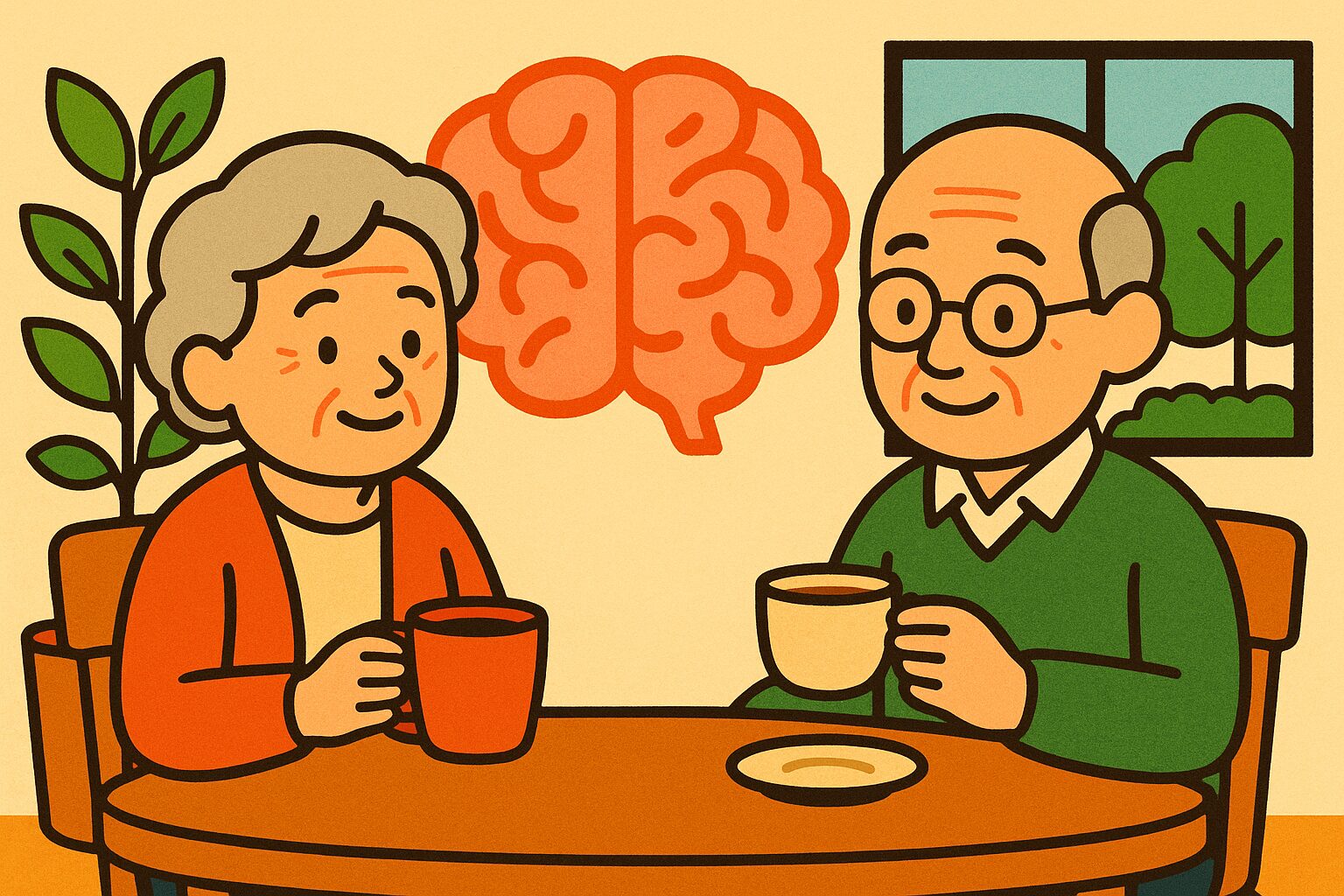
結論「1日3杯以上のコーヒーまたは紅茶を飲む人は、認知症の発症リスクが約58%も低下することがわかりました。」
この記事はこんな方におすすめ
✅親や自分の将来の認知症が心配な方
✅コーヒーまたは紅茶を日常的に飲んでいる方
✅日常の飲み物で健康を守りたい方
✅認知症を予防する習慣を取り入れたい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:コーヒーまたは紅茶って、飲むと脳に良いって本当?
🟡結果:1日3杯以上飲む人は認知症のリスクが約58%も低下
🟢教訓:毎日の習慣が、将来の認知症予防につながるかも
🔵対象:台湾の60歳以上の高齢者が対象 日本人にも応用可能な知見

はじめに
皆さん、こんにちは!
最近、家族のちょっとした物忘れが気になることがあって、「何か日常の中でできることはないかな」と思うようになりました。
ふとしたきっかけで、普段の飲み物が脳の健康と関係しているかもしれない――そんな研究に出会ったんです。
今回ご紹介するのは、台湾の医学雑誌「Journal of the Formosan Medical Association」に掲載された研究。
台湾の研究チームが、コーヒーまたは紅茶の摂取と認知症リスクの関係を調べたものです。
「毎日の習慣」が将来の健康にどうつながるのか?
今回はその研究をもとに、飲み物と脳の健康の関係について、やさしく解説していきます。
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Coffee and tea consumption and dementia risk: The role of sex and vascular comorbidities”
(コーヒーと紅茶の摂取と認知症リスク:性別および血管性併存疾患の役割)
J Formos Med Assoc. 2025 Feb;124(2):178-185.
PMID: 38714417 DOI: 10.1016/j.jfma.2024.04.018
掲載雑誌:Journal of the Formosan Medical Association(中華民国医師会雑誌)【台湾】 2025年1月より
研究の目的
この研究は、「コーヒーまたは紅茶を飲むことが、認知症の発症リスクを下げるのか?」という疑問を明らかにするために行われました。
その背景には、以前からカフェインが脳の働きに良い影響を与えるかもしれないという研究結果がある一方で、結果がまちまちだったことがあります。
特に、これまでの研究は「アルツハイマー型認知症」に偏っており、血管性認知症(VaD)や、性別や持病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)による違いまで詳しく見たものは少なかったのです。
そこで本研究では、コーヒーまたは紅茶の摂取が認知症リスクにどう影響するのか、そしてその影響が人によって違うのかという点を、より細かく検証することを目的としました。
研究の対象者と背景
この研究に参加したのは、台湾の3つの病院に通う60歳以上の高齢者848人です。
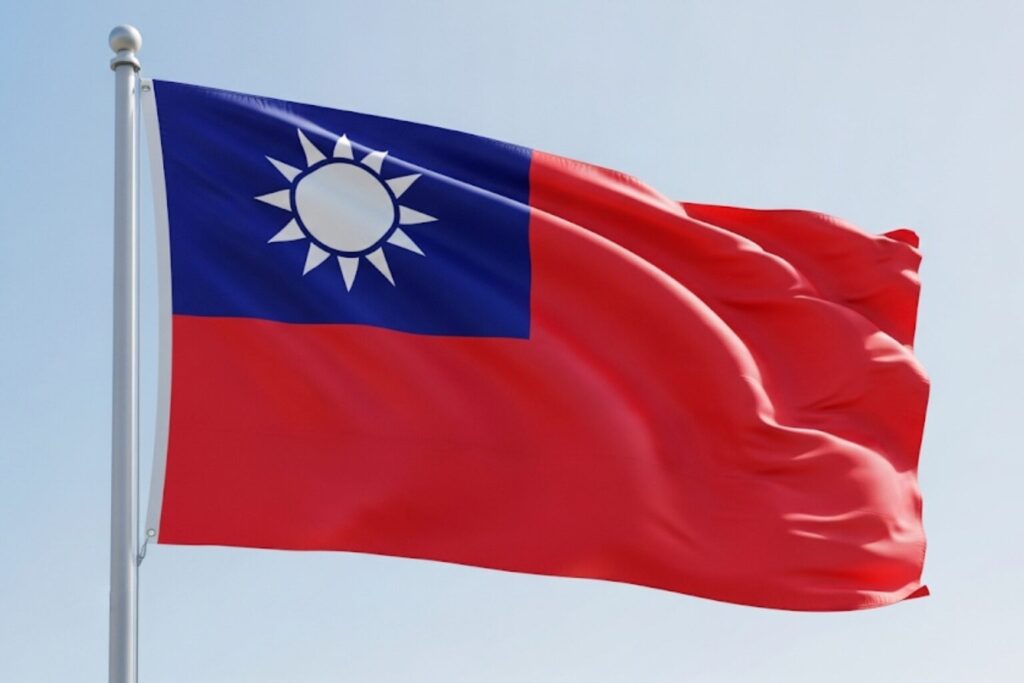
内訳は以下の通りです:
・アルツハイマー型認知症(以下:ADと表記):278人
・血管性認知症(以下:VaDと表記):102人
・健康な対照群(認知症なし):468人
参加者は2007年から2010年の間に募集され、コーヒーまたは紅茶をどれくらい飲んでいるか、生活習慣や持病(高血圧、糖尿病、脂質異常症)などの情報も詳しく集められました。
また、認知症と診断された人については、脳の画像検査(MRIなど)で診断の正確性を確認しています。血管性認知症の人は「脳の小さな血管障害(小血管病)」に限定するなど、非常に厳密に分類されていました。
本研究は台湾の高齢者を対象にしていますが、日本と同様にお茶を飲む文化があること、アジア系の体質や生活習慣が似ていることから、日本人にとっても参考になる内容です。
ただし、日本での食生活や運動習慣の違いもあるため、完全に同じとは言い切れない点に注意が必要です。とはいえ、「日常的な飲み物が脳に良い可能性がある」という視点は、私たちにとっても大きなヒントになりそうですね。

研究の手法と分析の概要
この研究は、「ケースコントロール研究」という手法を用いた観察研究です。
つまり、すでに認知症と診断された人たちと、診断されていない人たちを比較して、生活習慣の違い(今回は飲み物の習慣)に注目する方法です。
調査の流れ
・調査期間:2007年〜2010年
・対象者数:認知症患者380人(うちAD 278人、VaD 102人)、健常な高齢者 468人
・評価方法:
- 認知症の診断は、医師による問診と脳の画像検査(MRI・CT)を含めて厳密に実施
- 飲料の摂取量は、面接形式のアンケートで「コーヒーまたは紅茶を1日何杯飲むか」を記録
- 飲み方(砂糖の有無など)についての情報は含まれていません
分析方法
収集したデータは、多数の影響因子(年齢、性別、教育歴、体型、生活習慣、病歴、遺伝的リスクなど)を考慮して、「本当に飲み物の習慣が認知症リスクに関係しているのか?」を検討するために、多変量ロジスティック回帰分析という方法で解析されました。
この手法によって、「たまたまではない関連性」を見極めることができ、結果の信頼性が高まっています。
【補足:各種用語】
・ケースコントロール研究とは?
過去の習慣(たとえば飲み物の量)を思い出してもらい、病気の有無と比べて調べる方法です。直接原因を証明することはできませんが、「関係がありそうか」を探るのに適した方法です。
・ロジスティック回帰とは?
複数の要因(年齢・性別・病歴など)を同時に考慮しながら、「飲み物の習慣」と「認知症リスク」の関連性を数値で表す分析方法です。
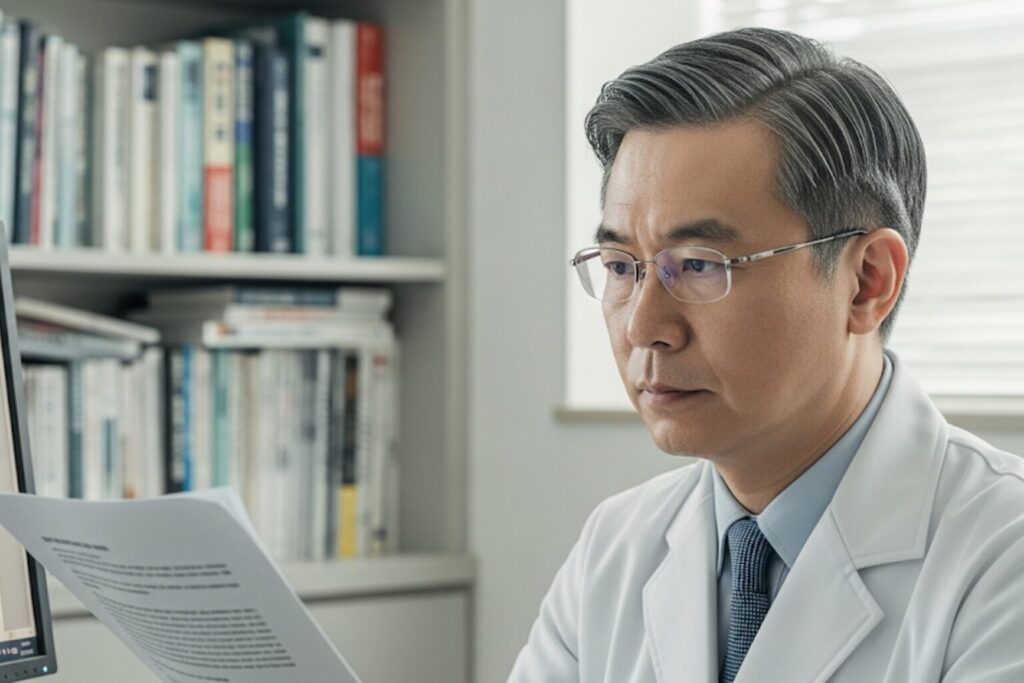
研究結果:コーヒー・紅茶で認知症は防げる?「量」と「種類」による違いとは
この研究では、コーヒーまたは紅茶を飲んでいる人は、飲まない人に比べて認知症のリスクが低い傾向にありました。
とくに、「どれくらい飲むか」や「どんな人が飲むか」によって、その効果には違いがあることがわかっています。
飲む「量」と認知症リスクの関係
| 1日あたりの杯数 | アルツハイマー型(AD) | 血管性認知症(VaD) | 全体の認知症 | 有意差の有無 |
| <1杯(基準) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | – |
| 1–2杯 | 0.82 | 0.49 | 0.74 | ❌(有意差なし) |
| 3杯以上 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ✅(有意差あり) |
→ 1日3杯以上の摂取で、すべてのタイプの認知症リスクがおよそ58%低下。
これは「統計的にも意味がある」とされる信頼性の高い結果です。
1〜2杯では効果がある可能性もありますが、明確な差とは言えず、“たまたま”の範囲を超えていないと考えられます。
※「有意差あり=統計的に明確な差であり、たまたまではない」

飲む「種類」と認知症リスクの関係
| 飲み方 | ADリスク | VaDリスク | 全体リスク | 有意差の有無 |
| 飲まない(基準) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | – |
| コーヒーまたは紅茶のみ | 0.66 | 0.44 | 0.60 | 一部有意差あり(VaD・全体) |
| 両方を飲んでいる人 | 0.54 | 0.20 | 0.44 | 一部有意差あり(VaD・全体) |
→ 「両方を飲む人」では血管性認知症において、約80%のリスク減少が見られました。

☕コーヒーだけ・🍵紅茶だけの人は?
| 飲み方と量 | ADリスク | 有意差の有無 | コメント |
| コーヒー 1–2杯 | 0.45 | ✅(有意差あり) | 少量でもリスク低下が確認された |
| コーヒー ≥3杯 | NA | NA | データ数が少なく不明確 |
| 紅茶 1–2杯 | 1.23 | ❌(有意差なし) | 効果は見られず |
| 紅茶 ≥3杯 | 0.52 | ❌(傾向のみ) | リスクは下がりそうだが確定せず |
→コーヒーは少量(1〜2杯)でもリスク低下が確認されました。
紅茶は3杯以上で効果が出そうな気配はあるものの、はっきりとは言えません。
数字に差があっても、統計的に意味がなければ“偶然かもしれない”と考えられるため、誤解に注意が必要です。

性別・持病による違い(サブグループ解析)
研究では、性別や血管性の持病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)ごとに効果の違いも分析されました。
✅女性では、飲まない女性に比べてリスク低下の効果がより強く出ていました。
✅高血圧のある人でも、有意なリスク低下が確認されました。
✅糖尿病のある人では、「コーヒーまたは紅茶のどちらかを飲むだけ」でもVaDリスクが大きく下がっていました(aOR=0.23)。
✅一方で、脂質異常症がある場合には効果が弱まる可能性があるという結果もありました。
▶ つまり、「誰にでも同じ効果があるわけではない」ことが示されており、個人の体質や持病を考慮した飲み方が今後の課題とも言えます。

研究の結論
✅確実にリスクが下がると確認されたのは、「3杯以上」かつ「両方を飲む」パターン
✅コーヒーだけでも一定の効果があるが、紅茶だけでは不明確
この研究では、コーヒーまたは紅茶を1日3杯以上飲むことで、アルツハイマー型認知症(AD)や血管性認知症(VaD)のリスクが有意に低下することが明らかになりました。
また、その効果は誰にでも同じというわけではなく、性別や持病の有無によって変化することも分かりました。
具体的には、女性や高血圧のある人では予防効果がより強く、糖尿病のある人では「コーヒーまたは紅茶のどちらか一方」でもVaDリスクが明確に下がる傾向が見られました。
一方、脂質異常症のある人では、その効果が弱まる可能性があることも示唆されています。
つまり、「どれくらい飲むか」だけでなく、「誰が飲むか」によっても効果は変わる可能性があり、今後は個別の体質や健康状態に応じたアプローチが求められるといえます。
【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点
この研究は、「コーヒーか紅茶か」に明確な優劣をつけることを目的としていませんが、個別のデータを細かく見ると、コーヒーを単独で飲んでいる人の方が、よりはっきりとしたリスク低下が見られたことが印象的でした。
とくに、1日1〜2杯程度でも効果が確認されていた点は、コーヒーを普段から飲む方にとって心強い発見ではないでしょうか。
一方で、紅茶に関しては、量を増やしても統計的には「効果があるとは言い切れない」状況です。
ただし、紅茶にはポリフェノールやカフェイン以外の成分も豊富で、別の健康効果をもたらす可能性もあるため、今回の結果だけで紅茶が劣っていると断定することは適切ではないと考えています。
また、「コーヒーと紅茶の両方を飲んでいる人」に最も良い結果が出ていたことから、どちらかにこだわらず、日によって飲み分けたり、両方を適度に楽しむという柔軟な姿勢が、実はもっとも実用的なのかもしれません。
そして忘れてはならないのが、この研究は台湾の方々を対象に行われたものだという点です。
アジア系の生活環境や文化が比較的近いという意味では、日本人にとっても示唆に富む研究であることは間違いありません。
今後は、「健康に良い飲み物」も人それぞれの条件に合わせて選ぶ時代になっていくかもしれません。
自分の体質や持病に応じた飲み方を意識することが、いちばん賢い「おいしい習慣」の育て方だと思います。

まとめ
コーヒーや紅茶は、リラックスタイムのお供として私たちの生活に溶け込んでいます。
今回の研究は、そんな飲み物が、認知症のリスクを下げる可能性があるという、とても身近で役立つ知見を示してくれました。
特に、1日3杯以上の摂取で効果が明確に出ること、そして性別や持病によって効果の出方が異なるという点は、これからの健康習慣を考えるうえで重要なポイントです。
自分の体調や生活スタイルに合わせて、コーヒーや紅茶を少し意識して取り入れるだけで、将来の自分にやさしい選択になるかもしれません。
「好きだから飲む」に、ほんの少し「脳の健康を気にして飲む」を加える──
そんなちょっとした意識が、今日から始められる予防への一歩になるはずです。
締めのひとこと
未来の記憶力は、今日の“選び方”で変わるかもしれません。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。


コメント