
結論「『コーヒーをよく飲む人は、顔が老けにくい』――42万人の遺伝データから、そんな驚きの関係が見えてきました」
この記事はこんな方におすすめ
✅スキンケアに力を入れているが「老け顔」が気になる
✅コーヒーは身体に良いのか気になっていた
✅老化の原因が生活習慣で変わるなら知りたい
✅医学的に信頼できる情報で肌ケアをしたい
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:毎日の飲み物が「顔の老化」に関係あるって本当?
🟡結果:コーヒーを多く飲む体質の人は、顔の老化リスクが約15%低いとわかりました(42万人分の遺伝データから判明)。
🟢教訓:「老け顔対策=スキンケア」だけじゃない。コーヒーの抗酸化作用が、内側から肌に働く可能性も。
🔵対象:ヨーロッパ系(白人)42万人が対象。日本人にも参考になる部分あり。

はじめに
皆さん、こんにちは!
年齢を重ねるごとに、「なんだか最近、顔が疲れて見える」「写真に写った自分が思っていたより老けて見える」…そんなふうに感じたことはありませんか?
わたし自身、40代に入ってからというもの、朝鏡を見たときの「たるみ」や「くすみ」が気になりはじめ、スキンケアや食生活を見直すようになりました。
でも正直、何が正しいのか迷うことも多いですよね。
本日ご紹介するのは、「毎日の飲み物が、顔の老化にどう関係しているのか?」を科学的に明らかにした研究です。
この論文は、イギリスの美容皮膚科学専門誌『Journal of Cosmetic Dermatology』に掲載されたもので、信頼性の高い遺伝データをもとに、コーヒーや紅茶、アルコールなどの飲み物と顔の老化との関係を詳しく分析しています。
今回はその研究をもとに、「肌年齢を若く保つために、どんな飲み物が良いのか?」をわかりやすく解説していきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Beverage consumption and facial skin aging: Evidence from Mendelian randomization analysis”
(飲料摂取と顔の皮膚老化:メンデルランダム化解析による証拠)
J Cosmet Dermatol. 2024 May;23(5):1800-1807.
PMID: 38178620 DOI: 10.1111/jocd.16153
掲載雑誌:Journal of Cosmetic Dermatology(美容皮膚科学ジャーナル)【イギリス】 2024年5月
研究の目的
「毎日の飲み物が、顔の老化にどれくらい影響するのか?」――そんな素朴な疑問を、科学的にしっかり確かめようとしたのが今回の研究です。
これまでにも「コーヒーをよく飲む人は若々しい」「お酒をよく飲む人は老け顔になりやすい」といった観察結果はありました。
でも、それが本当に“その飲み物が原因”なのか、あるいは“たまたま他の要因と重なってそう見えただけ”なのかは、はっきりしていませんでした。
そこでこの研究では、「飲み物の種類と顔の老化」に因果関係があるのかを調べるために、遺伝情報を手がかりに使う特殊な統計手法(メンデルランダム化解析)を用いました。
この手法を使うと、生活習慣と健康リスクの“本当の因果関係”に近づけると考えられています。
今回はコーヒー、紅茶、アルコール、砂糖入り飲料(SSB)の4種類について、どれが「顔の老化を早めるか、あるいは防ぐか」を調べることが目的でした。

研究の対象者と背景
今回の研究で使われたのは、イギリスの「UKバイオバンク」という大規模な健康データベースに登録されている、約42万人以上の男女のデータです。

このデータベースには、参加者の生活習慣や食事、見た目年齢に関する自己評価、そして遺伝子情報まで幅広く記録されています。
特に重要なのは、今回対象となった人々がすべて「ヨーロッパ系(白人)」の人種的背景を持っているという点です。
つまり、アジア系やアフリカ系など、肌の特徴が異なる人種は含まれていません。
そのため、この研究結果を日本人にそのまま当てはめることには限界があるものの、たとえば「コーヒーに含まれる抗酸化物質が肌の老化を防ぐ可能性」など、人種に関係なく作用するメカニズムもあるため、一定の参考にはなり得ると考えられます。

研究の手法と分析の概要
この研究では、「コーヒーなどの飲み物が、顔の老化にどんな影響を与えるのか?」を、信頼性の高い方法で調べるために、「メンデルランダム化解析(MR)」という統計手法が使われました。
これは、生まれ持った体質(遺伝情報)を手がかりに、特定の生活習慣が肌の老化などに“本当に影響しているのか”を調べる方法です。
実際の手順は以下の通りです:
1.飲み物の摂取量を自己申告で記録
UKバイオバンクに登録された約42万人の参加者に、「コーヒー、紅茶、アルコールをどのくらい飲むか?」をアンケート形式で回答してもらいました。
2.全員のDNA情報も活用
参加者の遺伝子データを分析し、「コーヒーをたくさん飲む人に共通して多く見られる遺伝的特徴(SNP)」を統計的に抽出。
3.その遺伝マーカーが、顔の老化とどう関係しているかを調査
顔の老化は「自分の顔が年齢に比べて若く見えるか、老けて見えるか」という自己評価データで数値化されています。
4.複数の統計手法で因果関係を分析
主に「IVW法(インバース・バリアンス加重法)」を使い、補助的に「MR-Egger法」や「Weighted median法」でも検証。
また、コーヒーに関しては、別の独立したデータセットを使って再現性の確認も行いました。
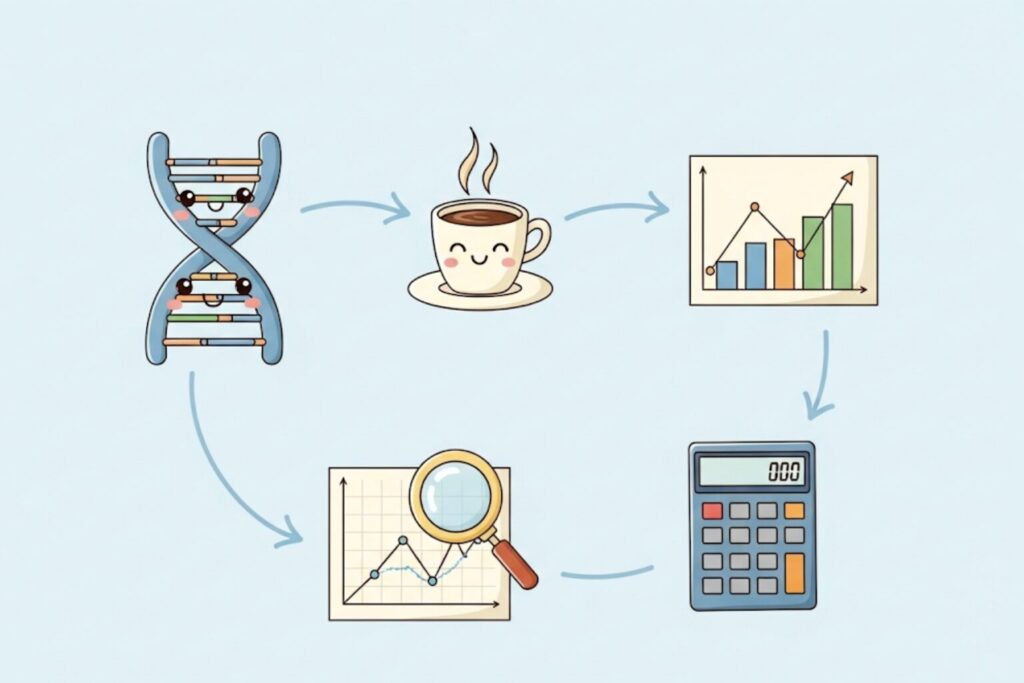
「お酒を飲むと顔が赤くなる体質」ってありますよね?
それと同じように、「カフェインを代謝しやすい体質」の人はコーヒーを飲んでも平気なので、自然とたくさん飲みやすい。
今回の研究では、そうした“飲みやすい体質(=遺伝)”と“肌の老化しにくさ”に関係があるかどうかを分析しているわけです。
このように、ただの観察データではなく、「体質に基づく傾向」を活用して、因果関係をできるだけ正確に見極めた研究であることが、この研究の大きな特長です。
【補足説明:使われた統計手法について】
IVW法(インバース・バリアンス加重法)
信頼度の高い遺伝子データに重みをつけて、全体の平均的な効果を出す基本的な方法。
→ 最も信頼されている標準的な手法で、精度が高いのが特徴です。
MR-Egger法
「本当に飲み物の影響だけか?」という疑問に答えるため、他の影響(バイアス)が混ざっていても修正しながら因果関係を分析できる方法です。
→ “たまたまの結果”を疑って確認するための手法です。
Weighted median法(加重中央値法)
一部のデータが不正確でも、正しい情報が半分以上あれば、信頼できる結果を出せる方法です。
→ 複数の手法を使うことで、研究結果のブレを減らし、信頼性を補強しています。
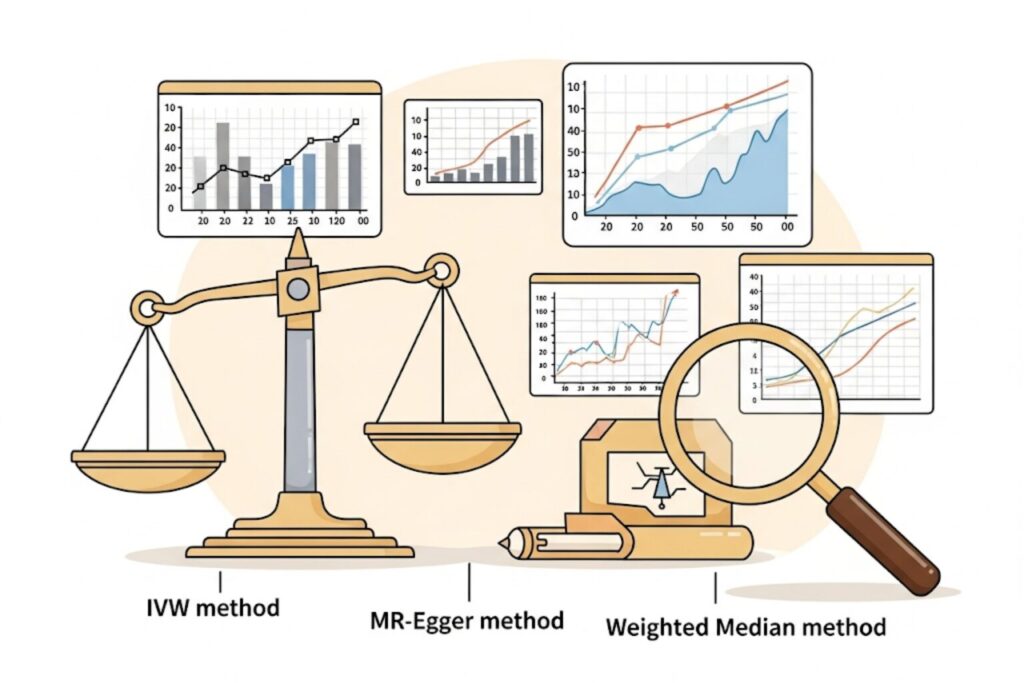
研究結果:コーヒーは“顔の老化”を防ぐ・・かもしれない!?
今回の研究で最も注目されたのは、「コーヒーを多く飲む遺伝体質を持つ人は、老けて見えにくい傾向がある」という結果でした。
この関係は、主要な統計手法(IVW法)だけでなく、補助的な分析(MR-Egger法・加重中央値法)でも一貫して確認されており、さらに別のデータセットでも再現性のある結果が得られています。
加えて、「本当にコーヒーの影響なのか?」という視点から、他の要因が混ざっていないかをチェックする追加の検証(感度分析)も行われ、コーヒー以外の影響はほとんどないと確認されました。
また、まったく別の人たちのデータを使った再確認でも、同じように「老けにくい傾向」が出ており、今回の結果が“たまたま”ではないことが裏づけられています。
一方で、紅茶・アルコール・砂糖入り飲料(SSB)には、見た目年齢に明確な影響は見られませんでした。
つまり、「肌の老化に特に関係していたのはコーヒーだけ」だったのです。
| 飲み物の種類 | 老化への影響(自己申告の見た目年齢) | 統計的有意性 | コメント |
| コーヒー | 老けにくい(若く見える傾向) | あり(有意) | 肌の老化を防ぐ可能性 |
| 紅茶 | 変化なし | なし | 老化との関係は不明確 |
| アルコール | 変化なし(やや悪化傾向ありも明確でない) | なし | 顔の老化との関連は不確定 |
| 砂糖入り飲料(SSB) | 変化なし | なし | 予想された悪影響は見られず |
「顔の老化」の評価は“自己申告”であることに注意
なお、顔の老化の評価はすべて参加者本人による主観的な自己申告に基づいています。
「シワの深さ」や「肌のハリ」といった医師による診断ではなく、以下のような質問への回答でした:
「あなたの顔は年齢に比べてどう見えますか?」
→選択肢:①若く見える
②年相応
③老けて見える
そのため、主観のバラつきや文化的価値観によるズレ(たとえば「老け顔」の定義の違い)が結果に影響している可能性もあります。
研究チームもこの点を「今後は皮膚診断や画像解析による客観的評価が必要」として、限界として明記しています。
また、論文内には「遺伝的に高いコーヒー摂取傾向」 と述べられていますが、具体的なコーヒーの摂取量(例:1日〇杯)は言及されていません。

研究の結論
この研究の結論は、次のようにまとめられます:
✅「コーヒーを多く飲む体質の人」は、“見た目が若い”と感じている傾向がある
✅紅茶、アルコール、砂糖入り飲料には、顔の老化に関する明確な影響は認められなかった
✅分析は複数の手法と別データセットで確認されており、コーヒー摂取と見た目年齢の因果的な関連が示唆された
とはいえ、見た目年齢の評価が主観的であること、対象がすべて白人であることから、結果の適用範囲には注意が必要です。
それでも、「コーヒーが見た目の若さに良い影響を与える可能性がある」という興味深いヒントが、今回の研究から明らかになったのは確かです。

【筆者の考察】日本人のわれわれがこの論文から学び活かせる教訓や注意点
この研究から得られる最大のヒントは、「毎日飲むコーヒーが、思っている以上に“肌の若々しさ”に関係しているかもしれない」ということです。
特にコーヒーには、抗酸化作用をもつポリフェノール類(クロロゲン酸など)が豊富に含まれており、活性酸素のダメージから肌を守る働きがあることが、これまでの基礎研究でも報告されています。
今回の研究では、“生まれつきコーヒーをたくさん飲みやすい体質”の人に、実際に「老けて見えにくい傾向」があったという結果が出たことで、「コーヒーの抗老化作用」は、理論だけでなく実際の人間の見た目にも影響している可能性があるという裏づけが得られたわけです。
ただし、研究対象はすべて白人(ヨーロッパ系)の人々であり、肌質や紫外線に対する感受性が異なるアジア人(日本人)にも同じ効果があるとは言い切れません。
また、顔の老化評価が“自己申告”である点も含めて、あくまで「参考情報」として受け取るのが賢明です。
とはいえ、「スキンケアを頑張るだけではなかなか変わらない…」と感じている方にとって、コーヒーのような身近な飲み物を、上手に生活に取り入れることの価値を、再確認できるきっかけになるのではないでしょうか。

まとめ
今回の研究は、「コーヒーを飲む習慣」と「顔の見た目年齢」との関係を、遺伝レベルから因果的に探った本格的な研究です。
結果として、
✅コーヒーをよく飲む体質の人は、若く見える傾向がある
✅紅茶やアルコール、砂糖入り飲料にはそのような関係は見られなかった
ということが明らかになりました。
この発見は、「肌の老化=スキンケアや紫外線対策だけではない」という新たな視点を与えてくれます。
コーヒーが持つ“内側からの力”が、実際の見た目にまで影響しているかもしれない――そう考えると、毎朝の一杯にも少しだけ意味が深まるかもしれません。
毎日続く小さな習慣が、10年後の顔を変える。
そんな可能性を感じながら、今日も一杯、楽しんでみてはいかがでしょうか。
締めのひとこと
「肌にいいもの」は、案外カップの中にあるかもしれません。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント