
結論「体を動かす、頭を働かせる、人と話す――この“3つの刺激”がそろった生活こそが、脳の若さを保つカギだとわかりました」
この記事はこんな方におすすめ
✅最近もの忘れが増えてきて「これって老化?」と不安な方
✅健康的な生活を送っているけれど、それが脳に良いのか知りたい方
✅認知症予防に「何をすればいいか」具体的に知りたい方
✅両親や祖父母の脳の健康を守りたいと思っている方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:年を取っても“脳を若く”保つ方法ってあるの?
🟡結果:よく歩き、趣味や読書で頭を使い、人と交流する習慣がある人は、脳の年齢が実年齢より平均5歳も若い傾向がありました
🟢教訓:「体・頭・心」に刺激を与える生活が、脳と認知機能の老化をゆるやかにするかもしれません
🔵対象:ドイツの高齢者211人を対象にした研究。日本人にも十分応用できる内容です

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
「あれ、何を取りにきたんだっけ?」と、立ち上がった瞬間に忘れてしまうこと、ありませんか?
わたしは仕事の合間にそんなことが何度もあり、「これって年のせいなのかな」と不安になることがあります。
特に40代に入ってからは、そういう“うっかり”が少しずつ増えてきて、不規則な仕事のせいで生活も乱れがち。
「このままだと将来は認知症かも…」なんて、つい諦めモードになってしまうこともあります。
でも、心のどこかでは「できることがあるなら、今のうちに知っておきたい」とも思っています。
そんな気持ちに応えてくれるのが、今回ご紹介する“脳の若さ”に関する研究です。
この研究は、オランダの加齢医学専門誌『GeroScience』に掲載された、ドイツの高齢者を対象としたもの。
日々の生活習慣と、脳や認知機能の“実年齢との差”との関係に注目した、とても興味深い内容です。
なお本文中では「脳が若返る」という表現を使うことがありますが、これは“脳や認知の状態が実年齢よりも良好である”ことを意味しています。
今回は、心と体をどう使えば“脳の健康”をより長く保てるのか、やさしく解説していきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“A physically and mentally active lifestyle relates to younger brain and cognitive age”
(身体的および精神的に活動的なライフスタイルは、脳と認知機能の若さに関連する)
Geroscience. 2025 Jul 7.
PMID: 40619559 DOI: 10.1007/s11357-025-01764-w
掲載雑誌:GeroScience【オランダ】 2025年7月
研究の要旨
研究目的
ライフスタイルと健康状態が脳や認知機能の老化とどのように関連しているかを調査する。
研究方法
211名の健常高齢者を対象に、ライフスタイル・健康情報、脳画像、血液バイオマーカーなどを用いて、脳年齢ギャップ(BAG:Brain Age Gap)と認知年齢ギャップ(CAG:Cognitive Age Gap)を分析。
研究結果
精神的・身体的に活動的で心血管リスクの低いライフスタイルは、BAGおよびCAGの低さ(すなわち予想より若い脳と認知機能)と関連していた。
結論
活動的なライフスタイルは、加齢に伴う脳の変性や認知機能低下に対するレジリエンス(耐性)に寄与する可能性がある。
研究の目的
年を重ねるとともに、脳の構造や認知機能はゆるやかに衰えていきます。
実際、同じ年齢でも“頭の冴え方”には大きな違いが見られることがあります。
その違いは、本当に年齢だけで説明できるのでしょうか?
この研究では、
「そうした違いは、生活習慣や健康状態と関係しているのではないか?」
という疑問を出発点に、脳のMRI画像や認知テストを通して、
“脳年齢”や“認知年齢”と生活スタイルの関係を明らかにしようとしました。
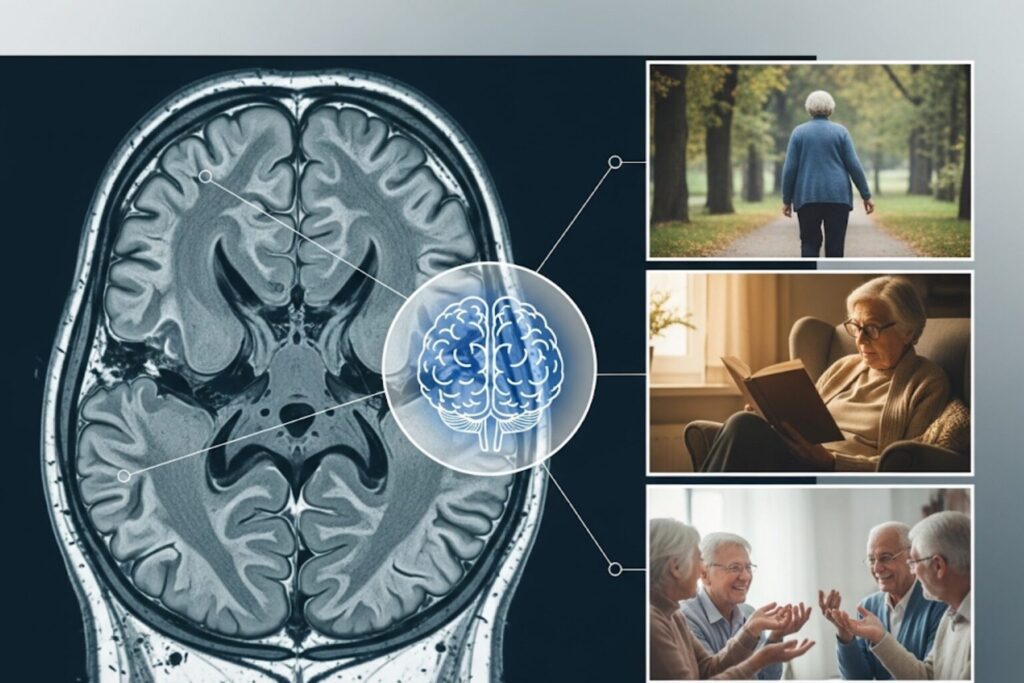
研究の対象者と背景
この研究に参加したのは、ドイツ・ベルリンに住む60歳以上の高齢者たち、合計1,316人です。

彼らは、BASE-II(Berlin Aging Study II)という高齢者の健康に関する大規模研究の一環で選ばれた参加者です。
研究に参加した方々は性別・学歴・健康状態・ライフスタイルなどは多様で、比較的健康意識が高く、自立した生活を送っている人が中心でした。
そのため、体調に課題を抱える高齢者全般にこの結果が当てはまるとは限らない点にも注意が必要です。
対象者はヨーロッパ系の高齢者ですが、研究で注目された要因(運動、趣味、社交、心臓の健康状態など)は、
日本人の生活にも共通する部分が多く、十分参考になると考えられます。

研究の手法と分析の概要
この研究は、横断的観察研究として行われました。
研究者たちは、参加者に対して以下の3つの視点からデータを収集・分析しています:
① MRIによる「脳年齢」の推定
参加者の脳のMRI画像をもとに、AIモデル(XGBoost)を使って「脳年齢」を推定。
この推定年齢と実年齢の差(Brain Age Gap)を分析しました。
このAIモデル(XGBoost)は、多数のMRIデータから学習しており、非常に高い精度で「脳の見た目年齢」を予測できるとされています。
これにより、研究全体の信頼性も高まっています。
② 認知テストによる「認知年齢」の推定
複数の認知課題(記憶・注意・処理速度など)から認知機能を総合評価し、
そこから「認知年齢」(Cognitive Age Gap)を算出しました。
③ 生活習慣と健康状態の評価
運動、趣味、読書、社会的交流、睡眠、喫煙、飲酒、血圧、血糖値、BMI、抑うつ症状など、
多くのライフスタイル要素や健康指標を記録・分類しました。
そして、これらの要素を組み合わせた「ライフスタイル+心血管+精神的健康」の3つの総合スコアを作成。
このスコアが脳年齢・認知年齢とどのように関係しているかを解析しました。
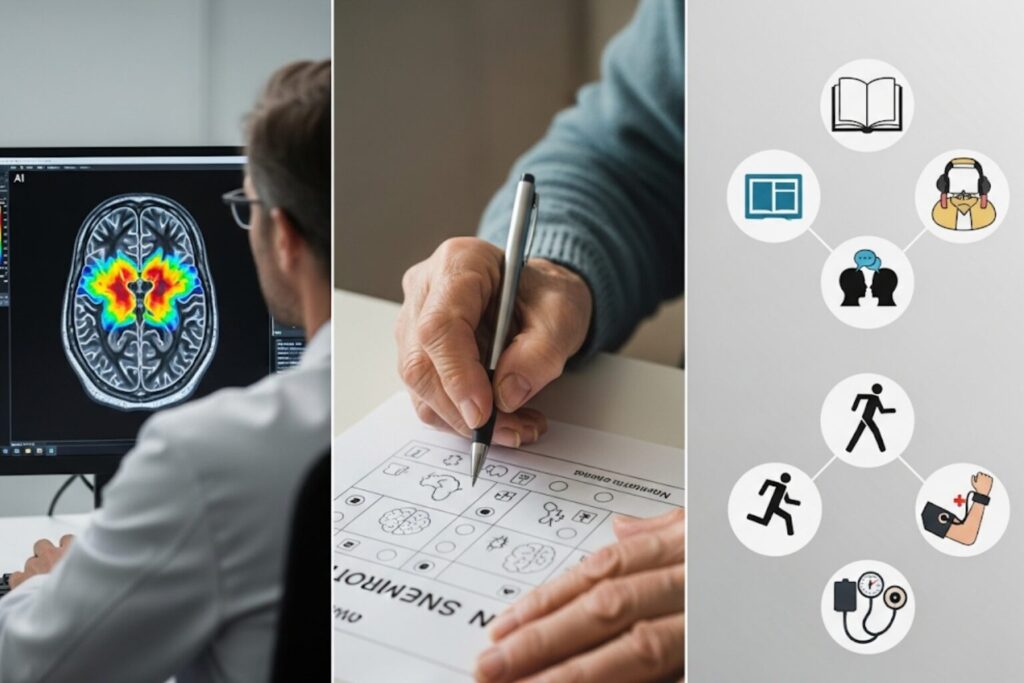
【補足:各種用語】
観察研究(横断的)
介入せずに、ある時点での状態を観察して相関関係を調べる手法。
「因果関係」は直接わからないが、「傾向」や「関連性」を見つけるのに有効。
脳年齢(Brain Age Gap)
実際の年齢と、MRI画像からAIが推定した「脳の年齢」との差。
マイナスであれば“脳が若い”、プラスなら“老化している”という指標。
認知年齢(Cognitive Age Gap)
実年齢と比較して、認知テストで示された機能レベルがどの程度“若いか・年寄りか”を示す指標。
XGBoost
たくさんの情報を組み合わせて、できるだけ正確な答えを導き出すAIの予測法のひとつです。
「この人の脳は何歳くらいか?」を推測するのに使われました。
研究結果
脳と心の“若さ”を保つ秘訣が見えてきた
この研究でわかったのは、
日常生活のスタイル・心の状態・身体の健康が整っている人ほど、
✅️脳の構造が実年齢より「若く」保たれ、
✅️記憶力や判断力などの認知機能も「年齢より良好」である
ということです。
研究では、これらの状態を点数化した3つのスコアと、“脳年齢”・“認知年齢”との差との関係が調べられました。
| 健康スコアの内容 | 脳の若さ(平均差) BAG | 認知の若さ(平均差)CAG |
| ライフスタイル(運動・趣味・睡眠など) | 約5.8歳若い | 約3.9歳若い |
| 心血管の健康(血圧・血糖など) | 約4.9歳若い | 約4.4歳若い |
| 精神的健康(抑うつが少ないなど) | 約4.0歳若い | 約2.2歳若い |
これらの3要素はすべて、脳と認知の若さにそれぞれ独立して有意に関連していることがわかりました。
「複合的な良さ」が鍵になる
とくに注目すべきなのは、
✅️3つのスコアのどれか1つだけが良好でも、他が不十分だと“脳の若さ”は得にくい
という点です。
たとえば、
・「運動はしているがストレスが多い」
・「血圧は安定しているけれど趣味がない」
といった生活では、十分な効果が得られにくい可能性があります。
また、年齢・性別・学歴・社会的背景(SES)を考慮しても、これらの関連性は統計的に有意(p<0.05)であり、
生活習慣の影響が客観的なデータとして確認された形になっています。
「生活の工夫」が、個人差を左右する
研究ではさらに、次のことがわかりました:
・脳の年齢の“個人差”のうち 約5〜7%
・認知機能の“個人差”のうち 約15%
が、生活習慣と健康状態で説明できることが示されました。
とくに認知年齢のほうが生活の影響を受けやすいという結果は、
記憶力や集中力といった認知機能が「日々の積み重ね」で変わり得るという希望につながります。
性別・学歴・社会環境の影響も
分析によって、次のような傾向も明らかになりました:
・女性の方が、生活習慣の良さによる影響がやや大きく現れる
・学歴が高く、経済的に安定している人ほど、認知年齢が若く保たれやすい
つまり、知的刺激のある生活や社会的な安定も、“脳と心の若さ”を支える要素と考えられます。

変化が見られなかった項目
一方、喫煙や飲酒といった習慣については、今回の分析では明確な関連は確認されませんでした。
また、生活習慣の影響には個人差もあり、すべての人に同じように当てはまるわけではないことも示唆されています。
ただしこの研究は「横断的観察研究」であり、生活習慣が直接“脳の若返り”を引き起こすという因果関係までは証明できません。
今後、より長期的な追跡研究や介入研究によって、こうした関係の因果性が明らかになることが期待されます。
研究の結論
“今”の積み重ねが、“将来の脳”をつくる
この研究からわかったのは――
ふだんの生活スタイルや心身の健康状態が、将来の“脳の若さ”を左右する
ということです。
・身体を動かしたり、趣味に熱中したり、しっかり眠る。
・血圧や血糖などを良い状態に保つ。
・ストレスを溜めすぎず、心を整える。
こうした積み重ねが、
脳の状態を実年齢より“良好”に保つことと深く関係していました。
しかもこれは、脳のかたち(構造)だけでなく、記憶力や集中力といった“認知のはたらき”にもつながっていたのです。
「生活習慣を見直すことで、将来の自分の脳にプラスの影響を与えられる可能性がある」
――このメッセージは、どの年代の人にとっても希望につながるものではないでしょうか。

【礼次郎の考察とまとめ】
わたしたちは「脳の老け方」を選べるかもしれない
この研究を読んで、わたしが一番印象に残ったのは、
「脳の老化には“個人差”があり、それは自分の生活で変えられるかもしれない」
という希望のある視点です。
年齢を重ねること自体は止められません。
でも「頭の回転が落ちた」「記憶力が不安」という悩みが、すべて加齢のせいとは限らないのだとしたら――
それは、少しだけ背筋が伸びるような、未来の自分を応援したくなる気持ちにさせてくれます。
もちろんこの研究の対象はドイツの高齢者で、わたしたち日本人にそのまま当てはまるとは限りません。
ですが、「心身の健康を大事にしながら、日々をアクティブに過ごすことが、脳の元気にもつながる」という考え方は、
日本のわたしたちにとってもきっとヒントになります。
特別なことをしなくてもいい。
・朝少しだけ早く起きて散歩してみる。
・興味のある本を読んでみる。
・気の合う人とおしゃべりしてみる。
そんな日々の積み重ねが、10年後・20年後の“あなたの脳”を形づくっていくのかもしれません。

締めのひとこと
脳も心も、いつからだって育て直せる
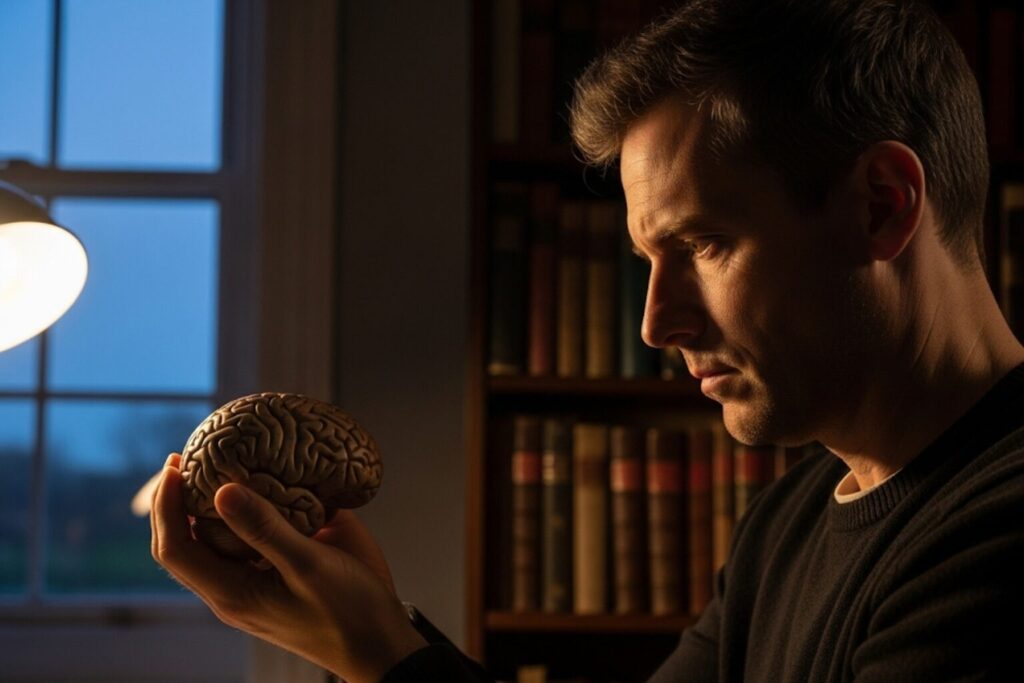
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。
🧠 脳の若さを保つなら、やっぱりこれ!
✨『ザ・脳トレ』こと――
『東北大学加齢医学研究所 監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング』
記憶、計算、集中力……
ゲーム感覚で“脳のはたらき”をやさしく刺激してくれる名作です。
私、礼次郎も以前どハマりしました。
ひさびさに、やろーっと。


コメント