
結論「脂肪を減らすには有酸素や併用が有利。ただし筋肉を守りたいなら筋トレが不可欠。はっきり差が出るのは“10週間以上”の継続から」
この記事はこんな方におすすめ
✅効率よく脂肪を減らしたいけど「筋トレと有酸素、どっちが正解?」と迷っている方
✅「体重は落ちたけど筋肉も落ちてしまった」とリバウンドが不安な方
✅筋トレも有酸素もやっているけど「やり方はこれで合ってる?」と疑問に思っている方
✅忙しい毎日の中で、最短ルートで成果を出したい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:脂肪を効率よく減らすには筋トレ?有酸素?それとも両方?
🟡結果:10週間以上続けると、有酸素や有酸素+筋トレは、筋トレだけより脂肪が約1kg多く減った。
🟢教訓:脂肪を落とすなら有酸素を中心に。ただし筋肉を残したいなら筋トレも組み合わせるのがベスト。
🔵対象:36研究・1,564人を解析。欧米中心の結果で、日本人は筋肉維持への配慮がより重要。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
運動で「痩せたい」と思ったとき、筋トレと有酸素運動のどちらを優先すべきか、迷ったことはありませんか?
「ランニングばかりしていると筋肉が落ちる」と耳にすることもあれば、逆に「筋トレだけでは体脂肪は減らない」と言う人もいますよね。
世の中には根拠があいまいな情報や意見も多く、どれを信じたらよいのか迷ってしまいます。
一生懸命トレーニングをすればどちらも効果はあるはずですが、どうせなら最短で効率よく成果を出したいのが本音だと思います。
そこで本日ご紹介するのは、「筋トレ」「有酸素運動」「両方の組み合わせ」を科学的に比較した最新の研究です。
イギリスの「Journal of the International Society of Sports Nutrition」に掲載された論文で、世界中の臨床試験をまとめたメタ解析。
つまり「どの運動が一番脂肪を落とすのか」を科学的な根拠をもって教えてくれる内容になっています。
今回は、その研究をわかりやすく読み解きながら、あなたに合った運動の選び方を考えていきましょう。
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Comparison of concurrent, resistance, or aerobic training on body fat loss: a systematic review and meta-analysis”
(同時(コンカレント)・レジスタンス・有酸素トレーニングの体脂肪減少効果の比較:系統的レビューとメタ解析)
Kworweinski Lafontant, Alexa Rukstela, Ardis Hanson et al.
J Int Soc Sports Nutr. 2025 Dec;22(1):2507949.
PMID: 40405489 DOI: 10.1080/15502783.2025.2507949
掲載雑誌:Journal of the International Society of Sports Nutrition【イギリス:IF 3.9(2024)】 2025年5月
研究の要旨
研究目的
「筋トレ」「有酸素運動」「その両方を組み合わせる方法」の中で、どれが一番脂肪を減らせるのかを調べました。
研究方法
1980年から2023年までに行われた36件の実験(1,564人が参加)をまとめ、体重や体脂肪、筋肉の変化を比べました。
研究結果
10週間以上続けた場合、有酸素運動と組み合わせ運動は、筋トレだけよりも脂肪が減りやすいと分かりました。ただし、筋肉を残す効果は筋トレの方が高い傾向がありました。
結論
脂肪を落としたい人は有酸素運動や組み合わせ運動が有利で、筋肉をしっかり残したい人は筋トレが効果的です。
考察
運動の効果は「どのくらい長く続けるか」と「どれだけ体を動かすか」に左右され、同じ日に両方の運動をするか、別々の日に分けるかはあまり大きな違いがありませんでした。
研究の目的
これまでの研究では、筋トレ(抵抗運動)は筋肉量を増やして代謝を高めることに、有酸素運動はエネルギー消費を増やして体重を減らすことに効果があるとされてきました。
さらに、両者を組み合わせた併用トレーニングは、理論的には双方の利点を得られると考えられています。
しかし実際には、「筋トレと有酸素運動では、どちらがより体脂肪を減らせるのか」「両方を組み合わせると本当に単独より効果が高まるのか」については、過去の研究結果が一致しておらず、はっきりとした答えが出ていませんでした。
これまでのレビューや解析は、主に筋力や持久力といった運動能力に焦点を当てたものが多く、体脂肪の減少そのものを直接比較したものは不足していたのです。
そこで本研究では、無作為化比較試験を体系的に収集し、筋トレ・有酸素運動・併用運動が体脂肪量、体脂肪率、体重、筋肉量に与える影響を直接比較することを目的としました。
さらに、介入期間(10週未満か10週以上か)、同じ日に行うか別の日に分けて行うか、運動量を揃えた場合の違いといった条件も検討することで、より実践的に「どんな運動が脂肪減少に効果的か」を明らかにしようとしたのです。

研究の対象者と背景
対象となった人々
分析に含まれたのは、代謝に問題のない健康な成人です。
年齢や性別は研究によって異なりますが、男女とも含まれていました。
規模と人数
システマティックレビューに組み入れられたのは36件の無作為化比較試験で、合計1,564人が対象となりました。
国や地域の背景
研究の多くは欧米で実施されており、体格や生活習慣の異なる集団を中心にしています。
日本人に当てはめる場合は、筋肉量が比較的少ないという体質の違いを考慮する必要があります。

研究の手法と分析の概要
研究デザイン
これはシステマティックレビューとメタ解析です。
1980年から2023年1月までに発表された臨床試験をデータベースから系統的に検索し、条件を満たす研究を厳選して統合しました。
比較された運動の種類
筋トレ(抵抗運動:RT)
バーベルやマシン、ダンベルを使った運動、または自重で行う腕立て伏せやスクワット。
研究では「15回程度持ち上げられる重さ(15RM)」を基準に設定されることが多く、日常でいえば「ちょっと頑張れば15回できるくらいの重さ」が目安です。
有酸素運動(AT)
ランニング、サイクリング、早歩き、エアロバイクなど、全身を使った持久的な運動。
強度は「中等度から高強度」とされ、日常の目安では「会話はできるけれど歌は歌えないくらいの息の弾み方」が相当します。
併用運動(CT)
筋トレと有酸素運動を同じ週に取り入れる方法。
たとえば「月水金は筋トレ、火木土はランニング」のように日を分けたり、「1日の中で筋トレとバイクを両方やる」形でも実施されていました。
・このレビュー自体は具体的に「スクワット」「ベンチプレス」といった種目までは提示していません。
・ただし、有酸素は「中〜高強度の全身持久的運動」、筋トレは「15RMを基準とした負荷を用いたレジスタンストレーニング」が典型的に使われていました。
・運動量や消費カロリーをそろえる工夫をした試験も含まれているため、「単純にランニング vs 筋トレ」ではなく、なるべく公平に比較できるようになっています。
評価項目
・体脂肪量(脂肪の重さそのもの)
・体脂肪率(体重のうち脂肪が占める割合)
・体重
・除脂肪体重(筋肉・骨・水分など脂肪以外の体重)
サブ解析(追加の分析条件)
・介入期間:10週間未満と10週間以上で比較
・運動のタイミング:同じ日に行うか、別の日に分けて行うか
・仕事量(運動の総量):運動量を揃えた場合の効果の違い

【補足:各種用語】
システマティックレビュー
あるテーマに関する研究を、ルールに従って網羅的に集め、質を評価しながらまとめる方法です。
メタ解析
集めた複数の研究データを統計的に統合し、全体としての平均的な効果を数値で示す方法です。
研究結果
主な発見
10週間以上続けた場合、有酸素運動(AT)と有酸素+筋トレ(CT)は、筋トレ(RT)のみよりも体脂肪の減少効果が大きいことが分かりました。
・ATはRTより 体重で約1.8kg、体脂肪で約1kg多く減少(有意差あり)
・CTもRTより 体脂肪で約1kg多く減少(有意差あり)
・筋肉量(除脂肪体重)はRTが最も維持でき、ATでは 約0.9kgの減少が見られました
・体脂肪率(体重に占める脂肪の割合)には有意な差はありませんでした
ATとCTの比較
体重の減少ではATがCTよりやや優れていましたが、体脂肪量や筋肉量では大きな違いはありませんでした。
運動期間の影響
10週間未満では3つの運動方法の間にほとんど差はありませんでした。
10週間以上継続して初めて明確な差が現れた点は重要です。
運動量(仕事量)の調整
消費エネルギーや運動時間をそろえて比較した場合、3つの方法の差はほとんどなくなりました。
つまり、総運動量が同じであれば、運動の種類による違いは小さいといえます。
実施タイミング(同日 vs 別日)
CTを同じ日に行うか別の日に分けるかで、効果に大きな差はありませんでした。
一部の研究で「同日実施で体脂肪減少がやや大きい」という傾向はありましたが、統計的には有意な差ではありませんでした。
性別や年齢の違い
女性や高齢者を対象とした研究も含まれていましたが、性別や年齢による明確な違いは確認されませんでした。
結果まとめ表
| 運動方法 | 体重の減少 | 体脂肪量の減少 | 筋肉量の保持 | 体脂肪率 | 特記事項 |
| 筋トレのみ (RT) | 少なめ | 少なめ | 最も良い | 差なし | 筋肉を守りたい人向け |
| 有酸素運動 (AT) | 最大 | 大きい | やや減少 | 差なし | 長期間で効果大、短期では差なし |
| 有酸素+筋トレ (CT) | 中程度 | 大きい | 中程度 | 差なし | 有酸素と筋トレを両立可能 |
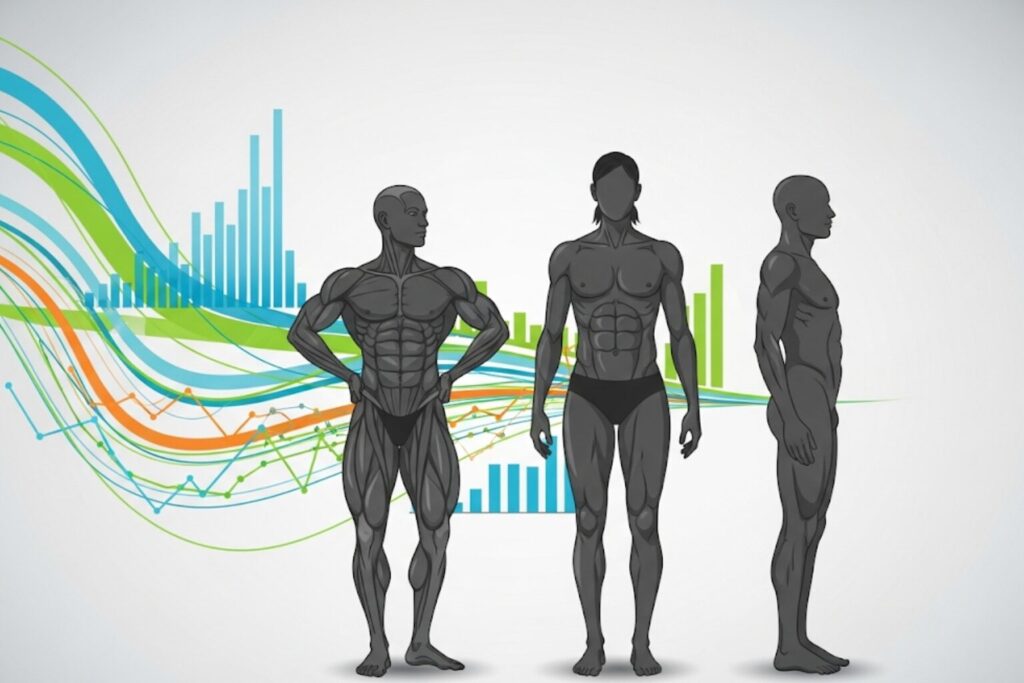
研究の結論
✅️脂肪を落とすには有酸素運動や有酸素と筋トレの組み合わせが効果的であり、筋肉を守りたいなら筋トレが欠かせない
体重と体脂肪を減らす効果は有酸素運動や併用運動のほうが明らかに大きい一方で、筋肉量を維持する効果は筋トレが最も優れていました。
体脂肪率そのものには大きな差はなく、また運動の種類よりも「どれだけ続けるか」「どのくらいの量をこなすか」が効果の分かれ目になっていました。
さらに、併用運動を同じ日に行うか、別の日に行うかによる違いはほとんど見られず、少なくとも体脂肪の減少においては順序よりも継続のほうが重要だと示されました。
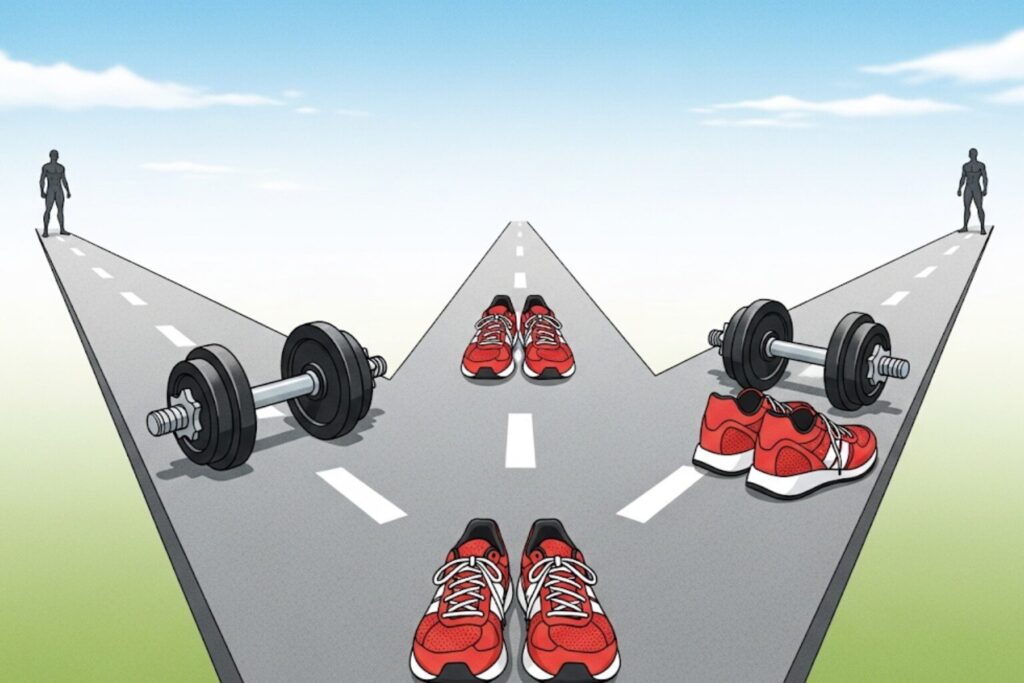
【礼次郎の考察とまとめ】
論文著者の考察
著者たちは、有酸素運動が体脂肪の減少に優れていた理由として、1回あたりのエネルギー消費が大きいことを挙げています。
反対に、筋トレは直接的な脂肪燃焼効果は小さいものの、筋肉を維持・増加させるため安静時の代謝を高め、リバウンドの防止に役立つと解釈しています。
そして両者を組み合わせることで、脂肪を落としながら筋肉をある程度保つというバランスの取れた効果が得られると説明しています。
ただし、併用では「干渉効果」と呼ばれる現象によって筋肉維持効果が弱まる可能性があるとも指摘されました。
さらに、運動量をそろえると効果の差が小さくなることから、どんな運動を選ぶか以上に「どれくらい動くか」が減量に直結するとしています。
また、短期間では結果に差が出にくく、10週間以上続けることで初めて有意な違いが見えてきました。
性別や年齢による違いは明確ではありませんでしたが、女性や高齢者を対象にした研究はまだ少なく、今後の課題とされています。
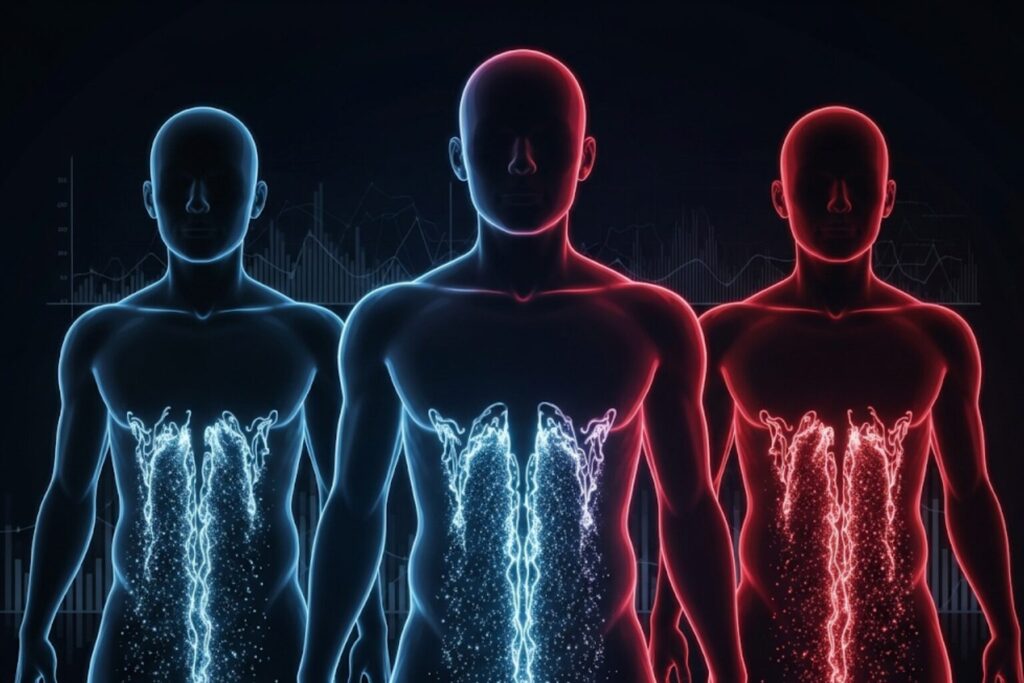
日常生活へのアドバイス
日常生活に置き換えると、この研究は「目的に応じて運動を選ぶこと」と「長く続けること」の両方が大切だということを教えてくれます。
たとえば、体重や体脂肪をしっかり減らしたい人はジョギングや自転車などの有酸素運動を中心にするとよいでしょう。
筋肉を落としたくない人は、スクワットや腕立てといった筋トレを取り入れる必要があります。
そして両方をうまく組み合わせれば、脂肪を落としながら引き締まった体を目指すことが可能です。
実際の生活では、有酸素と筋トレを同じ日にまとめても、別々の日に分けても効果は大きく変わらないため、自分のペースや習慣に合わせて選べば十分です。
わたし自身の感想としては、多くの人が感覚的に「有酸素は痩せる」「筋トレは筋肉を守る」と思っていたことが、この研究で科学的に裏付けられたのはとても大きいと感じました。
ただし、はっきりとした差を出すには10週間以上、つまりおよそ3か月の継続が必要でした。
逆に言えば、それより短い期間であれば、筋トレか有酸素かという区別に神経質になる必要はなく、どちらの努力も無駄にはならないということです。
また、Apple Watchのようなウェアラブルデバイスを活用して運動時の消費エネルギーを把握できれば、どの運動を選ぶかにこだわりすぎなくてもよいのではないでしょうか。
最終的には「どの種類の運動を選んだか」よりも「きちんと動いてエネルギーを使ったか」が重要であることを、この研究は示しています。
いずれにしても、この結果は「努力は裏切らない」ということの証明でもあります。
自分に合った運動を見つけて、無理なく続けていくことが健康的な成果につながるのではないでしょうか。

締めのひとこと
脂肪を落とすにも筋肉を守るにも、継続がすべてです

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント