
結論「少量のお酒は抑うつリスクを下げる一方、中程度以上では自殺リスクを高める──この“両刃の剣”が最新研究で明らかになりました」
この記事はこんな方におすすめ
✅お酒とメンタルの関係を科学的に知りたい方
✅「少しのお酒は本当に体に良いの?」と気になっている方
✅家族や友人の飲み方が心配でヒントを探している方
✅お酒と上手に付き合う方法を知りたい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:お酒は心に良いのか?悪いのか?
🟡結果:1日1杯なら抑うつリスクが下がるが、2杯以上で自殺リスクが急上昇。
🟢教訓:健康や気分のために「新しく飲み始める」のは危険。飲むなら“少量・ほどほど”がカギ。
🔵対象:韓国12万人を9年追跡。日本人も体質的に参考になるが、そのまま当てはめるのは注意が必要。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
お酒の席で楽しくなりすぎて、翌日どっと落ち込んだ経験はありませんか?
これはあくまで日常的な例え話ですが、実際に「飲酒と心の健康」の関係は医学的にも研究されているんです。
これまでは「飲酒と寿命の関係」や「アルツハイマー病への影響」といった身体の健康に関するテーマを中心にお話ししてきました。
今回は少し切り口を変えて、お酒が心の健康(メンタルヘルス)にどんな影響を与えるのかを見ていきます。
具体的には、「今までお酒を飲んでいなかった人が飲み始めたとき、その量によって抑うつや自殺リスクがどう変わるのか?」 という、少しシビアで大切なテーマです。
ご紹介するのは、韓国の12万人以上を対象にした大規模研究で、アメリカの医学雑誌 Depression and Anxiety(日本語では「抑うつと不安」)に掲載された精神医学の専門的な知見です。
この記事では、「お酒は少しだけなら心に良いのか?それとも危険なのか?」という疑問に迫り、日常生活に役立つヒントをお届けします。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Associations of Changes in Alcohol Consumption on the Risk of Depression/Suicide Among Initial Nondrinkers”
(初回時非飲酒者における飲酒量の変化と抑うつ・自殺リスクの関連)
Sungmin Cho, Sangwoo Park, Su Kyoung Lee et al.
Depress Anxiety. 2024 Nov 11:2024:7560390.
PMID: 40226658 DOI: 10.1155/2024/7560390
掲載雑誌:Depression and Anxiety【アメリカ:IF 3.6(2024)】 2024年11月
研究の要旨
研究目的
非飲酒者が飲み始めた際の飲酒量の違いが、抑うつや自殺リスクに与える影響を検討。
研究方法
韓国成人12万9千人を約9年間追跡し、飲酒習慣の変化と抑うつ・自殺の発生率を比較。
研究結果
少量(~1杯/日)は抑うつリスク低下と関連、中等度以上(2~4杯/日)は自殺リスク上昇、元飲酒者で4杯以上は抑うつリスク増加。
結論
軽度の飲酒開始は抑うつを減らす可能性があるが、中等度以上では自殺リスクが高まる。
考察
社会的要因や生物学的機序の関与が考えられるが、自己申告バイアスや民族特異性により結果の一般化には注意が必要。
研究の目的
この研究の目的は、「お酒を飲んでいなかった人が新たに飲み始めたとき、その飲酒量の変化が抑うつや自殺のリスクにどう影響するのか」を明らかにすることです。
従来の研究は「飲酒とメンタルヘルスの関係」を扱っていましたが、ほとんどが一時点の飲酒状況だけを測定しており、「時間の経過による飲酒習慣の変化」がどのように影響するかは十分に検討されていませんでした。
そこで本研究では、韓国の12万人以上を対象に、長期間にわたって飲酒習慣の変化と抑うつ・自殺リスクとの関係を詳細に追跡することが試みられました。
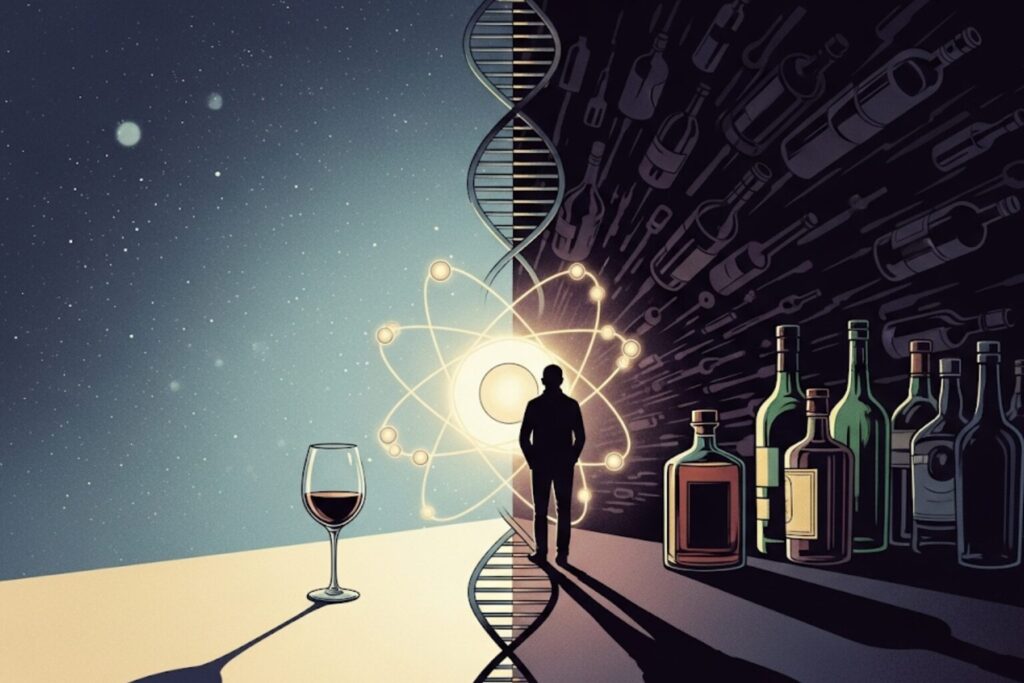
研究の対象者と背景
この研究は韓国の大規模データをもとに行われました。

対象者
この研究は、韓国の国民健康保険データを用いた大規模な追跡調査です。
対象は 成人129,446人。
その内訳は、真の非飲酒者 102,721人 と 元飲酒者 26,725人 でした。
背景
韓国は飲酒文化が盛んである一方で、自殺率が高くメンタルヘルスが大きな社会課題となっています。
日本人もアルコール分解能力が弱い人が多いため、この結果は参考になりますが、文化や生活習慣の違いからそのまま当てはめる際には注意が必要です。

研究の手法と分析の概要
研究デザインと期間
研究の形式は 前向きコホート研究。
2011年1月から2019年12月まで平均約9年間追跡し、飲酒習慣の変化と抑うつ・自殺の発生を比較しました。
飲酒量の測定方法
飲酒量は健康診断での自己申告をもとに、1杯=純アルコール10g として定量化しました。
具体例
・ビール中ジョッキ約1杯弱(350ml缶の3/4程度)
・ワイン1杯(約100ml)
・焼酎25度で約60ml
この基準を用いて、
・0杯/日(非飲酒)
・1杯未満/日
・1杯以上2杯未満/日
・2杯以上4杯未満/日
・4杯以上/日
に分類しました。
また、週の飲酒頻度(週1回未満/週1回/週2回/週3~4回/週5回以上)も調査対象となりました。

評価項目と分析
・抑うつは診断記録(ICD-10)や抗うつ薬の処方で判定
・自殺は死亡票の死因登録で判定
分析には Cox回帰分析(Cox比例ハザードモデル)を用い、年齢・性別・運動習慣・BMIなどを段階的に調整することで、飲酒そのものの影響をできるだけ正確に評価しました。
【補足:各種用語】
観察研究
自然な集団を長期間追いかけ、生活習慣と病気の関連を調べる方法。
コホート研究
ある条件で人を集めて、将来の発症率を比べる研究デザイン。
ハザード比(HR)
ある群のリスクが基準と比べて何倍かを示す数値。1.0が基準で、0.9ならリスク10%低下、1.3なら30%増加を意味します。
研究結果
抑うつリスクの変化
非飲酒を続けた人を1.0とした場合:
飲酒量
・1杯未満/日→ 0.91倍(約9%低下)
・1杯以上2杯未満/日 → 0.98倍(有意差なし)
・4杯以上/日(元飲酒者含む) → 1.31倍(約30%上昇)
※元飲酒者で再び4杯以上飲むようになった人は、抑うつリスクが特に高まる傾向がありました。
飲酒頻度
・週1回 → 0.88倍(約12%低下)
・週2回 → 0.97倍(有意差なし)
・週3回以上 → 有意差なし
サブグループ解析:
・60歳未満 → 軽飲酒で0.85倍(15%低下)
・運動習慣あり → 軽飲酒で0.87倍(13%低下)
・非喫煙者かつ4杯以上 → 1.33倍に上昇
👉 抑うつについては「直線的に増える/減る」傾向は確認されず、少量で下がるが、多量で逆に上がる“カーブ型”の関係が見られました。

自殺リスクの変化
非飲酒を続けた人を1.0とした場合:
飲酒量
・1杯未満/日 → 1.02倍(有意差なし)
・1杯以上2杯未満/日 → 1.05倍(有意差なし)
・2杯以上4杯未満/日 → 2.25倍(2倍以上に上昇)
・4杯以上/日 → 上昇傾向(有意差なし)
飲酒頻度
・週1回 → 1.01倍(有意差なし)
・週2回 → 1.02倍(有意差なし)
・週3~4回 → 2.03倍(約2倍に上昇)
・週5回以上 → 1.15倍(増加傾向だが有意差なし)
直線的効果:
・飲酒を1杯増やすごと → 自殺リスク1.17倍
・飲酒日を1日増やすごと → 自殺リスク1.15倍
👉 自殺については、飲酒量や飲酒日の増加に応じて直線的にリスクが上がる「階段型」の関係が見られました。

その他
・性別による違いは小さく、全体と同じ傾向が見られました。
・1杯以上2杯未満/日や週2回の飲酒は、抑うつ・自殺ともに大きな変化は見られませんでした。
・自殺件数は抑うつに比べて少なく、数字の解釈には注意が必要です。方向性を示すものとして受け取ることが適切です。
まとめ表
| 飲酒習慣の変化 | 抑うつリスク | 自殺リスク |
| 非飲酒を継続 | 1.0(基準) | 1.0(基準) |
| 1杯未満/日 | 0.91倍 ↓ | 1.02倍(変化なし) |
| 1杯以上2杯未満/日 | 0.98倍(変化なし) | 1.05倍(変化なし) |
| 2杯以上4杯未満/日 | ―(有意差なし) | 2.25倍 ↑↑ |
| 4杯以上/日(元飲酒者含む) | 1.31倍 ↑ | 上昇傾向(有意差なし) |
| 週1回 | 0.88倍 ↓ | 1.01倍(変化なし) |
| 週2回 | 0.97倍(変化なし) | 1.02倍(変化なし) |
| 週3~4回 | ―(有意差なし) | 2.03倍 ↑↑ |
| 週5回以上 | ―(有意差なし) | 1.15倍(増加傾向) |
| 1杯増加 | ― | 1.17倍 ↑ |
| 飲酒日1日増加 | ― | 1.15倍 ↑ |
研究の結論
✅️非飲酒者がお酒を飲み始めると、少量なら抑うつリスクが下がるが、中等度以上では自殺リスクが上がる
という結論でした。
具体的には
✅️抑うつリスク低下⇩と関連 → 少量(1日1杯未満)の飲酒開始
✅️抑うつリスクの上昇⇧と関連 → 多量飲酒(1日4杯以上、特に元飲酒者や非喫煙者)
✅️自殺リスクが顕著に上昇⇧ → 2杯以上の飲酒開始(1日2杯 以上で自殺リスクはおよそ2倍に上昇)
という結論が導かれました。

【礼次郎の考察とまとめ】
論文著者の考察
なぜこのような結果が出たのか。著者たちは以下のように解釈しています。
・軽い飲酒は社交の場で人とのつながりを増やし、気分を和らげる作用がある可能性
・生物学的な働きとして、少量のアルコールが脳の神経成長因子(BDNF)に影響し、気分の安定に寄与する可能性
・一方、中等度以上の飲酒は脳のバランスを崩し、気分障害や衝動性の高まりを通じて自殺リスクを押し上げる
また、飲酒量は自己申告であり、教育や食生活などの交絡因子が考慮しきれていない点、自殺件数が少ないため統計的に安定性に限界がある点も指摘されています。

日常生活への示唆
この結果から学べることはシンプルです。
・少量なら気分を和らげる効果があるかもしれない
・しかし、量や頻度を増やすと一気にリスクが跳ね上がる
・特に「自殺リスクの直線的な増加」は見逃せません
つまり「気分のためにお酒を飲む」のは慎重であるべきで、健康やメンタルのために新たにお酒を始めることは勧められません。
では、私たちの日常生活にどう役立てればよいのでしょうか?
「ストレス発散の一杯」を見直す
疲れた日の“ご褒美の一杯”は一時的に気分を和らげるかもしれません。
ただし、それが週3回以上になると、リスクが一気に上がることがわかっています。
「今日は本当に飲みたい日?」と自分に問いかける習慣が安心につながります。
お酒以外の“気分転換”を持つ
研究では「運動習慣がある人」で軽い飲酒の抑うつリスク低下が強く見られました。
つまり、お酒に頼らず、軽い運動や散歩で気分を上げることも有効です。
周囲の人を思いやる視点
自分だけでなく、家族や友人の飲酒習慣にも目を向けてください。
特に「最近飲む量が増えてきた」「週に何度も飲んでいる」と感じる人には、やさしく声をかけることが、心の健康を守るきっかけになるかもしれません。

日本人はアルコール分解が弱い体質の人が多く、少量でも体に負担がかかりやすい特徴があります。
韓国の研究結果はそのまま参考になりますが、文化や生活習慣の違いから、「健康のためにはお酒は飲まないほうがよい」という意識を持つことが大切です。
締めのひとこと
お酒を心の重荷にしないように

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。




コメント