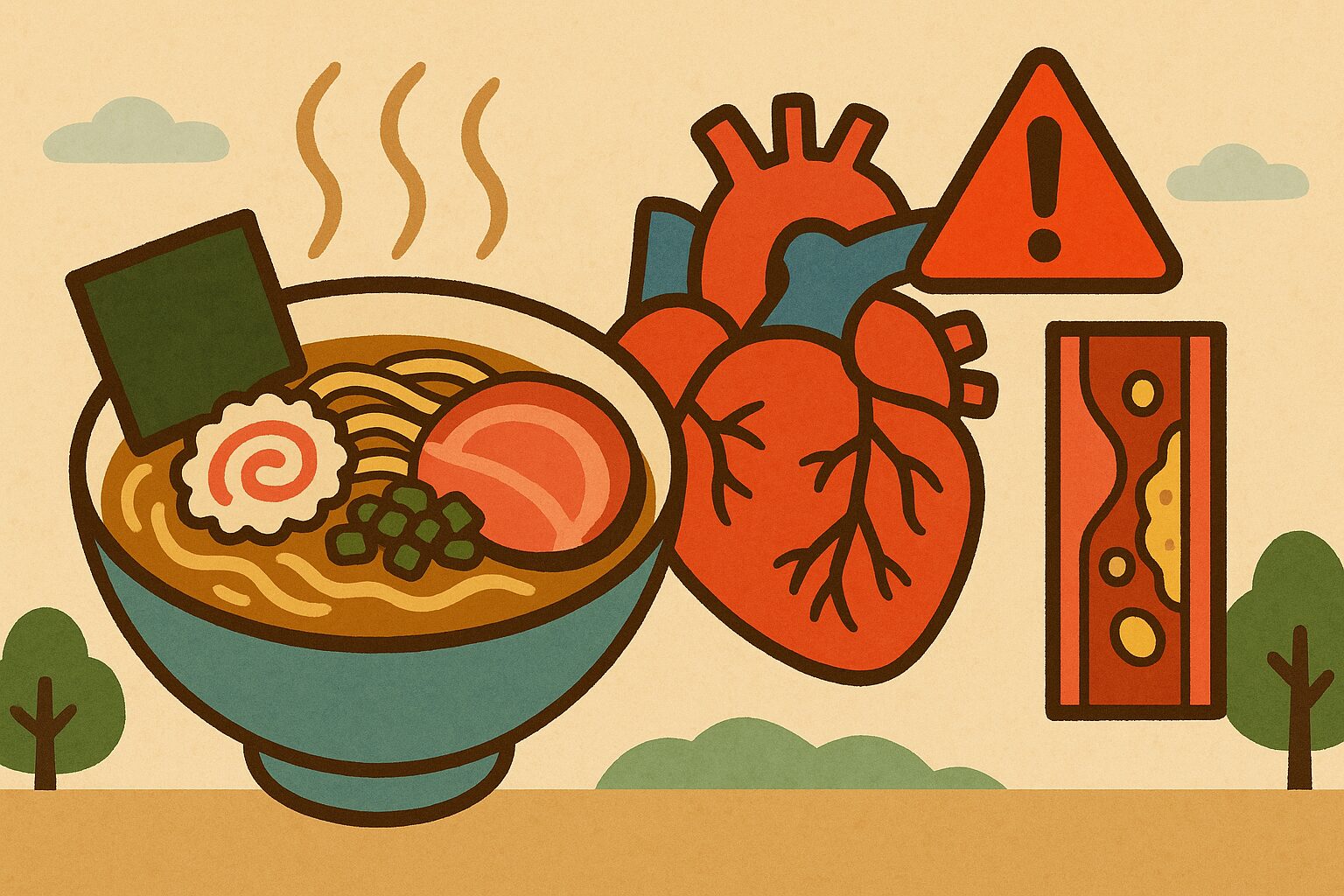
結論「ラーメンを週3回以上食べる人は死亡リスクが約1.5倍に
特に男性・70歳未満・スープをよく飲む人・飲酒習慣がある人で危険性が高いことがわかりました」
この記事はこんな方におすすめ
✅ラーメンは好きだけど健康への影響が気になる方
✅塩分・生活習慣病リスクを減らしたい方
✅「スープは全部飲んで大丈夫?」と疑問に思ったことがある方
✅科学的根拠に基づいた食生活の工夫を知りたい方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:おいしいラーメン、健康への影響は?
🟡結果:ラーメンを週3回以上食べる人は死亡リスクが約1.5倍に。特に「男性・70歳未満・スープをよく飲む・お酒を飲む人」では2倍以上になることもわかりました。
🟢教訓:食べる回数やスープの量、飲酒習慣を見直すだけでリスクを減らせる可能性があります。
🔵対象:日本・山形県在住の40歳以上 6,725人を対象とした大規模研究。日本人の生活に直結する内容です。
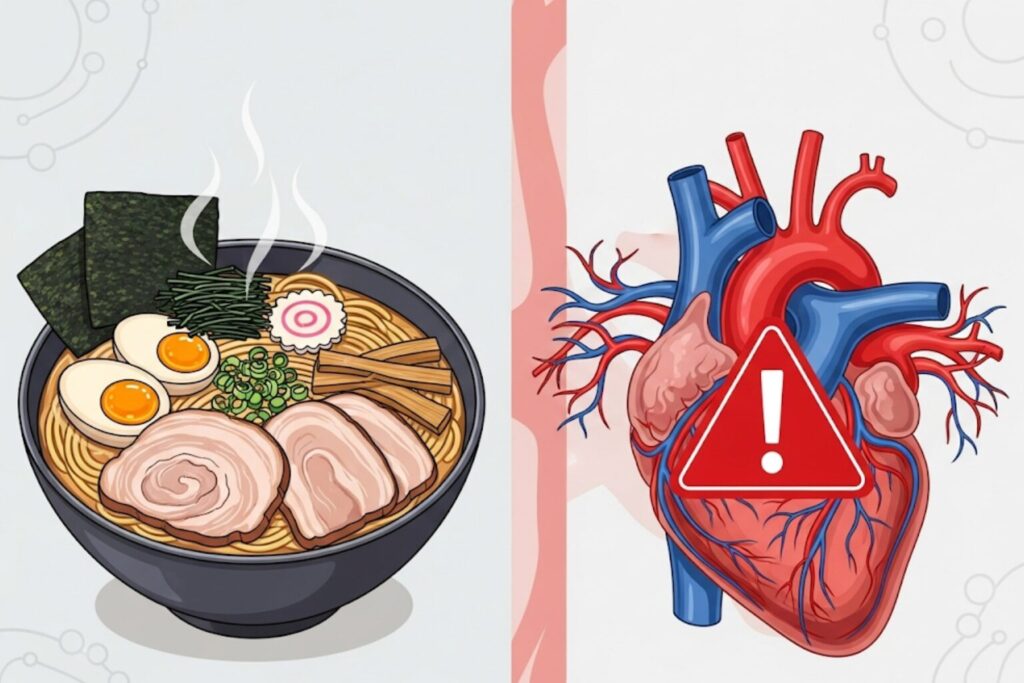
※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さんこんにちは!
皆さんはラーメン、お好きですか?
日本人の国民食ともいえるラーメンは、手軽で美味しくて、つい週に何度も食べたくなってしまいますよね。
ただその一方で、「体に悪いのでは?」と気になることも…。
以前、「ラーメン店の多い県ほど脳卒中での死亡率が高い」という研究結果をご紹介したことがあります。
あれは都道府県単位の統計に基づいたもので、個人レベルの健康への影響まではわかりませんでした。
そこで今回は、個人単位でラーメンの摂取頻度と死亡率の関係を調査した、日本の研究チームによる最新の研究をご紹介します。
掲載されたのは、フランス発・栄養と高齢化を専門とする国際医学誌『The Journal of Nutrition, Health and Aging』。
ラーメンを健康的に楽しみたい方には、見逃せない内容です!
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Frequent Ramen consumption and increased mortality risk in specific subgroups: A Yamagata cohort study”
(特定の集団におけるラーメンの頻繁な摂取と死亡リスクの増加:山形コホート研究)
Miho Suzuki, Natsuko Suzuki, Ri Sho, Masayoshi Souri, Tsuneo Konta
J Nutr Health Aging. 2025 Aug 1;29(10):100643.
PMID: 40752043 DOI: 10.1016/j.jnha.2025.100643
掲載雑誌:The Journal of Nutrition, Health and Aging【フランス:IF 3.2(2024)】 2025年8月
研究の要旨
研究目的
ラーメンの摂取頻度と死亡との関連性を日本の一般住民において明らかにすること。
研究方法
山形県の住民6,725人(40歳以上)を対象に、2009年から2023年まで追跡し、ラーメン摂取頻度・スープ摂取量・生活習慣と死亡リスクを解析。
研究結果
週3回以上ラーメンを食べる群では、男性・70歳未満・スープを50%以上飲む・飲酒している人で死亡リスクが有意に高かった。
結論
ラーメンの過剰摂取は一部の人々において健康リスクを高める可能性がある。
考察
背景要因(性別、年齢、飲酒・塩分摂取など)によってラーメンの健康影響は異なるため、個別の注意喚起が必要。
研究の目的
ラーメンは日本人にとって欠かせない人気メニューですが、スープを含めると非常に塩分が多いことが知られています。
過剰な塩分摂取は、脳卒中や胃がん、心血管疾患のリスクを高めるといわれています。
これまでにも「ラーメン店が多い地域ほど脳卒中の死亡率が高い」という報告はありましたが、それはあくまで都道府県単位の統計データを使ったもの。
そこで今回の研究では、日本の一般住民一人ひとりのラーメンの食べ方と死亡リスクの関係をより詳細に調べるため、個人単位での摂取頻度と死亡との関連を検証しました。
つまり、「ラーメンを週にどのくらい食べると危険なのか? スープを飲むとどうなるのか?」
といった、日々の食習慣と健康の関係を明らかにしようとした研究です。
研究の対象者と背景
対象となった人
この研究に参加したのは、
日本・山形県に住む40歳以上の男女6,725人。

2009年から始まった山形大学の地域住民を対象とした「山形コホート研究」の一環として実施されました。
参加者は、
・男性:2,349人
・女性:4,376人
と、女性のほうがやや多い構成です。
なぜ山形?そして日本人への影響は?
山形県は、全国でもラーメンの消費量が非常に多い地域として知られています。
特に山形市は、2024年の総務省「家計調査」によると、1世帯あたりのラーメン外食費が全国第1位を記録。
2位の新潟市に6,000円以上もの差をつけて、圧倒的な1位となっています。
都道府県単位での消費額ランキングは正式には公表されていませんが、「ラーメン大国・山形」といっても過言ではないでしょう。
そんな山形県で行われたこの研究は、ラーメンの摂取と健康への影響をリアルに反映しやすい条件がそろっています。
また、対象者はすべて日本人であり、使われているデータも日本国内の生活習慣や食文化に基づくものです。
そのためこの研究結果は、私たち日本人が自分ごととして受け止めやすく、生活に応用しやすい貴重な知見だといえるでしょう。

研究の手法と分析の概要
研究デザイン
この研究は「観察研究:前向きコホート研究」という方法で行われました。
つまり、参加者に特別な治療や食事指導などはせず、日常生活の中でどれだけラーメンを食べているか?を追跡する形です。
対象者にアンケートを郵送し、記入後に返送してもらう形式で、食事や生活習慣に関するデータを収集しました。
調査期間と追跡方法
・調査開始:2009年
・追跡終了:2023年12月まで(最大で約14年)
・中央値の追跡期間:4.5年間
・死亡情報:参加者の死亡は死亡診断書に基づき正確に把握されています。
本研究のアウトカムは「全死因による死亡」のみで、他の疾患発症(例:糖尿病や高血圧の新規発症など)は対象外です。

ラーメンの摂取頻度の分類
ラーメンを食べる頻度は、以下の4グループに分類されました
| 頻度 | 内容 |
| 月に1回未満 | ほとんど食べない人 |
| 月1〜3回 | たまに食べる人 |
| 週1〜2回 | 普通に食べる人 |
| 週3回以上 | よく食べる人(ラーメン好き) |
さらに、「ラーメンのスープをどれくらい飲むか?」もチェックされました。
スープの摂取量は
・「半分以上(≧50%)」
・「半分未満(<50%)」
の2つに分けて評価しています。
分析方法
参加者の死亡リスクを比較するため、「Cox比例ハザードモデル」という統計手法が使われました。
この方法では、
・年齢
・性別
・喫煙・飲酒習慣
・糖尿病・高血圧・脂質異常症の有無
などの健康状態の違いを調整したうえで、ラーメン摂取と死亡リスクの関係を分析しています。

【補足:各種用語】
観察研究
参加者に対して特別な治療や指導をせず、普段の生活の中での行動や健康状態を見守る調査のことです。
今回の研究では、ラーメンの食べ方を観察し、将来の健康状態(死亡)との関係を調べました。
前向きコホート研究
研究開始時に健康な人たちを集めて、将来どんな健康変化が起きるかを追いかける方法です。
今回のように「ラーメンをどれくらい食べていたか?」という情報を先に集め、その後に「誰が亡くなったか?」を追跡する形なので、“前向き”な流れでの調査となります。
この手法は、原因と結果の時間的なつながりを評価しやすいという特徴があります。
Cox比例ハザードモデル
「ある条件の人の死亡リスクは、別の条件の人より何倍高いか?」を比較するための統計方法です。
たとえば、「週3回以上ラーメンを食べる人の死亡リスクは、週1〜2回の人より2.7倍」などの数値を導きます。
研究結果
週3回以上のラーメン習慣が、死亡リスクを約1.5倍に
調査対象となった1,915人のうち、
追跡期間(中央値4.5年)中に145人が亡くなりました。
分析の結果、
ラーメンを週に3回以上食べている人は、そうでない人に比べて死亡するリスクが明らかに高くなる傾向が確認されました。
具体的には、週1〜2回ラーメンを食べる人が最もリスクが低く、このグループを基準に比較したところ、
「週3回以上」の人の死亡リスクは1.48倍(95%信頼区間:0.85〜2.56)と推定されました(P=0.16)。
統計的には「有意」とは言えませんが、明確な傾向としてリスクが上昇していた点は注目に値します。
リスクが高まる条件と傾向
さらに詳細な分析では、次のような条件に該当する人ほど、ラーメンの影響による死亡リスクが顕著に高くなることがわかりました。
| 条件 | 死亡リスクの傾向(週1〜2回を基準に比較) |
| ラーメンを週3回以上食べる人 | 約1.5倍に上昇(HR=1.48) |
| 男性 | 約2倍のリスク増加 |
| 70歳未満の人 | 約2.2倍のリスク増加 |
| スープを半分以上飲む人 | 約2.4倍のリスク増加 |
| 飲酒習慣があり、週3回以上食べる人 | 最大2.7倍のリスクに |
特に注目すべきは、「スープを半分以上飲む」人と「飲酒習慣がある」人の組み合わせです。
これらの条件では、ラーメンの頻度が高くなるにつれて、死亡リスクが急激に上昇していました。
また、飲酒やスープ摂取量との“組み合わせ”がリスクを相乗的に高めていることも統計的に裏付けられており、
交互作用(interaction)の検定でも、飲酒(P=0.002)・スープ摂取量(P=0.003)の両方が有意な結果を示していました。
これは、「単なる食事内容」ではなく、「生活習慣の積み重ねが健康に与える影響の大きさ」を物語っています。
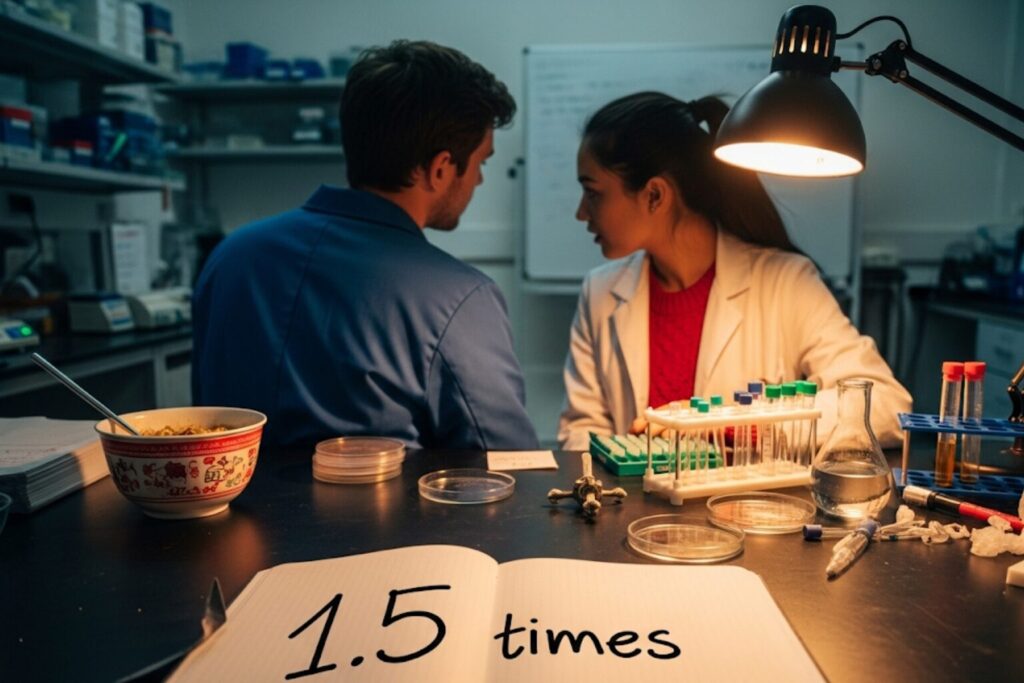
「ほとんど食べない人」にもリスク上昇?
一方で、「ラーメンを月1回未満しか食べない人」の中にも、ややリスクが高くなる傾向が見られました。
研究チームはその理由として、「健康状態が悪化したことで、医師の指導などによりラーメンを控えている人が含まれていた可能性(=逆因果性)」を指摘しています。
つまり、「ラーメンをまったく食べないから健康」という単純な話ではなく、もともとの体調や生活背景を含めて評価する必要があるというわけです。
女性ではリスク上昇は見られず
男女別に分析すると、男性ではラーメンの頻度が高いほど死亡リスクも上昇する傾向がはっきり見られました。
一方、女性ではこの関連は明確ではなく、統計的にも有意なリスク増加は確認されませんでした。
この違いの理由は明らかではありませんが、性差による代謝や生活習慣の違いが関与している可能性があります。
この結果が示す意味とは?
この研究は、「ラーメンそのものが悪い」というよりも、
食べ方や習慣の“積み重ね”が健康リスクに大きく影響することを教えてくれます。
たとえば、
・「スープを飲み干す」
・「お酒を一緒に飲む」
・「頻度が高すぎる」
といった条件が重なると、リスクが何倍にも膨れあがることがわかりました。

研究の結論
この研究は、日本人の中高年を対象に、ラーメンの摂取頻度と死亡リスクの関係を調べたものです。
結果として、
✅️週に3回以上ラーメンを食べる人は、死亡リスクが約1.5倍に増加している
ことがわかりました。
特にリスク上昇が目立ったのは、以下のような条件に当てはまる人たちです:
✅️男性
✅️70歳未満の比較的若い層
✅️飲酒習慣がある人
✅️スープを半分以上飲む人
これらの条件が複数重なることで、死亡リスクはさらに高くなる傾向が確認されました。
とくに、「スープ摂取量」と「飲酒習慣」との組み合わせでは、相乗的にリスクが上昇していました。
一方で、女性では明確なリスク上昇は確認されておらず、また「ラーメンを月1回未満しか食べない人」の中にもややリスクが高まる傾向が見られました。
これは、健康状態の悪化によりラーメンを控えている人が含まれていた可能性もあると考えられています(逆因果性)。
つまり、ラーメンそのものよりも、“頻度 × 食べ方 × 生活習慣”という掛け合わせが、健康リスクに大きく影響しているという点が、この研究の重要なポイントです。

【礼次郎の考察とまとめ】
なぜこうした結果が出たのか?(論文著者の考察より)
今回の研究では、ラーメンの摂取頻度と死亡リスクの関連が、
「ラーメンを食べること」そのものではなく、「食べ方や生活習慣の組み合わせ」によって左右されることが明確になりました。
著者らは、
ラーメンに含まれる高塩分や脂質、カロリーが、血圧や動脈硬化といった循環器系のリスクに長期的に影響する可能性を丁寧に指摘しています。
また、「スープを多く飲むこと」や「飲酒習慣」との相互作用に注目した点、
さらに「ほとんど食べない人」にも健康上の要因があるかもしれないという逆因果性への配慮も含め、
観察研究としてのバイアスや限界にも誠実に言及しており、非常に高い倫理性と科学的配慮が感じられる研究です。

ラーメンとどう付き合うか? わたしたちのヒントに
この研究が教えてくれるのは、「ラーメンが悪い」ではなく、
“どんな頻度で、どんなふうに、どんな生活の中で食べるか”が大事、ということ。
誰でもつい飲みたくなるあのスープ。
でも、「今日は疲れてるから全部飲むのはやめておこう」とか、
「飲み会の帰りはラーメン我慢しようかな」といった、ちょっとした意識の工夫が、
将来の健康リスクを減らしてくれるかもしれません。
日本人だからこそ、響く研究でした
ラーメンのような、つい手が伸びてしまう身近な食べ物ほど、
「どのくらい、どう食べると、どんな影響があるのか」をきちんと検証することは意外と難しいものです。

今回の研究は、私たちの生活習慣のなかで起こる“小さな選択”が、長期的にどんな健康リスクと関わるかを、具体的に教えてくれました。
「どうやって楽しみながら付き合うか」を考えるきっかけをくれる、とても実用的で意義深い研究だったと思います。
素晴らしい研究をありがとうございました。
締めのひとこと
ラーメンも、健康も、どっちも大事にしたい。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。



コメント