
結論「フルマラソンは臓器に一時的な負担をかけますが、適切な準備とケアをすれば健康にプラスとなり、安全に楽しめることが最新研究で示されました」
この記事はこんな方におすすめ
✅マラソンやランニングの健康効果を知りたい人
✅つらすぎる「フルマラソンは体に悪いのでは?」と不安な人
✅指導者や医療従事者としてランナーを支える立場の人
✅健康づくりとしてジョギングを続けたい人
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:フルマラソン、めっちゃつらいけど健康に良いの?それとも悪いの?
🟡結果:練習は心臓や肺を鍛え、免疫や筋肉にもプラス。ただしレース直後は腎臓・消化管・免疫に一時的な異常が見られる。
🟢教訓:正しい準備とケアをすれば、マラソンのメリットはリスクを上回る。
🔵対象:過去の研究329件をまとめた最新レビュー論文

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
皆さんはマラソンをされますか?
わたしは以前よく走っていたのですが、膝を痛めてしまい、しばらく走るのをやめていました。
最近になって膝の調子が少しずつ戻ってきたので、短い距離からリハビリを兼ねてまた走り始めています。
「運動は体にいい」とよく言われますが、フルマラソンのように42kmという長い距離を一度に走り切ることは、本当に体にとって良いことなのでしょうか?
むしろ負担が大きすぎて、臓器や身体機能に悪影響はないのか――。
そんな素朴な疑問を持ったことがある方もいらっしゃるかと思います。
本日ご紹介するのは、イギリスの生理学・スポーツ医学系の学術誌に掲載された
「マラソン走の生理学と病態生理」というナラティブレビュー論文です。
この論文では、マラソンが私たちの身体にどんな影響を与えるのかを、心臓・筋肉・腎臓・免疫など幅広い角度から整理しています。
今回はその内容をもとに、マラソンと健康の関係について解説していきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Physiology and Pathophysiology of Marathon Running: A narrative Review”
(マラソン走の生理学と病態生理:ナラティブレビュー)
Sports Med Open. 2025 Jan 27;11(1):10.
PMID: 39871014 DOI: 10.1186/s40798-025-00810-3
掲載雑誌:Sports Medicine – Open【イギリス:IF 5.7(2024)】 2025年1月
研究の要旨
研究目的
マラソンが心臓・肺・腎臓・消化管・肝臓・血液・免疫・筋骨格・内分泌・中枢神経に与える「良い影響」と「悪い影響」を整理して一つにまとめること。
研究方法
ナラティブレビュー形式。PubMed・Scopus・Google Scholar から 1,021 件を抽出し、最終的に 329 件を採用(英語とドイツ語、マラソン関連の研究のみ)。検索は 2023 年11月まで。
研究結果
トレーニング段階では、心臓の構造変化や心血管リスクの改善、肺機能や腸の動きの向上、さらに骨・筋肉・血液・免疫・神経系にも良い影響が見られた。
一方でレース直後には、1〜3日の一過性のバイオマーカー変動が多く、急性腎障害(AKI)、消化器症状、けが、感染リスク上昇、ホルモン変化や睡眠障害なども確認された。
結論
マラソンは全体として安全であり、得られるメリットはリスクを上回る。アスリート、指導者、医療関係者にとって有用な知見となる。
考察
短期間に見られる「異常値」は多くがストレス反応で可逆的。ただし、まれに心臓突然死や急性肝不全のような重篤な事例もある。暑さ・脱水・過度の負荷・既往症の管理が重要。さらに、長期的影響、特に心臓と腎臓への作用については、今後の前向き研究が必要とされる。
研究の目的
本研究の目的は、フルマラソンという極限の持久運動が、
心臓・肺・腎臓・消化管・肝臓・血液・免疫・筋骨格・内分泌・神経といった全身のシステムにどのような
「良い影響」と「悪い影響」をもたらすのかを体系的に整理することにあります。
これまでマラソンの影響に関する報告は臓器ごとに散在していましたが、
それらを一つに統合し、健康上のリスクとベネフィットの両面から包括的に理解することを目的としています。
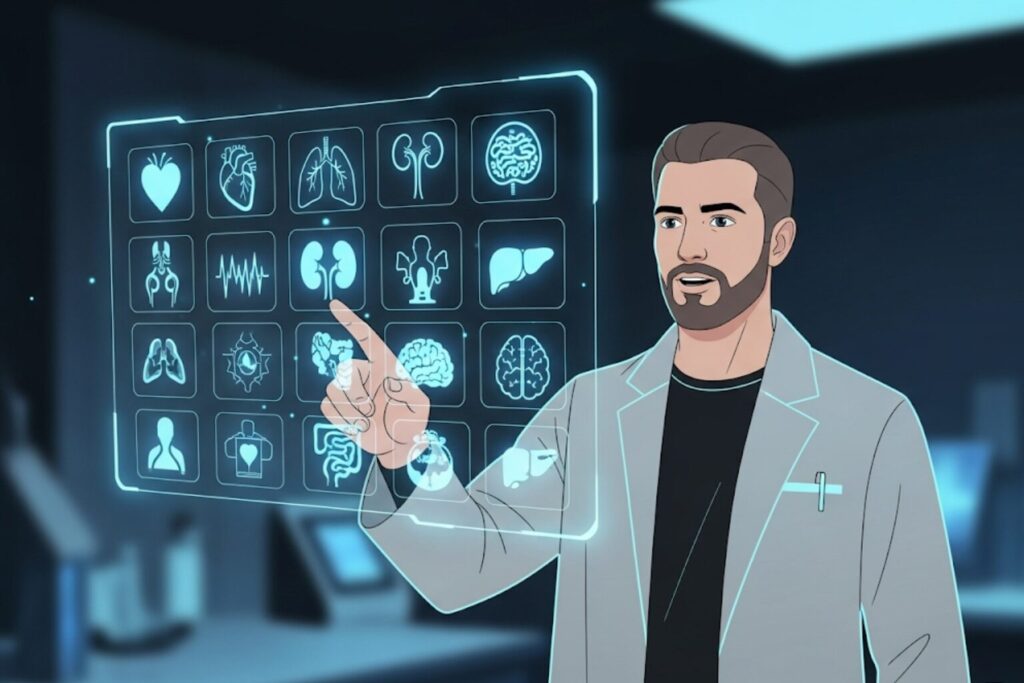
研究の対象者と背景
文献の範囲
この研究は、フルマラソンに関する既存の研究を対象にしています。
ハーフマラソンやウルトラマラソン、トレイルランニングなどは含まれていません。
ランニング以外のスポーツや短距離走も含まれていません。
採用された研究数
最初に検索された論文数:1,021件
最終的に採用された論文数:329件
言語と対象
英語とドイツ語で書かれた研究のみが対象となりました。

研究の手法と分析の概要
研究の種類
本研究は「ナラティブレビュー」という形式です。
これは研究者が既存の文献を整理・統合して解説する手法です。
ナラティブレビュー・システマティックレビュー・アンブレラレビューの違い
以前の記事にも登場したシステマティックレビュー・アンブレラレビューとの差異です。
◎ナラティブレビュー:
著者が分野全体を整理・解説するが、検索条件や評価基準は明確でない。主観が入りやすい。
👉例えるなら「詳しい人の解説記事」。
◎システマティックレビュー:
あらかじめ決めたルールに従い、文献を網羅的かつ客観的に収集・分析する。再現性が高い。
👉例えるなら「条件を決めて検索した調査報告」。
◎アンブレラレビュー:
すでに発表されたシステマティックレビューやメタ分析をさらにまとめ、分野全体のエビデンスを俯瞰する。
👉例えるなら「調査報告を束ねた総集編」。
データベース検索
利用したデータベースは以下の通りです。
・PubMed
・Scopus
・Google Scholar
検索は 2023年11月まで に公開された研究を対象に行われました。
選択と分析
・1,021件から重複や不適切なものを除外
・厳密にマラソン走に関連するものだけを精査し329件を採用
・各研究から得られた知見を、心臓・肺・腎臓・消化管などの臓器ごとに整理しました
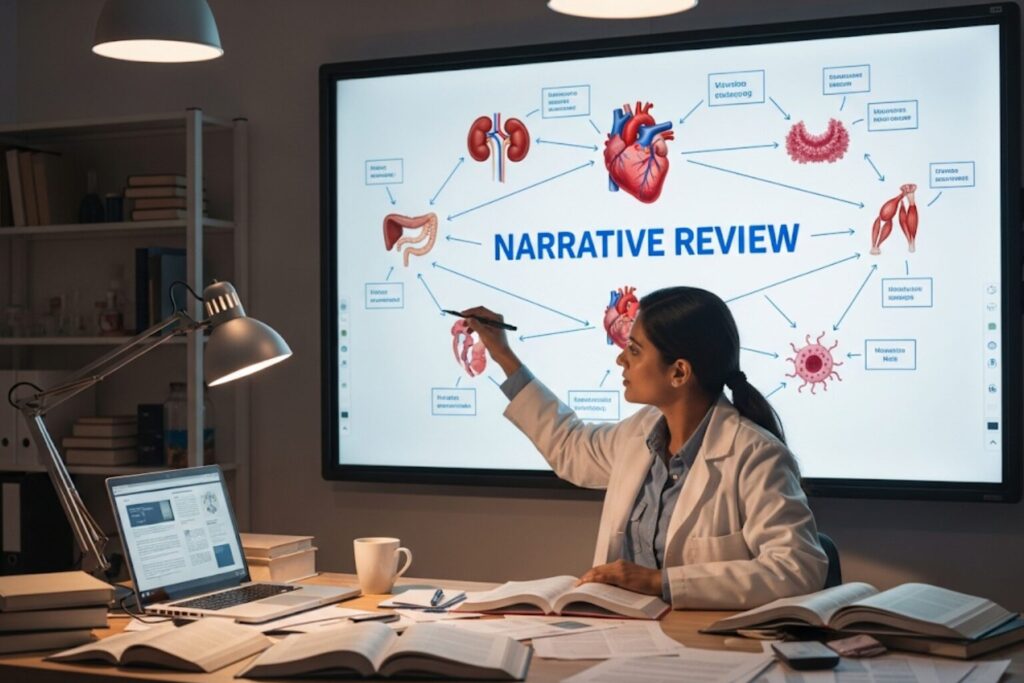
研究結果
トレーニングによる良い影響
マラソンの練習は体にさまざまなプラス効果をもたらします。
・心臓の構造が鍛えられ、心血管リスクが下がる
・肺機能が改善し、呼吸が効率的になる
・腸の動きがよくなり、消化も整う
・骨や筋肉が強化され、持久力が増す
・血液や免疫のバランスが安定
・神経系やホルモンの働きが調整される

レース直後に見られる変化
完走後には一時的な異常が多く現れます。多くは1〜3日で回復します。
・腎機能の低下(急性腎障害の兆候)
・下痢や吐き気などの消化器症状
・筋肉や関節のけが
・感染にかかりやすくなる(免疫低下)
・ホルモンの乱れや睡眠障害
・肝酵素の一過性上昇
・赤血球減少や鉄不足
・脱水や体温上昇による熱中症リスク
・集中力の低下や気分の変化
ランナー貧血(赤血球減少・鉄不足)
レース後には赤血球減少や鉄不足が生じることがあり、いわゆる「ランナー貧血」として知られています。女性ランナーや体格の小さい方に多く見られ、特に注意が必要です。

回復と長期的な影響
・多くの異常は数日〜数週間で自然に回復
・長期的には免疫や血液の安定化が見られる
・深刻な後遺症はごくまれ
個人差と環境の影響
・女性や体格の小さい人は、腎やホルモンの変化が出やすい傾向
・暑さや寒さといった環境条件でリスクは大きく変化
主な結果の整理(表)
| 影響の種類 | プラス効果(練習期) | マイナス効果(レース直後) |
| 心臓・血管 | 心構造の適応、リスク低下 | まれに突然死の報告あり |
| 肺・呼吸 | 機能改善 | 呼吸機能は概ね保たれる |
| 腎臓 | 血流効率化 | 一過性の腎障害(AKI) |
| 消化管 | 腸運動改善 | 下痢・嘔吐など |
| 骨・筋肉 | 強化、持久力向上 | けが・筋損傷 |
| 免疫 | バランス安定 | 感染リスク増加(短期) |
| 血液・造血系 | 循環改善 | 赤血球減少、鉄不足 |
| 肝臓 | 特記なし | 肝酵素値上昇 |
| 神経・ホルモン | 調整作用 | ホルモン変化、睡眠障害 |
| 中枢神経 | 調整作用 | 集中力低下、気分変化 |
| 体温調節 | 適応改善 | 熱中症・低体温リスク |

研究の結論
全体的な評価
フルマラソンは、多くの臓器に良い影響をもたらします。心臓や血管、肺、筋肉、免疫系の機能が改善し、健康維持や病気予防に役立ちます。
安全性について
レース直後には腎臓や消化管などに一時的な負担がかかりますが、多くは数日で回復します。重い合併症はまれであり、適切な準備と管理を行えば、マラソンは安全なスポーツといえます。
実用的な意義
マラソンの利点はリスクを大きく上回り、選手やコーチ、医療従事者にとって有用な知見が得られると結論づけられています。
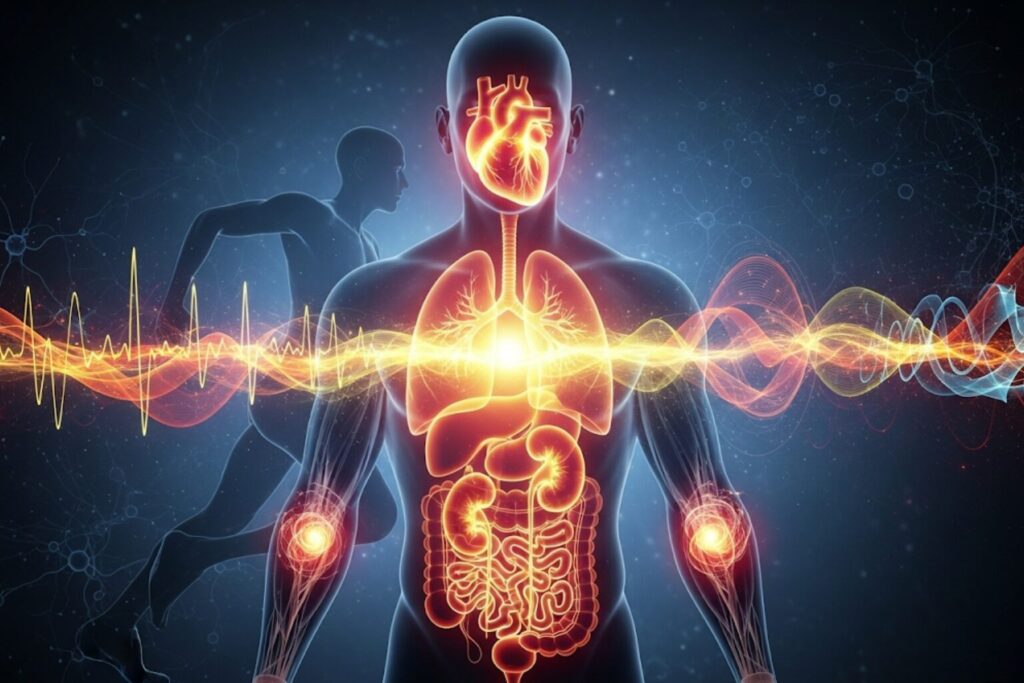
【礼次郎の考察とまとめ】
論文著者の考察
マラソンで観察される一過性の異常値は、多くが
「身体が強いストレスに適応しようとする反応」です。
腎臓の数値上昇や免疫の低下、肝酵素の変動などは、
レース直後の強い負荷に伴う一時的な現象であり、通常は数日で回復します。
ただし、熱中症や重度の脱水、既往歴のある心疾患などでは深刻なトラブルが起こり得ます。
そのため、過去の病歴や体調に応じた慎重な判断が欠かせません。
長期的な影響についてはまだ十分に明らかではなく、特に心臓や腎臓の負担については今後の研究が必要とされています。
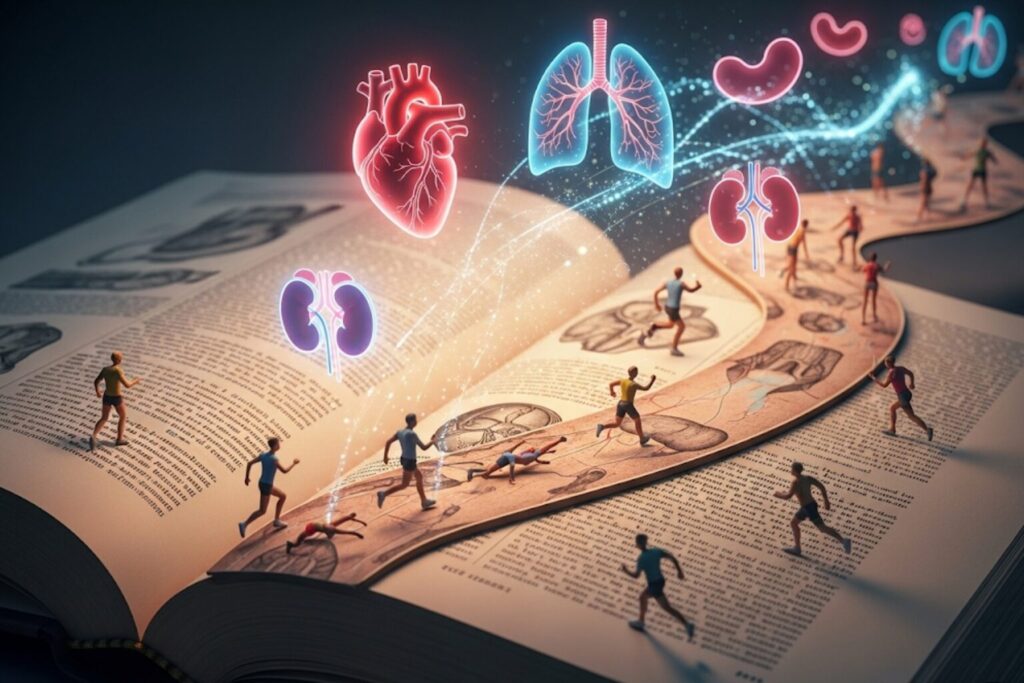
日常生活へのヒント
① 普段の練習は「体を強くする投資」
適度なランニング習慣は、心臓や血管を守り、筋肉や骨を丈夫にします。毎日でなくても、週に数回のジョギングでも十分に効果があります。
② レース前後のコンディション管理
レース前は睡眠と栄養をしっかりとり、体を整えて臨むことが大切です。
レース後は免疫が一時的に下がるため、人混みを避けたり、手洗い・うがいを丁寧にすると風邪予防につながります。
③ 水分と電解質のバランス
ただ水を飲むだけでなく、塩分やミネラルを含む飲料を取り入れることが熱中症対策になります。
特に夏場や汗を多くかく方は意識的に補給を心がけましょう。
④ ケガを防ぐセルフケア
走った後にストレッチやアイシングを行うことで、筋肉痛や関節への負担を軽減できます。
シューズ選びもケガ防止の大切な要素です。
⑤ 無理せず「休む勇気」を持つ
体調がすぐれない時や疲れが抜けない時に走り続けると、思わぬ不調につながります。
休むこともトレーニングの一部と考えるとよいでしょう。
⑥ 日常の生活習慣に活かす
マラソンで得られた学びは、普段の生活習慣にも応用できます。
例えば「規則正しい睡眠」「食事と水分のバランス」「適度な運動」などは、ランナーでなくても健康維持に役立ちます。

つまりマラソンは、正しい準備とケアをすれば健康を底上げする最高の習慣になります。
一方で、無理や油断はリスクにつながるため、自分の体と対話しながら取り組むことが重要です。
もちろん、今回の結果はフルマラソン参加者だけでなく、ハーフマラソンや10kmラン、さらには日常のジョギングやウォーキングを楽しむ方々にも十分あてはまる内容だと思います。
みなさんも運動の際には、今回ご紹介したヒントを意識することで、より安全で楽しい「走る生活」につなげていただければ嬉しいです。
締めのひとこと
ゴールより大事なのは安全です
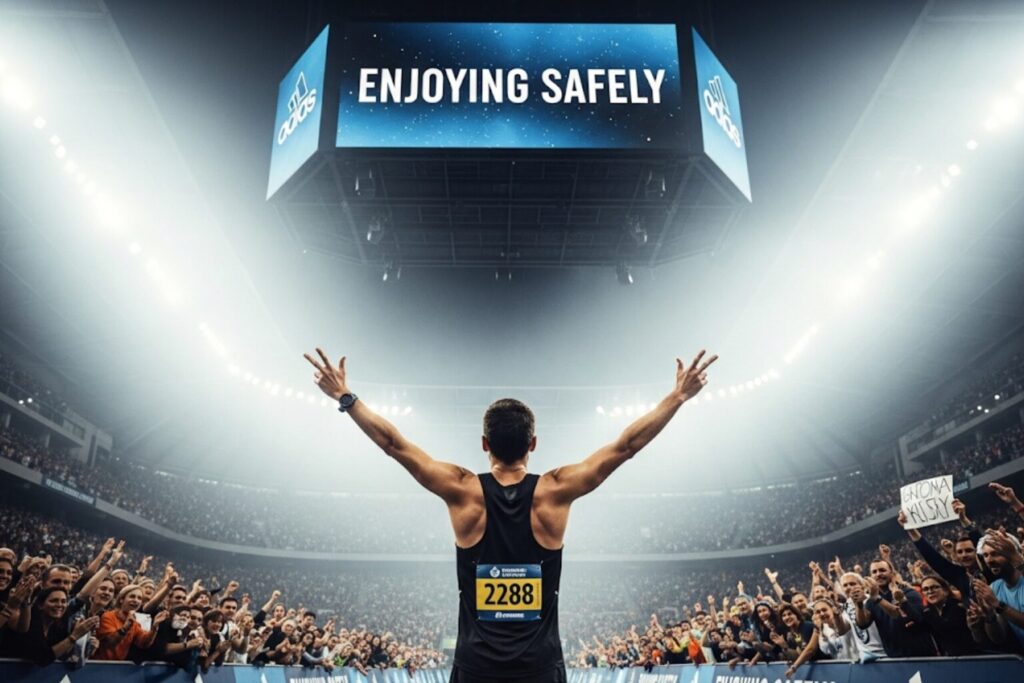
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント