
結論「コップ1杯弱の緑茶を飲むだけで、集中力が高まり“時間を忘れるほどの没頭感”を得られる可能性があると最新研究で示されました」
この記事はこんな方におすすめ
✅勉強や仕事にもっとスムーズに集中したい人
✅コーヒーは苦手だけどカフェインの力を借りたい人
✅1日の中で「メリハリをつけたい」と思っている人
✅作業が長く感じて疲れやすいと感じている人
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:集中力が続かない。短時間でも“夢中”になれる方法は?
🟡結果:緑茶を1杯弱(210mL)飲むと、眠気や疲労が抑えられ、フロー感(没頭感)が有意に上昇。作業時間も短く感じられた。
🟢教訓:たった一杯の緑茶が「自然に集中できる環境」を作ってくれる。
🔵対象:18〜26歳の健康な日本人男性を対象にした研究。
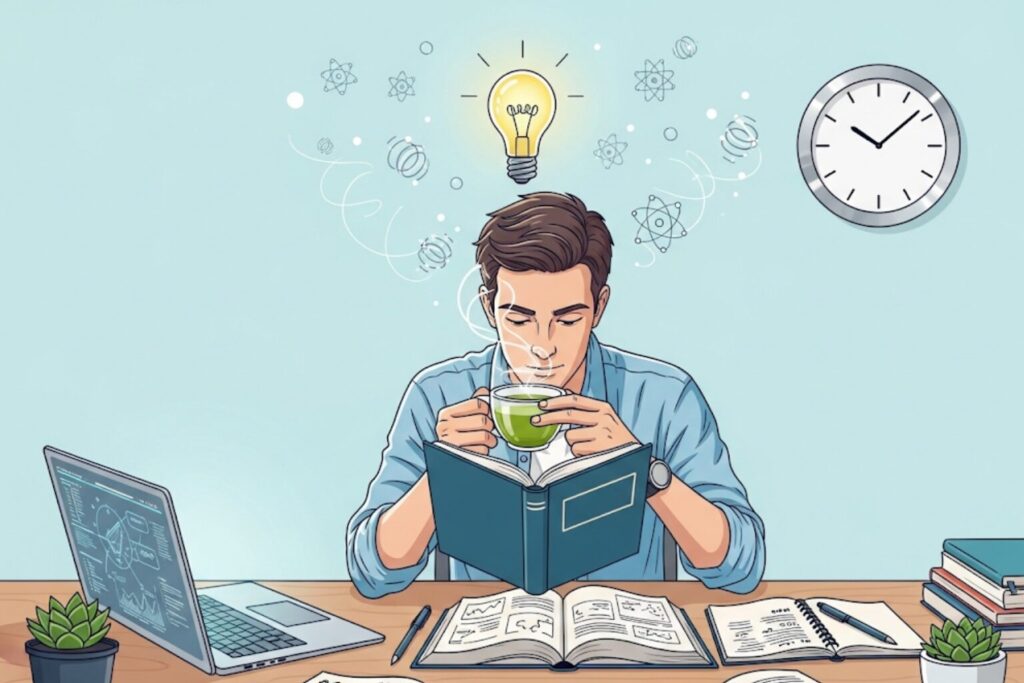
※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
普段、勉強や仕事にどれくらい集中できていますか?
2時間、3時間と夢中になって作業が進むと、とても気持ちがいいですよね。
わたし自身も毎日ブログ記事を書くのにかなりの時間を使うので、「集中」は欠かせない要素です。
でも人間ですから、集中が途切れることもあります。
作業中についSNSやネットニュースを見てしまい、「あれ、全然進んでないじゃん!」と焦ってしまう日もあります。
毎日同じように集中できれば効率はぐんと上がるのに…そう思ったこと、きっと皆さんもあるのではないでしょうか。
今回ご紹介するのは、そんな悩みに関わる研究です。
アメリカのオープンアクセス学術誌 PLOS ONE に掲載された最新の論文で、
「少量の緑茶が短時間の作業でも集中力と“没頭感(フロー状態)”を高める」 ことが示されました。
この研究は、日本の研究者が日本人を対象に行ったものですので、私たちの生活にそのまま応用できる可能性があります。
実は、前回の記事に続いて今回も「お茶」に関するテーマです!
それでは一緒に、この研究の内容をわかりやすく解読していきましょう。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Green tea consumption rapidly enhances cognitive performance and flow state during mental tasks in healthy young adults”
(緑茶の摂取は、健常な若年成人の知的課題中に認知パフォーマンスとフロー状態を短時間で高める)
PLoS One. 2025 Jul 10;20(7):e0328394.
PMID: 40638646 DOI: 10.1371/journal.pone.0328394
掲載雑誌:PLOS ONE【アメリカ:IF 2.6(2024)】 2024年7月
研究の要旨
研究目的
緑茶を少量飲むことで、短時間の作業中の集中力や没頭感に影響があるかを調べた。
研究方法
18〜26歳の健康な男性22名が、何も飲まない・水・緑茶の3条件で課題に取り組んだ。
研究結果
課題の正解率は差がなかったが、緑茶を飲んだ場合に眠気が抑えられ、没頭感が高まり、作業時間を短く感じた。
結論
少量の緑茶でも、集中を維持し、疲労や眠気を軽減しながら作業の没頭感を高める可能性がある。
考察
ただし対象は若い男性に限られており、今後は女性や幅広い年齢層での検証が必要である。
研究の目的
この研究の目的は、
日常的に親しまれている緑茶を少量飲むだけで、短時間の作業に集中しやすくなるのかを明らかにすることです。
緑茶にはカフェインやテアニンといった成分が含まれ、従来から「覚醒作用」や「リラックス効果」が報告されてきました。
しかし、「少量を飲んだ直後に、実際の作業中の集中や没頭感にどのような変化が生じるか」は、これまで十分に調べられていませんでした。
そこで研究者たちは、暗算や数字探しといった短時間の課題を用い、緑茶の摂取が集中力・疲労感・フロー状態に即時的な効果をもたらすのかを検証することにしました。

研究の対象者と背景
参加者について
この研究には、日本人の健康な男性22名(18〜26歳)が参加しました。

背景
若年層は体調や生活習慣のばらつきが少ないため、飲み物による集中力や疲労感の違いを観察しやすいと考えられています。
研究者について
この研究は、日本の研究者グループ(東京農業大学ほか) によって行われました。
そのため、参加者も同じく日本国内の大学生や若者が中心でした。
注意点
対象が日本人男性に限られているため、女性や年齢の高い人、また海外の人にも同じ結果が当てはまるかどうかは不明です。今後の研究で検証が必要です。

研究の手法と分析の概要
研究デザイン
この研究は介入研究であり、研究者が条件を設定して、効果の違いを比べる方法がとられました。
条件の設定
参加者は同じ日に、以下の3条件で課題に取り組みました。
1.何も飲まない(NONE)
2.水を飲む(WATER)
3.緑茶を飲む(TEA)
飲む量
水と緑茶は 70mLを3回に分けて合計210mL 摂取しました。これはちょうどコップ1杯弱の量です。
摂取のタイミングは、
・1回目:課題開始前
・2回目:暗算課題の前
・3回目:数字探索課題の前
という流れで、作業中には飲まず、直前に少しずつ飲む形でした。
あえて少しずつ飲む形にしたのは、のどの渇きや一気飲みの影響を排除し、実生活に近い条件を再現するためです。
さらに、飲料の温度は 室温(25±1℃) に統一されていました。冷たすぎたり熱すぎたりすると集中に影響する可能性があるため、温度の要因を排除する工夫がされています。

実施した課題
各条件のあとに、
・暗算(短時間の計算問題)
・数字探索(たくさんの数字から指定の数字を探す課題)
をそれぞれ5分間ずつ行いました。
これらの課題は、短時間でも集中力や注意力を測ることができ、しかも私たちの日常的な勉強や仕事に近い作業です。
そのため、緑茶を飲んだ直後に起こる変化を観察するのに適しているのです。
測定した項目
課題の前後や終了後に、「疲労感」「作業の負担感」「フロー感」「時間の感じ方」の感覚を
「主観的アンケート」や「チェックリスト」を用いて数値化(スコア化)して効果が比較されました。
疲労感(どれくらい疲れを感じたか)
SFF(Subjective Feeling of Fatigue) という質問票を使いました。
「どのくらい疲れたか?」を5段階で自己評価し、数値に変換しています。
作業の負担感(どれくらいしんどかったか)
NASA-TLX(タスク負担指数) という国際的によく使われる評価法を採用。
「作業がどれくらい大変に感じたか」をいくつかの要素に分けて点数化します。
フロー感(どれくらい夢中になれたか)
FEC(Flow Experience Checklist) というチェックリストを使用。
「作業に夢中になれたか」「時間を忘れる感覚があったか」などの質問に答え、合計スコアを算出します。
時間の感じ方(長く感じたか、短く感じたか)
DJR(Duration Judgment Ratio) を使いました。
「実際は5分だったけれど、どのくらいの長さに感じたか」を自己申告させ、実際の時間と比率を取ることで「短く感じた or 長く感じた」を数値化しました。

研究結果
主な発見
緑茶を飲んだグループでは、
眠気の増加が抑えられ、さらにフロー感(没頭感)が有意に高まりました。
また、作業時間を「実際より短く感じる」効果も確認されました。
正答率と処理スピード
課題の正解率は、どの条件でもほぼ100%に近く、大きな差は見られませんでした。
これは「天井効果」と呼ばれ、もともと正解率が非常に高いため違いが出にくかったと考えられます。
ただし暗算課題では、緑茶を飲んだ場合に反応時間が短くなり、解答回数が増える傾向がありました。
つまり「間違いは減らないけれど、同じ時間でより多く解答できる=処理効率が上がる」可能性があります。
疲労感と眠気
何も飲まない条件や水を飲んだ条件では、課題を終えた後に疲労感や眠気が強まりました。
一方で緑茶を飲んだときには、疲労感の上昇が抑えられ、眠気の増加も軽減されました。
これは作業を続けやすくする効果につながると考えられます。
作業の負担感
作業のしんどさを評価するスコア(NASA-TLX)では、大きな差は認められませんでした。
つまり緑茶を飲んでも、「作業が特別に楽になった」とまでは言えません。
しかし少なくとも負担感が悪化することはなく、安定していたと解釈できます。
時間の感じ方
緑茶を飲んだときには、同じ5分間の課題が「短く感じられる」傾向がありました。
これは「フロー状態」に近い感覚で、夢中になったことで時間を忘れてしまう体験に通じています。
結果まとめ
| 評価項目 | 緑茶を飲んだ場合の変化 | 意味すること |
| 正答率 | 差なし | 間違いは増えていない |
| 暗算のスピード | 反応時間短縮・解答回数増加 | 処理効率が向上 |
| フロー感 | 有意に上昇 | 作業に夢中になれる |
| 疲労感 | 上昇が抑制 | 疲れにくい |
| 眠気 | 増加が抑制 | 集中が途切れにくい |
| 作業負担感 | 大きな差なし | 作業のしんどさは変わらない |
| 時間感覚 | 短く感じる | 没頭していた証拠 |
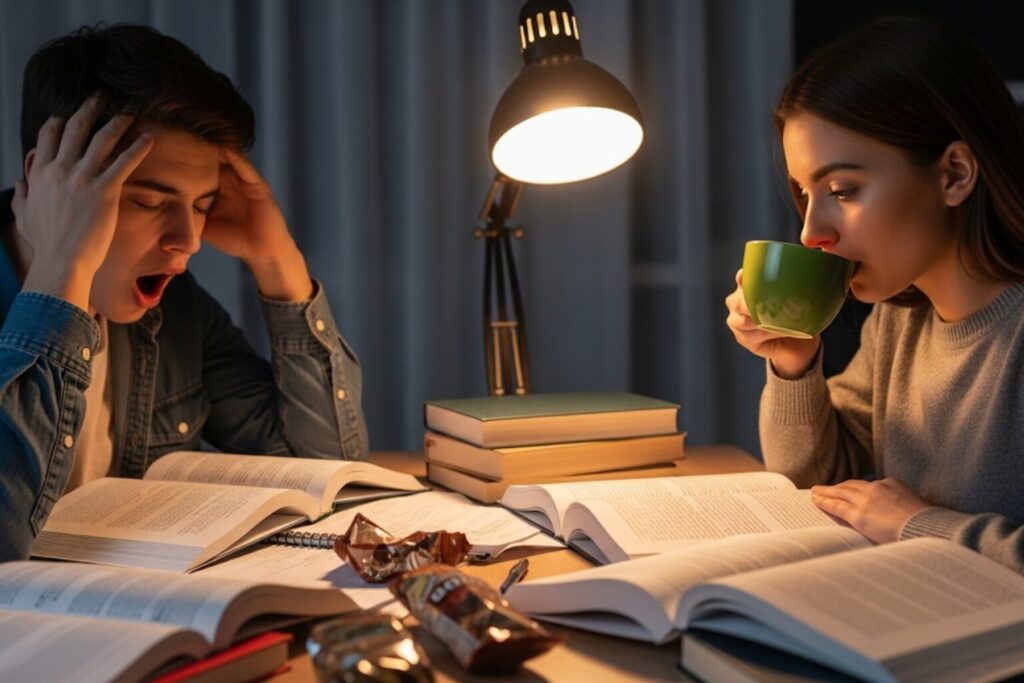
研究の結論
少量の緑茶が集中力と没頭感を高める
今回の研究では、
✅️コップ1杯弱(210mL)の緑茶を課題直前に飲むことで、集中力が高まり、作業に没頭しやすくなることが示されました。
眠気と疲労感を抑制
✅️緑茶を飲んだ場合、眠気の上昇が抑えられ、作業による疲労感も悪化しにくいことが確認されました。
認知課題そのものの正解率は大きく変化なし
計算や数字探しの「正解率」に大きな差は出ませんでしたが、
✅️反応時間の短縮やレスポンス数の増加といった改善の傾向が見られました。
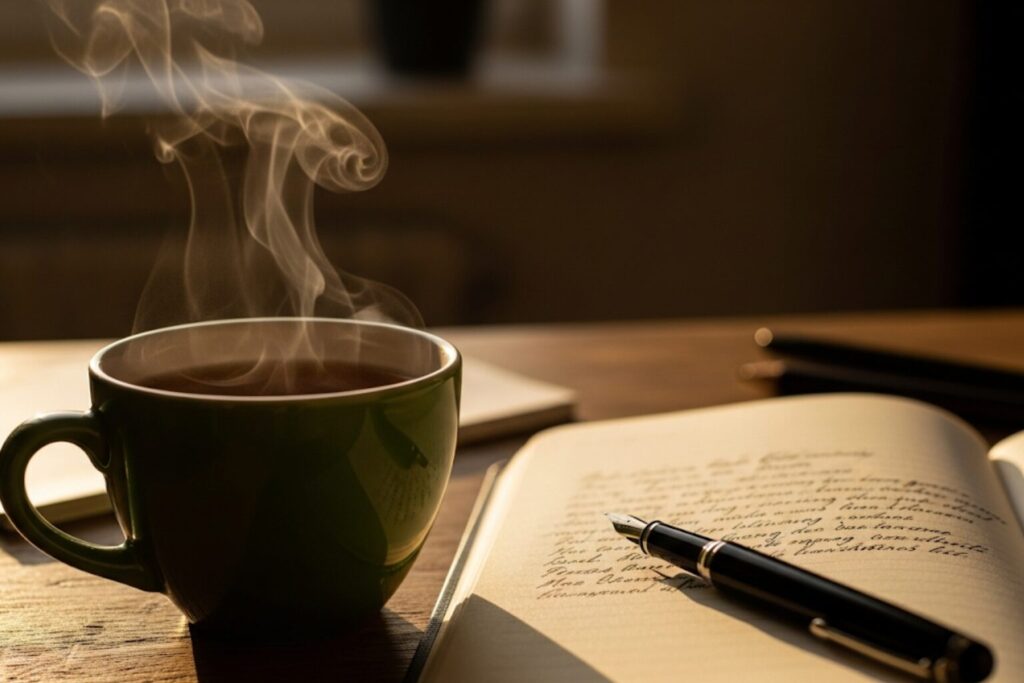
【礼次郎の考察とまとめ】
論文著者の考察
研究者らは、緑茶に含まれる カフェインとテアニン の組み合わせが、今回の結果に関与していると指摘しています。
・カフェインは眠気を抑えて覚醒を促す作用がある
・テアニンはリラックスを助け、ストレスを和らげる効果がある
✅️この二つが同時に働くことで「緊張しすぎず、適度に集中できる状態」が作られ、フロー感の向上につながったのではないかと考えられています。
また、飲んだ量が少なかったにもかかわらず効果が確認された点は重要です。
日常生活で取り入れやすい条件で結果が出ているため、実用性が高いといえます。

日常生活へのヒント
この結果からわかるのは、集中したい作業の前に少量の緑茶を飲むことが効果的かもしれないということです。
たとえば、
・勉強を始める前に小さなカップで緑茶を一杯
・会議や資料作成の前に湯のみ1杯の緑茶で気持ちを切り替える
といった習慣が「自然な集中モード」を作るサポートになりそうです。
ただし、この研究は 若い日本人男性のみ を対象としているため、女性や年齢が高い方、また海外の人々にも同じ効果があるかは今後の研究が必要です。

おまけ:実生活に役立つ・自分専用AIプロンプト
今回もご用意していません
本当はここで「AIプロンプト」を紹介する予定だったのですが……今日も断念しました。
理由はとてもシンプルで、この研究が伝えていること自体がすでに十分シンプルだったからです。
「緑茶をちょっと取り入れるだけで集中や没頭感が高まる」
——それ以上でも、それ以下でもありません。
無理にAIを使って複雑に仕立てるより、このまま素直に受け止めて実践するのが一番だと思いました。
結果として3日続いて“プロンプトなし”になってしまいましたが、これはむしろ朗報かもしれません。
だって、特別なツールや準備がいらず、誰でもすぐに試せるのですから。
締めのひとこと
緑茶ではじまる“没頭体験”
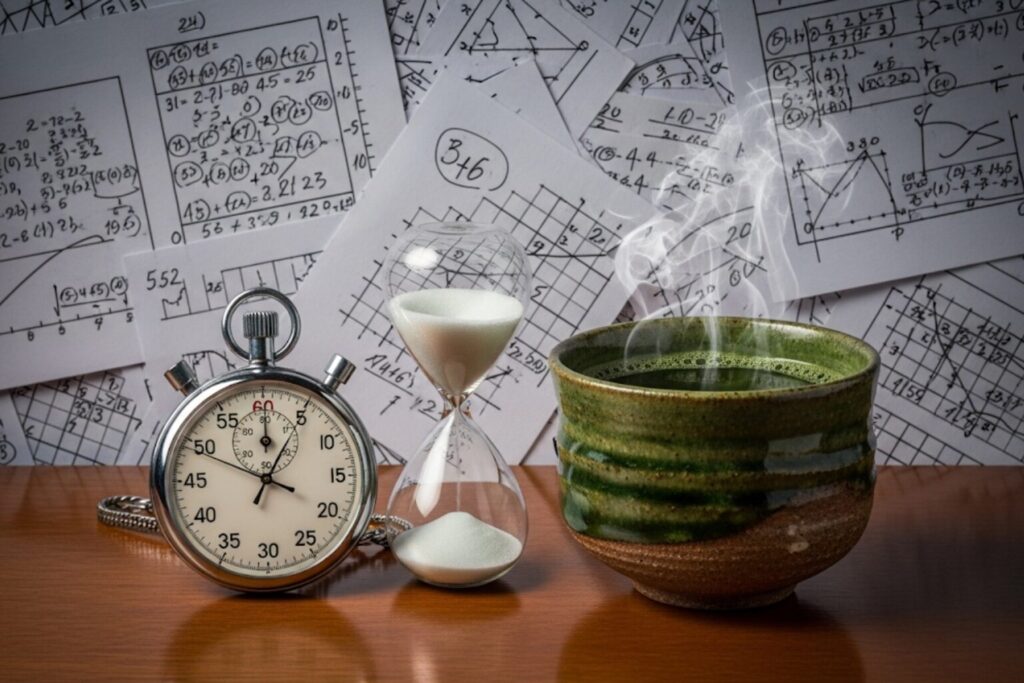
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント