
結論「抹茶うがいを1か月続けると、歯周病菌が有意に減少しました。しかも善玉菌は守られ、安全性も確認されています」
この記事はこんな方におすすめ
✅歯周病が気になる方、口臭や歯ぐきの腫れに悩んでいる方
✅歯磨きだけで大丈夫か不安な方
✅手軽で安全なオーラルケアを取り入れたい方
✅緑茶・抹茶の健康効果に興味がある方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:自分で手軽にできる歯周病ケアってある?
🟡結果:抹茶うがいで歯周病菌(P. gingivalis)が有意に減少。善玉菌は保たれ、副作用なし。
🟢教訓:歯磨き習慣に抹茶をプラスするだけで、手軽に口腔環境を改善できる可能性あり。
🔵対象:日本人歯周病患者45人を対象とした臨床試験。日常生活にも応用可能。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。
すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。
あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、きちんとオーラルケアしていますか?
私は外科医なのですが、日常診療の中で「口の中の小さなトラブル」が思わぬ全身の感染症につながる場面によく出会います。
虫歯や歯周病が原因で、最終的には外科手術が必要になるようなケースも多々あるのです。
「歯は一生もの」とよく言いますが、
忙しい毎日ではなかなか理想的にケアできませんよね。
私自身も、仕事で疲れて毎食の歯磨きをサボってしまったり、
酔っ払ってそのまま寝てしまった…なんてことが、正直あります。
(ほんとにたまにですよ、笑)
今回はそんな「侮れない口腔ケア」のテーマとして、
歯周病と抹茶の関係を調べた最新の研究をご紹介します。
しかも、この研究は日本人研究者によるものなので、私たちにとっても身近で実用的な内容です。
私は医科なので歯科の専門論文を読むのは初めてですが、
専門用語をかみ砕きながら、一緒に分かりやすく読み解いていきましょう。
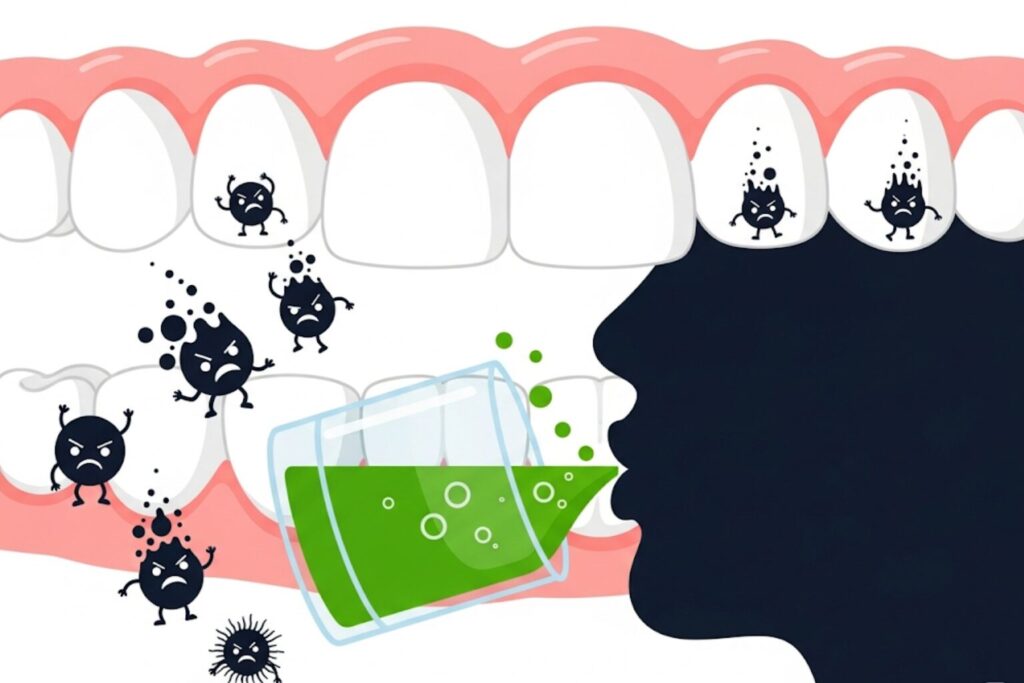
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

※本記事は、PubMed掲載の査読付き論文をもとに、現役医師が一次情報をわかりやすく解説しています。
以下に出典を明示し、信頼性の高い医療情報をお届けします。
今回読んだ論文
“Multimodal inhibitory effect of matcha on Porphyromonas gingivalis“
(抹茶によるPorphyromonas gingivalisへの多面的な阻害効果)
Microbiol Spectr. 2024 Jul 2;12(7):e0342623.
PMID: 38771061 DOI: 10.1128/spectrum.03426-23
掲載雑誌:Microbiology Spectrum【アメリカ:IF 3.8(2024)】 2024年7月
研究の要旨
研究目的
抹茶が歯周病菌 P. gingivalis を抑えられるか、臨床的にも役立つかを検証。
研究方法
試験管内で複数菌種に対する作用を調べ、さらに歯周病患者45人を対象に「抹茶うがい」vs「大麦茶・アズレン」で1か月比較。
研究結果
抹茶は悪玉菌(P. gingivalis など)を選択的に抑制し、臨床試験でも唾液中の菌数が有意に減少。善玉菌は保たれた。
結論
抹茶は多方面から歯周病菌を抑える作用があり、補助療法として有望。
考察
抹茶は日本人に取り入れやすいが、より大規模で長期の臨床研究が必要。
研究の目的
歯周病は「サイレントディジーズ(静かな病気)」とも呼ばれ、気づかないうちに進行し、最終的には歯を失う原因になるといわれています。
その主要な原因菌のひとつが Porphyromonas gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)です。
これまでに、緑茶や抹茶の成分が抗菌作用を持つことは知られていましたが、
実際に「抹茶そのもの」を水に溶かしてうがいに使ったときに効果があるかどうかは、科学的に証明されていませんでした。
そこでこの研究では、
抹茶を用いた含嗽(うがい)が口の中のP. gingivalisの菌数を減らせるのかどうか
を、臨床的に確かめることを目的としました。
Porphyromonas gingivalisとは?
P. gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)は、歯周病の代表的な原因菌で「悪玉菌」と呼ばれています。
歯ぐきの奥深くに潜み、バイオフィルムを作ってしぶとく増殖します。
この菌は炎症を悪化させる酵素や毒素を分泌し、歯ぐきや歯を支える骨をじわじわと壊していきます。
さらに近年では、心筋梗塞や認知症といった全身疾患との関連も指摘されており、口の中だけにとどまらない“厄介者”です。
研究の対象者と背景
対象者
この研究には、日本国内の大学病院に通院する慢性歯周病の患者45人が参加しました。

背景
歯周病は世界的に広くみられる病気ですが、特に日本では40歳以上の約8割がかかっているといわれています。
今回の研究は日本人患者を対象として行われたため、私たち日本人にとっても直接的に参考になるデータです。
ただし参加者数が45人と少なく、観察期間も1か月と短いため、今後は大規模で長期の研究が必要とされています。
リアルな生活習慣のまま試した研究
ふだんの歯磨き+抹茶うがい
この研究では歯磨きの回数や歯磨き粉の種類までは統一していませんでした。
つまり、普通に自分のやり方で歯磨きをしていた人たちに“抹茶うがい”を加えたらどうなるかを見た研究です。
だからこそ、日常生活にそのまま応用できる可能性があると考えられます。

研究の手法と分析の概要
デザイン
この研究は介入研究(ランダム化比較試験)として行われました。
患者はランダムに3つのグループに分けられています。
グループ分け
・抹茶群:抹茶粉末 2g を滅菌水60mLに溶かし、1日2回うがい
・大麦茶群:市販の大麦茶を規定の方法で抽出して使用
・アズレン群:市販のアズレン含嗽薬を規定濃度に希釈して使用
期間
うがいを続けた期間は1か月です。
評価方法
・唾液中の歯周病菌数をDNA解析(qPCR)で測定
・歯ぐきの状態(歯周ポケットの深さ)も臨床的に評価
qPCR
qPCRは「菌の量を正確に測るための方法」です。
やっていることをすごくかんたんに言うと、菌が持っている設計図(DNA)をコピーして、そのコピーの数を数えることで「菌がどれくらいいるか」を調べています。
・コピーがたくさん作られる → 菌がたくさんいた証拠。
・コピーが少ない → 菌が減っている証拠。
つまり、論文で「qPCRで菌数を調べた」とあるときは、
「口の中にいる菌を目に見えないレベルで数えたんだな」と理解すれば十分です。

研究結果
抹茶うがいで悪玉菌が減少
1か月の試験で、
抹茶うがいをしたグループだけが歯周病の原因菌(P. gingivalis)を有意に減少させました。
さらに、試験管での検証では、抹茶は菌の増殖を抑えるだけでなく、
菌が集まって塊を作る「バイオフィルム形成」や、菌が分泌する酵素の働きも阻害することが示されました。
一方、大麦茶やアズレンを使ったグループでは菌数の変化は小さく、有意な改善は認められませんでした。
歯ぐきの状態と出血の変化
抹茶群では歯周ポケットの深さや出血が少し減る傾向を示しました。
さらに、炎症に関わる分子の働きが抑えられる可能性も示唆され、単なる菌数の減少以上に「歯ぐきの炎症そのもの」に働きかける効果が期待されます。

善玉菌への影響は少ない
抹茶は悪玉菌を抑えつつ、善玉菌(口の常在菌)には大きな影響を与えませんでした。
これは「菌を全部やっつける」のではなく、バランスを保ちながら悪玉菌を選んで減らすという理想的な作用です。
安全性
抹茶うがいを1か月続けても、副作用や体調不良は報告されませんでした。
食品由来という安心感も含めて、安全性は高いと考えられます。
結果のまとめ
| 評価項目 | 抹茶群 | 大麦茶群 | アズレン群 |
| 歯周病菌(P.g.) | 有意に減少 | 変化なし | わずかに減少 |
| 歯周ポケット深さ | 改善傾向(有意差なし) | 変化なし | 変化なし |
| 出血のしやすさ | 減少傾向(有意差なし) | 変化なし | 変化なし |
| 善玉菌への影響 | ほとんど影響なし(温存された) | 変化なし | 変化なし |
| 副作用 | 報告なし | 報告なし | 報告なし |

研究の結論
抹茶うがいで歯周病菌が減少
今回の研究では、
✅️通常の歯磨きに加えて「抹茶でのうがい」を行ったグループで、歯周病の原因菌である Porphyromonas gingivalis が有意に減少しました。
これは抹茶の成分が菌の増殖や活性を抑える働きを持つことを示しています。
安全性も確認された
抹茶うがいを続けても口の粘膜や歯ぐきに悪影響はなく、安全に取り入れられる方法であることも示されました。
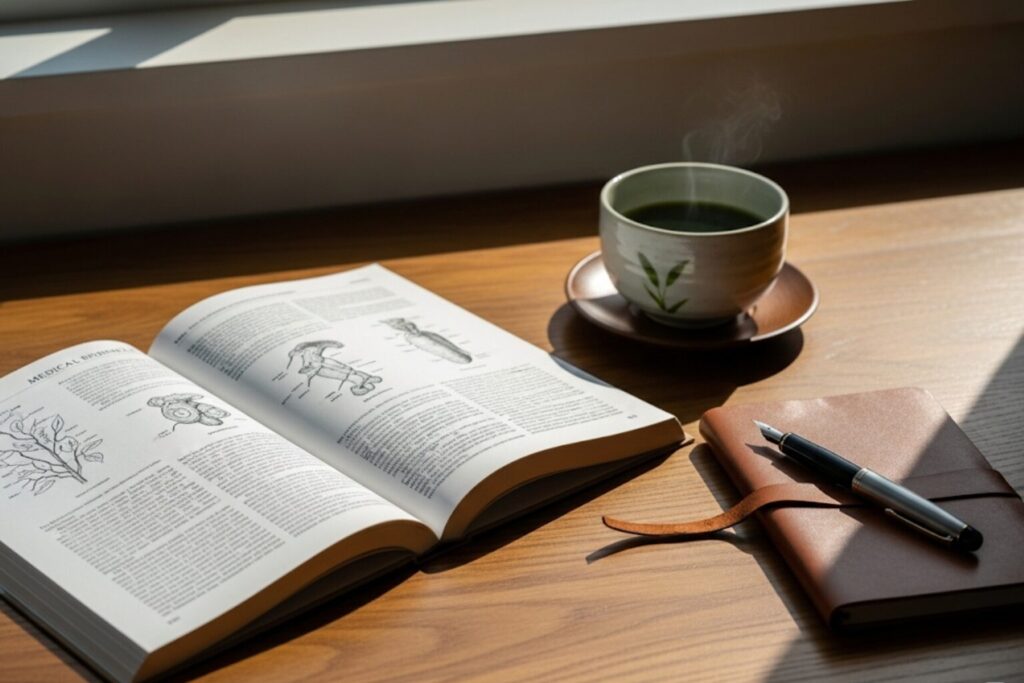
【礼次郎の考察とまとめ】
なぜ抹茶で効果があったのか(論文著者の考察)
研究者によると、
抹茶にはカテキンやクロロフィルなど多くの有効成分が含まれています。
特に抹茶は茶葉をそのまま粉末で摂取するため、緑茶の抽出液に比べて濃度の高い成分を直接取り入れることができます。
そのため、菌の数を減らすだけでなく、菌が集まって塊を作るのを防いだり、膜の性質に影響を与えるなど、多面的に働いた可能性が指摘されています。

抹茶と緑茶の違い
論文では緑茶について直接の比較は行われていません。しかし、普段わたしたちがコンビニや自販機でよく飲むのは緑茶飲料です。
緑茶は「葉を抽出した液」を飲むのに対し、抹茶は「葉を丸ごと粉末にして摂取」します。
手軽に手に入る抹茶飲料は一部に限られ、若干高価になる傾向もあります。
一般論としては、緑茶にもカテキンが含まれているため一定の効果は期待できますが、抹茶ほど濃度は高くありません。
イメージとしては「緑茶=ベース」「抹茶=その強化版」と考えるとわかりやすいでしょう。
日常生活へのヒント
この研究から私たちが学べるのは、
「ふだんの歯磨き習慣に抹茶を加えるだけで、悪玉菌を抑える可能性がある」
という点です。
忙しくて歯磨きが不十分なときでも、抹茶を飲んだり、うがいに取り入れたりすることでプラスの効果が期待できるかもしれません。
もちろん、抹茶で歯周病が治るわけではなく、あくまで補助的なケアです。
それでも、日本人にとってなじみのある抹茶が「口の健康を守る味方」になりうるのは心強いことです。
抹茶うがい後のすすぎについて
この研究では「抹茶でうがいをしたあとに水ですすぐかどうか」については明記されていませんでした。
研究の目的は「口の中にとどまった抹茶成分の抗菌作用」を調べることなので、おそらく水ですすがずに終えていた可能性が高いと考えられます。
日常生活で取り入れる場合は、飲み込む必要はなく、
あくまで「うがい」として利用し、抹茶の成分をしっかり残したいならそのまま終えるのが効果的かもしれません。
ただし、歯の着色が気になる方は軽く水でゆすいでもよいでしょう。

おまけ:実生活に役立つ・自分専用AIプロンプト
今回もご用意していません
ここで「AIプロンプト」を紹介する予定でしたが……断念しました(笑)
なぜなら、この研究のメッセージは極めてシンプルで、
「抹茶を生活に取り入れるだけで効果が期待できる」
という明快なものだったからです。
プロンプトを作っても“回りくどい”説明になりそうで、逆に不自然だなと感じました。
シンプル・イズ・ベスト、ですね。
ごめんなさい
締めのひとこと
お口の健康に、抹茶で一服

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント