
結論「週3回以上の“ピリ辛習慣”が、心筋梗塞や脳卒中のリスクを少しだけ下げてくれるかもしれません。」
この記事はこんな方におすすめ
✅辛いものが好きだけど、健康への影響がちょっと気になる方
✅心筋梗塞や脳卒中のリスクを少しでも下げたいと考えている方
✅信頼できるデータに基づいた“日々の食事改善ヒント”を知りたい方
✅唐辛子や香辛料をもっと上手に生活に取り入れたいと思っている方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:辛いものって本当に健康にいいの?
🟡結果:中国の48万人を対象にした12年の追跡調査で、週に3回以上辛い料理を食べる人は、心筋梗塞リスクが約8%、脳卒中リスクも約5〜6%低下していました。
🟢教訓:唐辛子に含まれるカプサイシンには、血管拡張や抗炎症作用の可能性あり。適度な“ピリ辛習慣”は血管の健康にプラスかも。
🔵対象:中国国内の30〜79歳の健康な男女。日本人にも類似の傾向が期待されます。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
わたし、けっこう辛いものが好きでして、
四川料理や激辛ラーメンでもわりと平気で食べちゃいます。
パスタやピザにはタバスコより辛い“スコーピオンソース”、
うどんやそばにも七味唐辛子をたっぷり…。
子どもの頃から「辛いものは代謝が上がって体にいい」ってよく聞きましたが、
それって本当なのか、ちょっと都市伝説っぽくないですか?
食べているときは平気でも、翌日のお通じで「おしりがヒリヒリ…」なんて経験、ありますよね(笑)
そんなとき、「本当に体にいいのかなあ」と不安に思いながらも、ついつい辛さがやめられない…。
そんなモヤモヤを、実は中国の研究者たちも感じていたようで、
なんと48万人という超大規模な調査で「辛い食べ物と血管の病気」との関係を調べてくれたんです。
今回は、中国の権威ある医学雑誌『Chinese Medical Journal(中国医学雑誌)』に掲載されたこの研究をもとに、
「辛い食べ物って、体にいいの?悪いの?」
というテーマに迫っていきます!
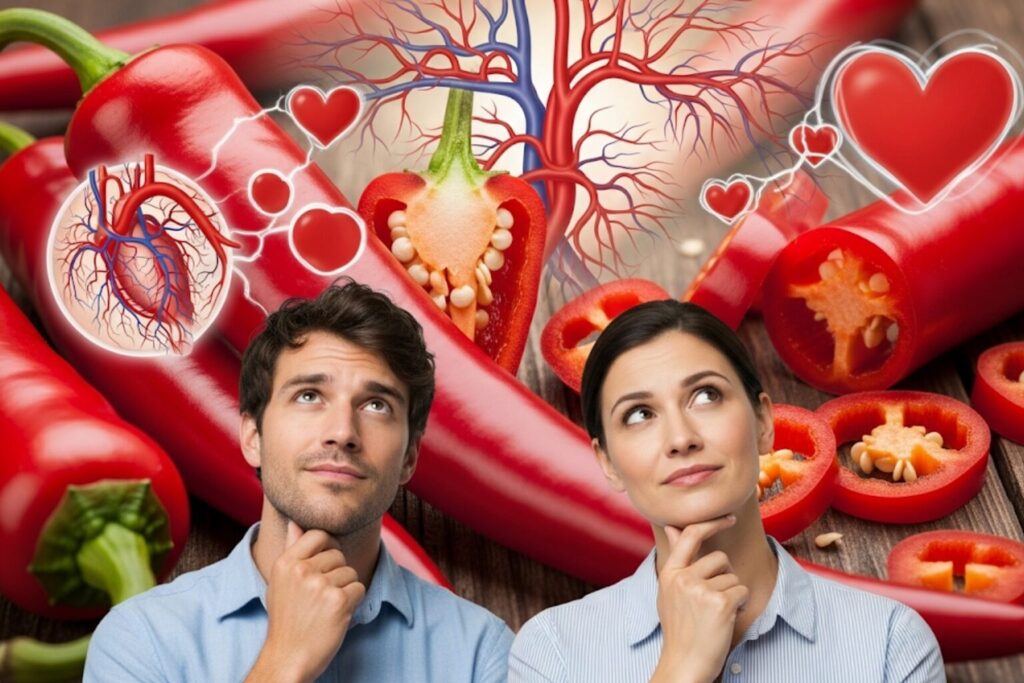
自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Spicy food consumption and risk of vascular disease: Evidence from a large-scale Chinese prospective cohort of 0.5 million people”
(香辛料の摂取と血管疾患リスクとの関連:中国50万人規模の前向きコホート研究からのエビデンス)
Chin Med J (Engl). 2025 Jul 20;138(14):1696-1704.
PMID: 39030074 DOI: 10.1097/CM9.0000000000003177
掲載雑誌:Chinese Medical Journal【中国】 2024年
研究の要旨
研究目的
辛い食べ物の摂取と血管疾患のリスクとの関係を調査する。
研究方法
中国の48万人以上を対象にした前向きコホート研究で、摂取頻度と疾患発症を長期追跡。
研究結果
辛い食べ物を頻繁に食べる人ほど、血管疾患、虚血性心疾患、冠動脈イベントのリスクが低下。
結論
香辛料の摂取は血管疾患の予防に有益な可能性がある。
研究の目的
「辛い食べ物は体に良い」と聞いたことがある方、多いのではないでしょうか?
とくに、「代謝が上がる」「血流が良くなる」といった話は、昔からよく耳にしますよね。
でも実際のところ、辛いものをよく食べる人が病気になりにくいのか、科学的にはまだはっきりしていません。
とくに、心筋梗塞や脳卒中といった“血管の病気”と辛い食べ物との関係については、明確なデータが不足していました。
今回の研究では、中国国内の48万人を対象に、約12年間にわたって「辛い食べ物の摂取頻度」と「血管の病気の発症率」との関係を調べました。
ここでいう「辛い食べ物」とは、唐辛子(チリペッパー)を使った料理や調味料のことを指しています。
具体的には、
・生の唐辛子
・乾燥唐辛子
・チリソース
・チリオイル
などを日常的にどのくらい食べているかを質問票で調査しています。
つまり、カプサイシンによる“ヒリヒリするような辛さ”が研究対象であり、
コショウ(胡椒)や山椒、塩辛さなどの辛さはこの研究には含まれていません。
欧米では「スパイスが寿命を延ばすかも」といった研究報告もありますが、
体質や食文化の異なるアジア圏では、それをそのまま当てはめることはできません。
そこで本研究は、
中国人を対象にして、唐辛子ベースの“辛い食べ物”が、血管系の病気にどのように影響するのか?
を医学的に検証することを目的としました。
要するに――
「辛いもの好きな人は、心筋梗塞や脳卒中にかかりにくいのか?」
という、素朴だけれど気になる疑問に対して、エビデンスで答えようとした研究です。
なお、今回の研究は「心血管・脳血管の病気」がテーマであり、辛いものとがん(食道がん・胃がんなど)のリスクについては対象外です。

研究の対象者と背景
今回の研究に参加したのは、中国国内10地域に住む30歳から79歳までの一般住民48万6,335人です。

都市部と農村部の両方が含まれ、地域差・食文化の違いも考慮されているのが特徴です。
たとえば四川や湖南など、辛い料理が日常的に食べられているエリアも対象に含まれており、
人々がふだんどのくらい辛いものを食べているか、どんな種類の辛さが好きかといった詳細な食習慣もアンケートで把握されました。
対象者は、もともと重い心臓病やがんを持っていない健康な成人が選ばれており、
その後約12年間にわたって、「血管の病気(心筋梗塞や脳卒中など)」の発症が追跡されました。
中国と日本は同じアジア圏であり、体質や遺伝的な特徴にいくらかの共通点があります。
一方で、辛いものの摂取量や味付けの文化は異なるため、この研究結果を完全に日本人に当てはめるのは注意が必要です。
特に、日本では「辛い=塩辛い・脂っこい」となりがちなので、塩分や油分との区別を意識することが大切です。

研究の手法と分析の概要
この研究は「前向きコホート研究」という方法で行われました。
これは、ある集団を長期間追跡し、生活習慣などが将来の病気にどう関係するかを調べる研究スタイルです。
研究の基本情報
・研究デザイン:前向き観察研究(介入はなし)
・追跡期間:平均12.1年間
・対象人数:48万6,335人
観察対象の病気
・虚血性心疾患(心筋梗塞など)
・冠動脈イベント(狭心症、突然死など)
・脳卒中および脳血管障害
データ収集と評価方法
・食習慣の調査:摂取頻度(週に何回辛いものを食べるか)、辛さの好み、摂取歴など
・健康状態の把握:健康診断の結果、病院での診療記録、死亡診断書など
・統計解析:年齢・性別・喫煙歴・飲酒習慣・運動量・BMIなどの要因を調整した上で、辛いもの摂取頻度ごとの病気リスク(ハザード比)を算出
このように、研究は信頼性の高い設計で行われており、データの質や規模も世界的に見て非常に優れたものといえます。

【補足:各種用語】
前向きコホート研究
研究開始時点での健康な集団を長期間にわたって追跡し、将来どんな病気が起きたかを記録する方法です。
「因果関係はあるのか?」を検証するのに適した設計であり、信頼性の高いデータが得られます。
ハザード比(Hazard Ratio, HR)
病気になる“スピード”や“確率”を比べるための指標です。
HR=1.00 → 差がない(基準)
HR<1.00 → リスクが低い
HR>1.00 → リスクが高い
たとえばHR=0.90なら「10%リスクが低い」と解釈します。
研究結果
辛いものが好きな人は、心筋梗塞や脳卒中になりにくい
この研究では、辛い食べ物の摂取頻度を4段階に分けて、「血管の病気(心臓・脳の病気)」の発症リスクとの関連が調べられました。
その結果、
✅️「辛いものをよく食べる人ほど、血管疾患のハザード比(HR)が低くなる」
傾向が明らかになりました。
| 辛い食べ物の摂取頻度 | 対象者数 | 虚血性心疾患のハザード比(HR) |
| ほとんど食べない(基準群) | 約11万人 | 1.00(基準) |
| 月に1〜2回 | 約12万人 | 0.98 |
| 週に1〜2日 | 約15万人 | 0.94 |
| 週に3日以上 | 約10万人 | 0.92(8%低下) |
週3日以上、唐辛子を使った辛い食べ物を食べている人では、心臓の病気(特に狭心症・心筋梗塞)になるリスクがおよそ8%低下していました。
さらに、脳卒中に関しても同様の傾向があり、出血性脳卒中はHR 0.95、虚血性脳卒中はHR 0.94と、それぞれ約5〜6%のリスク低下が見られました。
| 病名 | HR(週3日以上) | リスクの変化 |
| 虚血性脳卒中(詰まるタイプ) | 0.94 | 約6%減少 |
| 出血性脳卒中(破れるタイプ) | 0.95 | 約5%減少 |
いずれも統計的に有意(P<0.05)であり、辛い食べ物と血管疾患リスクに一定の関連があると判断されています。

「辛さの強さ」も重要だった
摂取頻度だけでなく、「どれくらい辛い味を好むか(好みの辛さの強さ)」も、病気リスクと関連していました。
以下のように、強い辛さを好む人ほど、病気のリスクは低めという結果でした。
| 好みの辛さの強さ | 虚血性心疾患のHR(週3日以上摂取者) |
| やや辛い | 0.96 |
| 中程度に辛い | 0.94 |
| とても辛い | 0.88(12%低下) |
つまり、「回数だけでなく、どのくらい辛いものを選んでいるか」もリスクに影響していたという点が興味深いですね。
男性でも女性でも、同じような効果が
この傾向は、男性にも女性にも共通して見られました。
つまり、性別にかかわらず、辛い食べ物を好む人では血管系疾患のリスクが少し低い傾向が確認されています。
生活習慣の違いがあっても同様の傾向が見られた
さらに、喫煙・飲酒・高血圧・肥満といったリスク因子の有無にかかわらず、
「辛いもの好き」の人にはおおむね血管系疾患のリスクが少し低い傾向が確認されており、これは多くの人に共通してあてはまる可能性を示唆しています。
逆にリスクが高くなるグループも?
月に1〜2回程度しか辛いものを食べない人では、病気リスクの変化はほとんどありませんでした(HR 0.98)
また、辛いものを避けている人・苦手な人では、他のグループと比べてややリスクが高めになる傾向もありました(とくに心血管疾患で顕著)
ただし、こうした人々には他に健康上の問題(高血圧、消化器疾患など)を抱えているケースも多く、
「辛いものを食べない=病気になりやすい」と単純に結論づけることはできないと研究者も注意を促しています。
病気ごとのリスク低下(HR一覧)
以下に、代表的な血管系疾患について、週3日以上辛いものを摂取していた人のリスク低下(ハザード比)をまとめます。
| 疾患名 | HR(週3日以上摂取) | おおよそのリスク低下率 |
| 心筋梗塞・狭心症 | 0.92 | 約8%減少 |
| 虚血性脳卒中(血管が詰まるタイプ) | 0.94 | 約6%減少 |
| 出血性脳卒中(血管が破れるタイプ) | 0.95 | 約5%減少 |
このように、心臓・脳の血管トラブルのほぼすべてに対して、辛い食べ物が“少しだけ”守ってくれるような傾向が見られました。
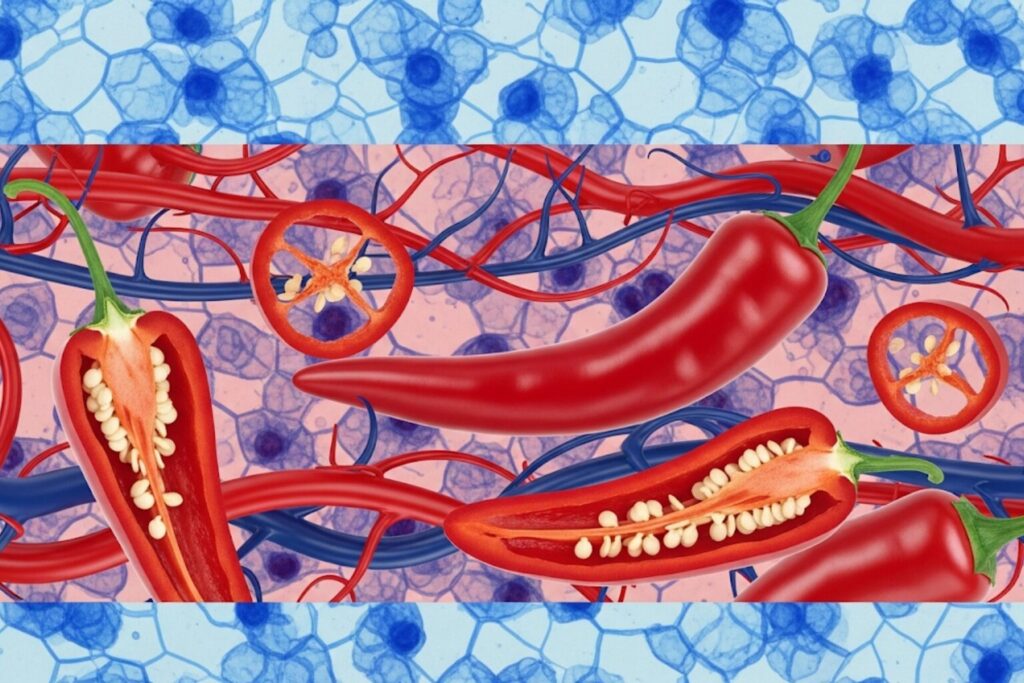
研究の結論
この研究からわかったことは、
辛いものを日常的に食べる人は、心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気にかかるリスクがやや低い
という事実です。
その傾向は、
摂取頻度が週3回以上の人にもっとも強く現れ、男女問わず、辛さの好みによっても影響があった
という点が注目されます。
このように、
“摂取頻度が多いほど”あるいは“辛さの強さが強いほど”血管疾患のリスクが低下する
という、いわゆる用量反応関係(dose-response relationship)が確認された点は、唐辛子の健康効果に対する因果的な可能性を示唆する結果と言えるでしょう。
もちろん、辛いものを食べれば絶対に病気が防げるというわけではありませんが、
辛い食べ物(とくに唐辛子を含む料理)をうまく取り入れた食生活は、血管の健康にプラスに働く可能性がある
という、信頼できるエビデンスです。
なお、今回の研究では「寿命そのものが延びるか(総死亡率)」は評価されていないため、
唐辛子=長寿の秘訣、と断言するにはさらなる研究が必要です。
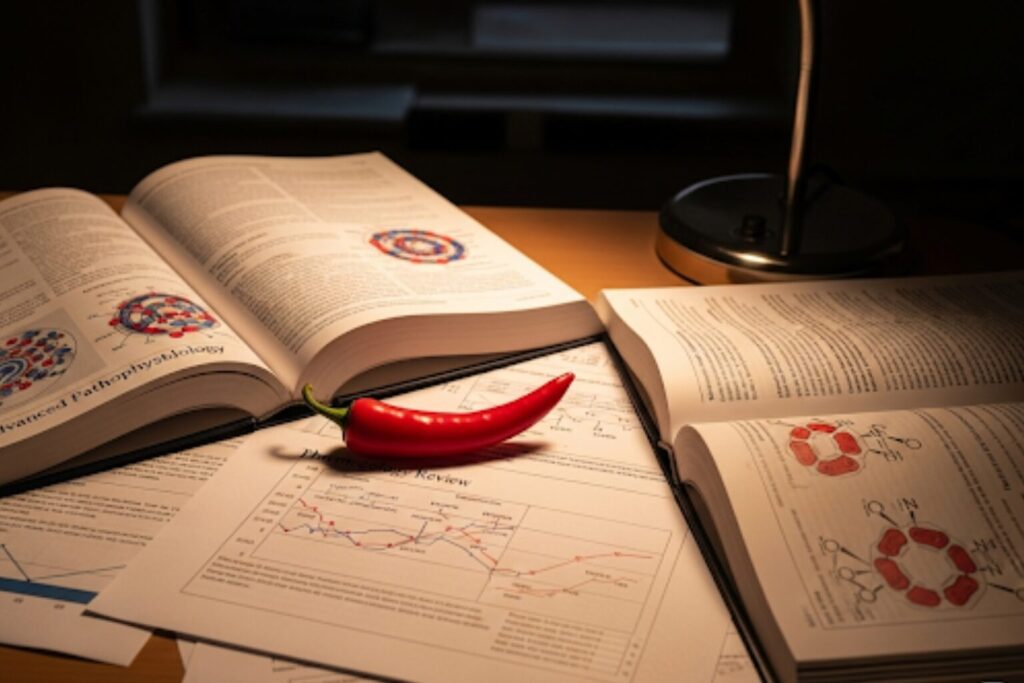
【礼次郎の考察とまとめ】
“唐辛子生活”が血管を守るかも?
辛いものが好きな私としては、かなりうれしい結果でした(笑)
なにより48万人という圧倒的な人数での追跡調査というのが、信頼性をぐっと高めています。
研究者たちの考察によれば、
唐辛子に含まれるカプサイシンが、血管を拡張したり、炎症や酸化ストレスを減らす働きをもつ可能性
があるそうです。
また、辛い食べ物を好む人は、野菜や豆、香辛料など多様な食品をバランスよく摂っている傾向もあるとのことで、
そうした全体的な食習慣が心血管の健康につながっているのかもしれません。
ただ注意点として、この研究では「がん」には触れていません。
辛いもの=体にいい!と盲信せず、食べすぎや刺激の強さには気をつけたいところですね。
日本人にも通じる教訓としては、辛いものを避けがちな人も、
適度に唐辛子や香辛料を食生活に取り入れてみることで、血流改善や代謝の活性化といった小さな健康効果を期待できるかもしれません。
なにより「おいしくて楽しめる食事」が、体にもいいなんてちょっとうれしいですよね。

締めのひとこと
“ヒリヒリ”の向こうに、ちょっとした健康が待っている

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。
やっぱり辛味と言ったらタバスコ!
色んな会社からペッパーソースが販売されていますが、わたし礼次郎はやはり『マキルヘニー社』製の『タバスコ・ペッパー・ソース』が味・辛味ともに至高だと考えております!
スタンダードなタバスコでは物足りないという方は、さらに上級者向けの辛さ『スコーピオン・ソース』はいかがでしょうか?
『純粋な辛さへのこだわりから生まれたタバスコ』の売り文句通り
タバスコ・ペッパー・ソースの約10倍の辛さ!
舌から脳天へ、突き抜けるように刺さります!笑


コメント