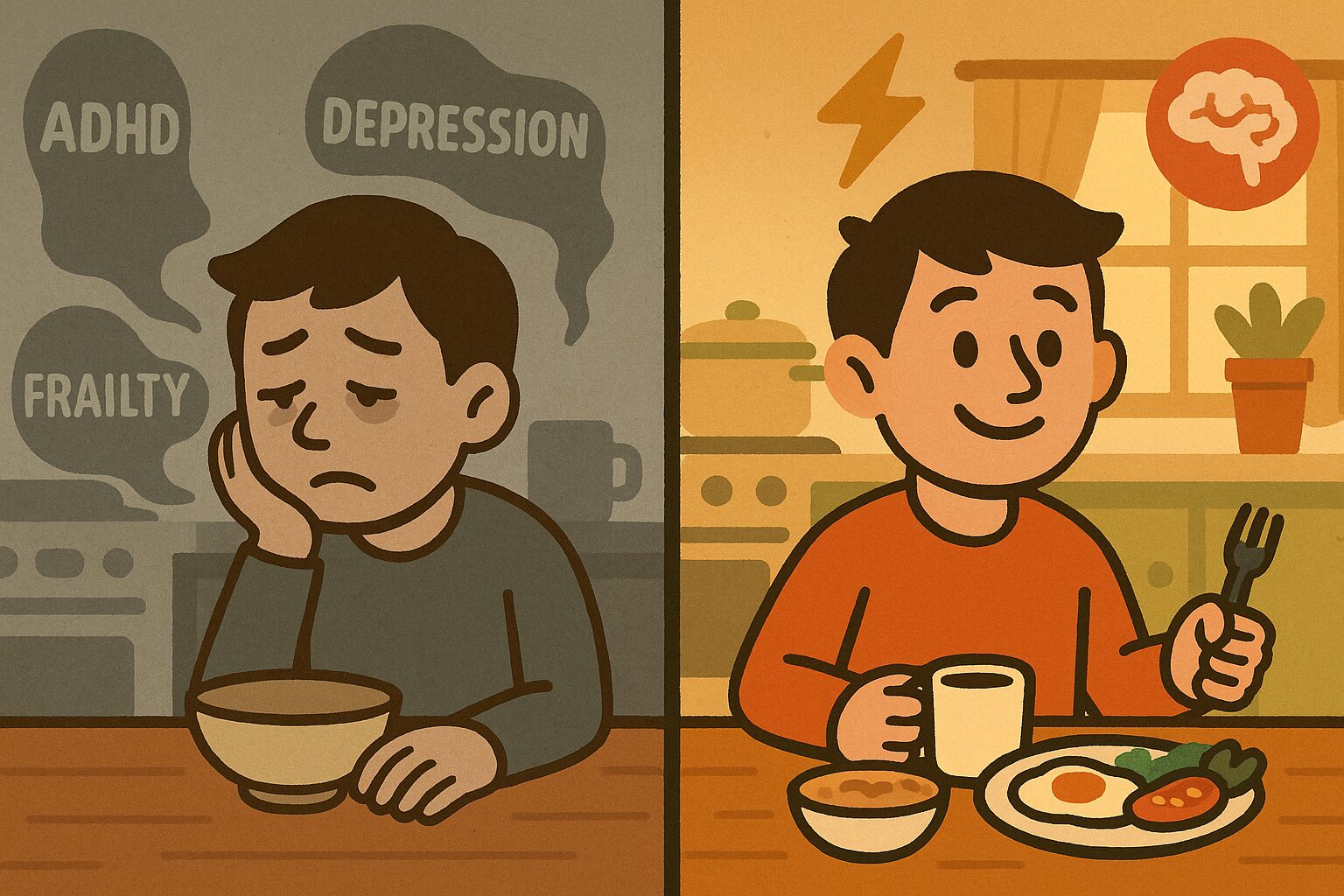
結論「朝食を抜くと、ADHDのリスクや認知力の低下とフレイル(虚弱体質)の進行につながる可能性がある」
この記事はこんな方におすすめ
✅朝は忙しくてつい朝食を抜きがちな方
✅最近、集中力の低下や体力の衰えを感じている方
✅高齢の家族の健康維持を気にかけている方
✅「朝食の大切さ」って本当なの?と感じている方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:朝食を抜くことって本当に心や体に悪いの?
🟡結果:ADHDのリスクは約29%増、フレイルは約68%増。記憶力もやや低下傾向に。
🟢教訓:毎日の朝食が、心と体と脳を守る“防波堤”になるかもしれません。
🔵対象:イギリスなどの19万人超データをもとにした信頼性の高い遺伝子研究です。

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
皆さんは毎日、朝ごはんをしっかり食べていますか?
私は三度の飯より飯が好きなほど食べることが大好きです。
ただ最近では、ブログの記事作成で夜中まで作業してしまう日も増えてきて、朝起きるのがだんだん辛くなってきました。
そんな日は、つい朝食を抜いて、プロテインやコーヒーだけで済ませてしまうことも少なくありません。
「朝ごはんは大事!」とはよく耳にしますが、正直なところ「気合でどうにかなるもの」と思っていた節もありました。
そんな中、「朝食を抜くことが、精神面や身体機能に本当に影響を与えるかもしれない」という衝撃的な研究論文に出会ったんです。
本日ご紹介するのは、そんな朝ごはんと健康の関係を遺伝情報に基づいて科学的に検証した、信頼性の高い国際的な研究です。
この論文は、イギリスの精神医学専門誌『BMC Psychiatry(BMC 精神医学)』に2024年に掲載されました。
今回はこの研究をもとに、
「朝食を抜くこと」が脳・心・体にどんな影響を与えるのか
を、できるだけやさしく、でも正確にお伝えしていきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Associations between breakfast skipping and outcomes in neuropsychiatric disorders, cognitive performance, and frailty: a Mendelian randomization study”
(朝食抜きと神経精神疾患・認知機能・フレイルとの関連:メンデルランダム化による研究)
BMC Psychiatry. 2024 Apr 2;24(1):252.
PMID: 38566068 DOI: 10.1186/s12888-024-05723-1
掲載雑誌:BMC Psychiatry【アメリカ】 2024年4月
研究の要旨
研究目的:
朝食抜きと神経精神疾患、認知機能、フレイルの因果関係をメンデルランダム化手法で評価すること。
研究方法:
欧州系GWAS(Genome-Wide Association Study:ゲノムワイド関連解析)データを用い、二標本メンデルランダム化(IVW法)で朝食習慣と各種健康アウトカムとの関係を解析。
研究結果:
朝食抜きはADHD(OR=2.74)、MDD(OR=1.7)、認知機能低下(β=-0.16)、フレイル増加(β=0.29)と有意な関連を示した。
結論:
朝食を抜くことはADHD、うつ、認知機能低下、フレイルのリスク要因である可能性が高い。
研究の目的
この研究の目的は、
「朝食を抜くこと」が、本当に精神的な不調や体の衰えの原因になるのか?
を明らかにすることでした。
というのも、これまでの研究では「朝食を抜く人ほど、うつっぽくなったり、集中力が落ちたり、体力がなくなったりしている」といった傾向は報告されていました。
でも、それが朝食を抜くこと“そのもの”が原因なのかどうかは、はっきりしていなかったのです。
もしかすると、「元々うつ傾向があるから朝ごはんを食べない」「もともと体が弱いから朝から食欲がない」といった逆のパターンも考えられます。
そこで今回の研究では、遺伝情報を活用した「メンデルランダム化」という手法を使って、こうした“逆因果”や“思い込み”を排除し、
「朝食を抜くことに本当に原因としての力があるのか?」を客観的に調べました。

研究の対象者と背景
この研究は、イギリスを中心としたヨーロッパ系の大人たちを対象に行われました。
朝食の習慣と、精神や身体の健康に関わるさまざまなデータを遺伝情報とあわせて分析しています。
具体的には、イギリスのUKバイオバンク(UK Biobank)という大規模な健康データベースから、約19万人の朝食に関する情報を取得。

加えて、
・ADHD(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動症)、
・うつ病
・認知機能
・フレイル(虚弱体質)
などに関するデータは、最大で46万人以上の欧州系成人を含む複数の国際的データベースから収集されました。
対象者の年齢は主に40〜70歳代、男女比はおおむね半々です。
ただし、これらのデータはすべて「欧州系の人々」に限られているため、日本人に完全に同じ結果が当てはまるとは限らないことには注意が必要です。
とはいえ、「朝食を食べるかどうか」が健康に影響する可能性は、日本人にも大いに関係があるテーマです。

研究の手法と分析の概要
この研究では、「メンデルランダム化(MR)」という手法を使って、朝ごはんを抜く習慣と健康への影響に因果関係があるのかを調べました。
これは、遺伝子の情報を“自然の実験”として活用するという、信頼性の高い統計的なアプローチです。
まず最初にやったこと
最初に研究者たちは、イギリスの「UK Biobank(UKバイオバンク)」という大規模な健康データベースに登録された約19万人分の情報を使って、「朝ごはんを抜きがちな人たち」を特定しました。
その人たちの遺伝子データを分析し、共通して見られる遺伝的な特徴(SNP:一塩基多型)を探しました。
これによって、「朝食を抜く傾向がある体質」と関連する遺伝的マーカーが特定されました。

その遺伝子を使って、次にやったこと
次に、別の大規模データベースを使って、その遺伝的マーカーを持つ人が、実際に「精神的な不調」や「体の衰え」を起こしやすいのかどうかを調べました。
調査対象となった健康指標は以下のようなものです:
・うつ病
・ADHD(注意欠如・多動症)
・認知機能
・フレイル(加齢による心身の虚弱)
これにより、「朝食を抜く体質」がこれらの症状や疾患の原因になっているかどうかを、より客観的に検証したのです。
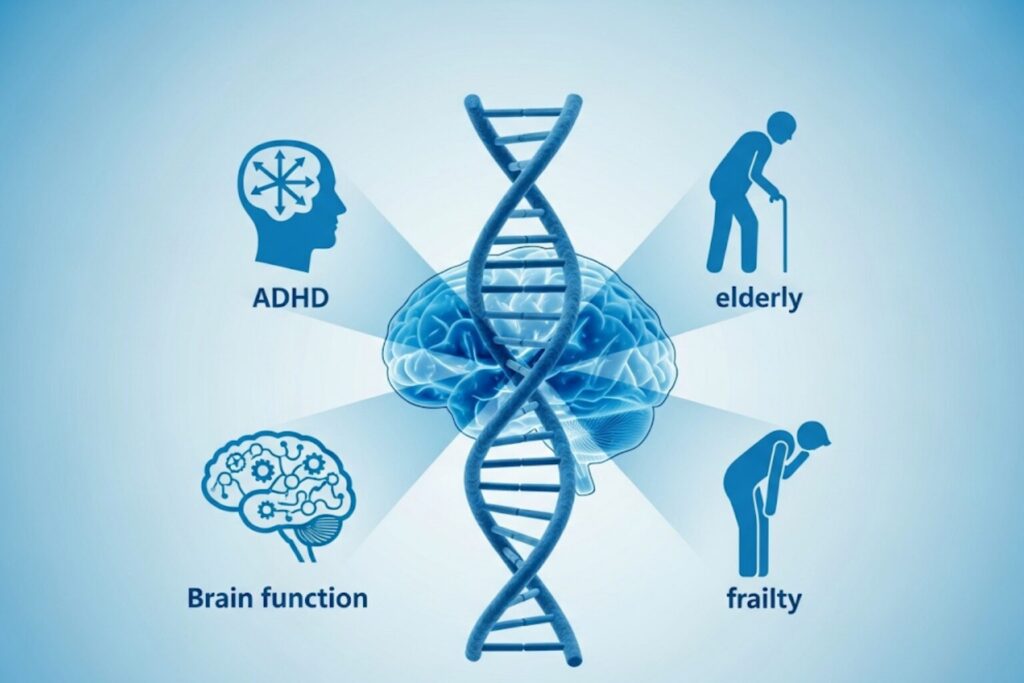
どうしてこの手法が使われたのか?
ふつうの観察研究では、「朝ごはんを食べない人は体調が悪くなりやすい」といった“関連性”はわかっても、“どっちが原因か”ははっきりしません。
たとえば、「体調が悪いから朝食が食べられないだけかもしれない」という“逆の因果”も考えられるからです。
でもMRは、生活習慣や気分に影響されない“生まれつきの遺伝子”をもとに調べるため、こうした混乱を避けて因果関係の有無を調べられるのが強みです。
信頼性を高める工夫も
この研究では、分析の信頼性を高めるために、以下のような複数の統計手法も使われました
・IVW法(Inverse Variance Weighted):最も基本で信頼性が高い推定方法
・MR-Egger法・加重中央値法:外れ値や偏りが結果に影響していないかを確認
・MR-PRESSO法:異常なデータ(外れ値)を検出し、修正する手法
・FDR補正(多重比較補正): 偶然の誤差で「有意」とならないよう調整する方法
これらの工夫により、より正確で再現性のある結果が得られるようになっています。

【補足:各種用語】
メンデルランダム化(MR)
MRは、「親からもらった遺伝子はランダムに決まる」という法則(メンデルの法則)を活かした方法です。
たとえば、「遺伝的に朝食を抜きがちな体質の人」が実際にうつ病やフレイルになりやすいなら、
“朝食抜きの体質”がそれらの原因になっている可能性が高いと考えられます。
SNP(Single Nucleotide Polymorphism:一塩基多型)
SNP(スニップ)とは、人によって少しずつ違うDNAの“一文字の違い”のことです。
この小さな違いが、体質や病気のなりやすさに関係していることがあります。
フレイル(Frailty)
フレイルとは、筋力や免疫力が低下し、病気やケガに弱くなった状態のこと。
特に高齢者で多く、寝たきりや認知症のリスクを高めるとされており、健康寿命を守るうえで注目されています。
研究結果
「朝食抜き」が心と体に与える、驚きの影響とは?
この研究では、「朝ごはんを抜きがちな体質(遺伝的傾向)」をもつ人が、以下のような心と体の不調を起こしやすいことが明らかになりました。
なかでも影響が大きかった3つの健康指標を、表にまとめました。
| 症状・状態 | リスクの変化 | 統計的有意性 | 備考 |
| ADHD(注意欠如・多動症) | 約29%増加(OR 1.29) | P = 0.027 | IVW法で有意 |
| フレイル(虚弱) | 約68%増加(OR 1.68) | P = 0.009 | MR-PRESSOで外れ値なし |
| 認知機能の低下 | 軽度の低下(β = -0.13) | P = 0.035 | 感度分析で一貫性あり |
・ADHD:注意力や集中力に関わる発達特性。朝食を抜く体質の人は、発症リスクが約3割高くなっていました。
・フレイル(虚弱):筋力や活動能力の低下リスクが約1.7倍に上昇。とくに中高年にとって見逃せない所見です。
・認知機能の低下:記憶や思考力のスコアがわずかに低下(β = -0.13)。一見小さな数値でも、母集団レベルでは意味のある変化です。
影響がなかった項目(陰性所見)
・うつ病・統合失調症・双極性障害:いずれも統計的に有意な関連は見られませんでした。
・BMI(体格指数):朝食抜き体質と体重や肥満傾向には関係がなく、「朝食を抜く=太る」または「太っているから朝を抜く」といった相関は確認されませんでした。
・アルツハイマー病や全般的な認知症:これらの疾患リスクと朝食抜きの関係も認められませんでした。
→ これらの結果は、「少なくとも悪化を招く証拠はない」ことを示しており、安心材料にもなります。
また、自閉スペクトラム症(ASD)、強迫性障害(OCD)、全般性不安障害(GAD)といった他の神経精神疾患についても、朝食を抜く体質との間に有意な関連は見られませんでした。
感度分析で確認された“因果関係の可能性”
この研究では複数の統計手法(IVW法・MR-Egger法・加重中央値法・MR-PRESSO法)を用いて、外れ値の有無や分析結果の一貫性を検証しています。
その結果、上記3項目については手法を変えても同様の傾向が確認され、「朝食を抜くことがリスクの原因になっている可能性が高い」と判断されました。
研究の結論
「朝食を抜く体質」は、心と体の健康に静かに影響している
この研究は、遺伝的な傾向を手がかりに「朝食を抜く習慣」と健康状態との因果関係を調べたものです。
その結果、朝ごはんを抜く傾向のある人は、
✅️ADHD(注意力や集中力に影響)を発症するリスクが約29%高い
✅️加齢に伴う体の虚弱(フレイル)を起こすリスクが約68%高い
✅️記憶力や思考力といった認知機能もわずかに低下する傾向がある
ことがわかりました。
しかもこの結果は、ただの相関関係ではなく、遺伝情報に基づくメンデルランダム化という手法で「朝食を抜くこと自体が原因となっている可能性が高い」とされるものです。
つまり、
「朝ごはんを食べる・食べない」という習慣は、気合や好みではなく、将来の心身の状態を左右する“静かな選択”かもしれない
ということです。
なお、本研究は「メンデルランダム化」によって因果関係の可能性を示すことが目的であり、
メカニズムの詳細は検証していないと明記されています 。

【礼次郎の考察とまとめ】
朝ごはんは、“大人の発達”にも影響するのかもしれない
今回の研究は、「朝食を抜く」というよくある習慣が、思った以上に私たちの脳や体に関わっている可能性を示してくれました。
特に印象的だったのは、ADHDやフレイルとの関連です。
子どもの発達だけでなく、大人になってからの集中力の持続や、老後の体力にまで影響するかもしれない──そう思うと、朝ごはんを抜くことの意味がずっしり重く感じられます。
とはいえ、毎朝しっかりした食事を整えるのが難しい人も多いはずです。
私もその一人で、仕事の忙しさや生活リズムで、朝ごはんを抜くことがどうしても出てきてしまいます。
でも「できる日だけでも、意識して摂る」ことで、脳や体に優しくなれるのなら、それはちょっとした“自分への投資”かもしれません。
特に日本のように高齢化が進む社会では、「フレイル予防」の観点からも、朝食習慣の見直しは大切な一歩になると感じました。

締めのひとこと
朝ごはんを食べることが、未来の自分を守る“ちいさな積み重ね”になる。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。
私、礼次郎のお気に入り朝ご飯!!
最強冷凍食品メーカー『ニッスイ』の焼きおにぎり🍙
レンチン2分でしっかり朝ご飯
お茶漬けにしても美味🍵
脂肪抜きでダイエットにもピッタリです!!


コメント