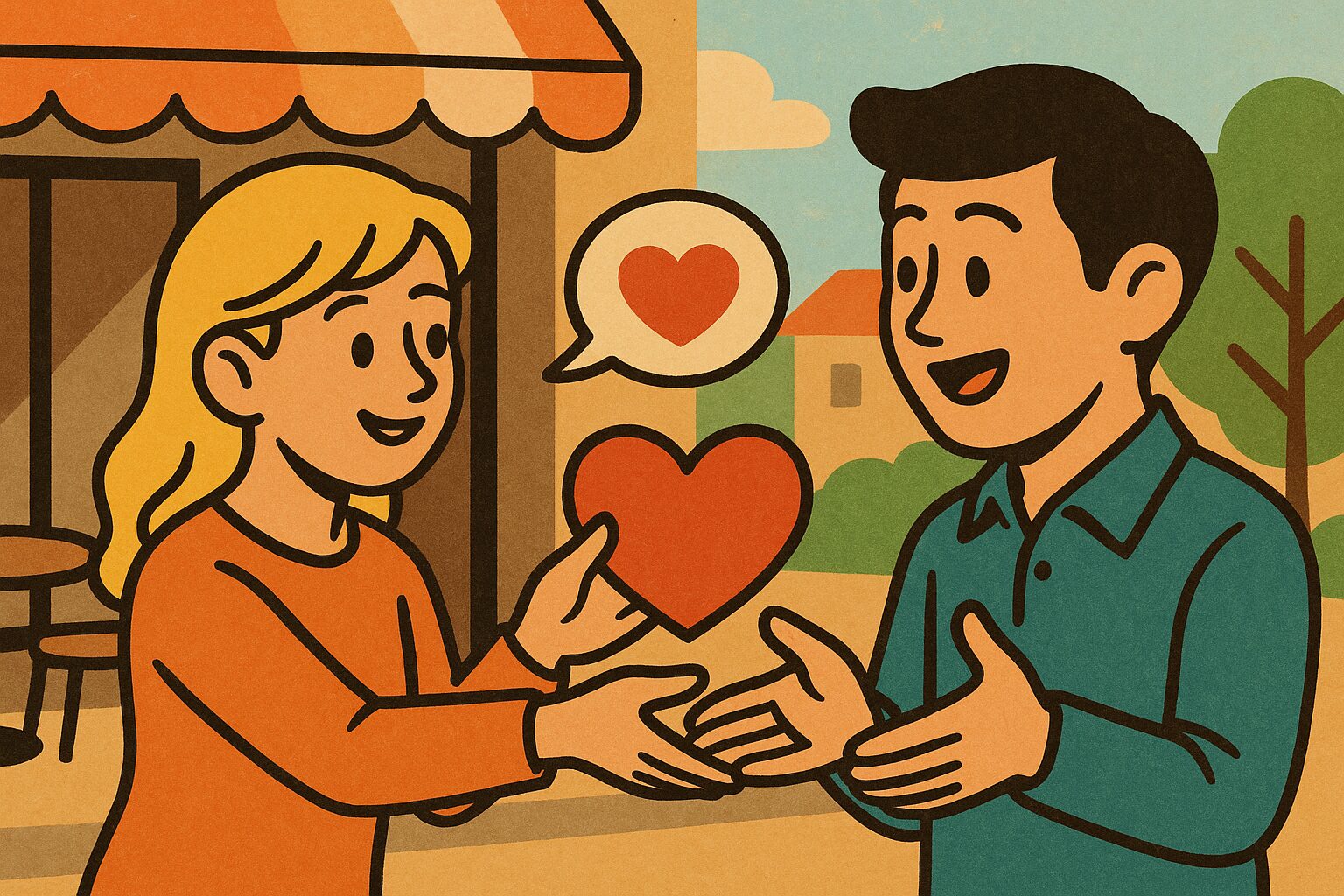
結論「「“先出しの精神”が、心を満たす――自分から愛を示すことで、“愛されている感覚”があとから育つ」
この記事はこんな方におすすめ
✅「与えてばかり」で空しくなる感覚に悩んでいる方
✅人とのつながりが希薄に感じている方
✅心の満足感や自己肯定感がほしいと感じている方
✅“科学で納得できる”人間関係のヒントを探している方
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:なんであの人は、人間関係がうまくいってるんだろう?
🟡結果:自分から愛を表現したあと、平均1.7時間以内に“愛されている感覚”が高まる傾向が確認されました
🟢教訓:先に“愛を届ける”「先出しの精神」が、自分自身の感情を満たす力になるのかもしれません
🔵対象:アメリカ在住の一般成人52人のデータ。文化の違いはあるものの、日本人にも参考になる心の仕組みです

※本記事内の画像は主にChat GPTおよびGeminiを用いて、すべてAIで生成しております。すべてイメージ画像であり、本文の内容を正確に表したものではありません。あらかじめご了承ください。
はじめに
皆さん、こんにちは!
誰かに優しくしたとき、逆に自分の心もふっと軽くなるような経験ってありませんか?
私は以前、自分の気分が不安定な時期があり、その影響で職場の人間関係にも支障を感じたことがありました。
あれこれ振り返ってみて、「もしかしたら自分の気分が落ちていたせいで、人への接し方が乱暴だったり、言葉がどこかテキトーになっていたのかもしれない」と気づいたんです。
それ以来、意識して「ありがとう」と伝えたり、相手の立場を想像して言葉を選ぶよう心がけるようになりました。
すると、少しずつ周囲との関係がほぐれていくのを実感できたんです。
本日ご紹介するのは、そんな“愛を伝えること”と“愛されている実感”のつながりを、科学的に調べたとても興味深い研究です。
この論文は、アメリカの科学雑誌『PLOS ONE(プロス・ワン)』に掲載されたもので、日常生活における愛の表現と感情のダイナミクス(変化の流れ)を扱っています。
今回は、その研究をもとに、
「愛を感じるためにできる具体的な行動」
について、やさしく解説していきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“How much we express love predicts how much we feel loved in daily life”
(日常生活において「愛を表現する量」は「愛されていると感じる量」を予測する)
PLoS One. 2025 Jul 2;20(7):e0323326.
PMID: 40601603 DOI: 10.1371/journal.pone.0323326
掲載雑誌:PLOS ONE【アメリカ】 2025年7月
研究の目的
この研究の目的は、日常生活における「愛を表現すること」と「愛されていると感じること」が、時間の流れの中でどのように影響し合っているのかを明らかにすることです。
これまでの心理学の研究では、「人に愛を伝えること(表現すること)」や「自分が愛されていると感じること」が、それぞれ幸福感(ウェルビーイング)と関係していることは知られていました。
しかし、両者がリアルタイムでどうつながっているのか、どちらが先に起こるのか、どれくらい影響が続くのか…
といった“時間的な関係”については、これまであまり詳しく調べられていませんでした。
とくに、「愛を表現したあとに、時間がたってから“愛されている感覚”が高まるのかどうか」といった因果関係については、日常生活の中で測定された研究は非常に限られていました。
そこで本研究では、参加者の日々の気持ちを記録し、愛の感情の変化を“時間軸”で追跡し、
「愛を表現することが、その後の“愛されている実感”にどんな影響をもたらすのか」
を科学的に検証しました。

研究の対象者と背景
この研究は、アメリカ・ペンシルベニア州に住む成人52人を対象に行われました。

参加者のうち67%が女性、80%が白人で、年齢は19歳〜65歳(平均30歳)。
全体の9割近くが恋人やパートナーのいる状態でした。
対象者の教育レベルはさまざまで、大学卒業以下が約4割、大学卒が4割、大学院レベルが約3割と、知的な層がやや多めの印象です。
ただし、人種構成がほぼ白人に偏っていたことや、1つの地域での調査だったことから、文化や生活習慣が異なる日本人にそのまま当てはめるには注意が必要です。
特に、日本では愛情表現を口に出す文化が控えめな傾向があるため、同じ行動をとっても感じ方や効果に違いがあるかもしれません。
研究の手法と分析の概要
この研究では、観察研究(エコロジカル・モーメンタリー・アセスメント=EMA)という手法が使われました。
参加者には4週間の間、1日6回スマートフォンに届く通知に応じて、
・今どれくらい愛されていると感じているか
・最近どれくらい愛を表現したか
を、それぞれ0~100のスライドバーで回答してもらいました。

このようなリアルタイムの感情記録を長期間にわたってくり返し集めることで、
・その人の中で愛の気持ちがどのように変化していくか
・愛を表現したあと、どれくらいしてから“愛されている感覚”が高まるのか
といった流れを、時間の軸にそって分析することができます。
さらに研究チームは、この大量のデータをもとに、
連続時間確率モデル(continuous-time stochastic process model)という数理モデルを使いました。
これは、個人ごとの感情の変化を「一人ひとりに固有の感情の動き」として捉えることができる方法で、
たとえば、
・どれくらい長く感情が続くか(=慣性)
・他の感情にどれくらい影響を与えるか(=交差影響)
といった特徴を数値として評価できます。
この手法を使うことで、「愛の気持ちや行動がどんなリズムで変わっていくのか」、
そして「それぞれがどう影響し合っているのか」を、
非常に繊細かつ現実的にとらえることができるのが、この研究の大きな特長です。

【補足:各種用語】
エコロジカル・モーメンタリー・アセスメント(EMA)
→ 日常生活の中で、その瞬間の気分や行動を記録してもらう手法。
記憶に頼らず“今このとき”を記録できるのが特長です。
連続時間確率モデル
→ 感情や行動の変化を、時間の流れに沿って“なめらかに”追いかける数学モデル。
個人ごとに異なる感情の癖(続きやすさ、変わりやすさなど)を数値で表現できます。
慣性(inertia)
→ 一度感じた愛情がどのくらい長く続くかを示す指標。
高ければ「ずっと愛を感じている」タイプ、低ければ「気分がすぐ切り替わる」タイプです。
交差影響(cross-influence)
→ たとえば「愛を表現したこと」が「愛を感じること」にどれだけ影響を与えるかを測る分析。
逆方向(感じる→表現する)も調べられます。
研究結果
愛を表現すると「愛されている感覚」が高まった
この研究では、「人に愛を伝えること」が、あとで「自分が愛されていると感じる気持ち」にどう影響するかを詳しく調べました。
その結果、誰かに愛情を表現したあと、約1.7時間のあいだに“自分が愛されている”という実感が高まることがわかりました。
つまり、
「愛を与える行動」が、その後に自分の感情にも良い影響をもたらしていたのです。
これは「先に受け取る」ことが大事なのではなく、自分から与えることによって心が整う可能性を示唆しています。

逆の方向(愛された→表現した)にはほぼ影響なし
一方で、「愛されていると感じたあと」に、誰かに思いやりを返すかどうかを分析したところ、その影響はほとんど見られませんでした。
この結果は、“返報”よりも“自発的に与えること”の方が感情に強く働きかけることを示しており、
これまで直感的に語られていた「愛は与えるもの」という考え方に、明確な科学的裏付けを与える発見となっています。
感情の「持続力」は愛を表現したときの方が強い
研究では、感情がどれくらい長く続くか=“慣性”についても分析されました。
その結果、「愛を表現したとき」の気持ちの方が、「愛されたと感じたとき」よりも長く続きやすいことがわかりました。
つまり、相手を思いやる行動の方が、自分の心に長く余韻を残す傾向があったのです。
感情の変化には個人差も
この効果の現れ方には、人によって大きなばらつきがあることもわかりました。
「愛を表現したあとに、ぐっと気分が良くなる人」もいれば、「あまり変化を感じない人」もいます。
この違いは性格や人付き合いのスタイルだけでなく、「感情の構造(emotion dynamics)」という心のクセにも関係している可能性があります。
研究チームは個人ごとの“交差影響(cross-influence)”の強さも分析しており、
「愛を表現したこと」が自分自身の感情に強く影響を与えるタイプの人ほど、はっきりとした変化を感じやすい傾向があることが示されました。
つまり、
人によって「心の響きやすさ」に差がある
ことがわかってきたのです。
これは、「人に優しくしても満たされた気がしない…」という感覚を抱える人にとっても、
無理を責めすぎず、「自分の感じ方を知ること」から始められるヒントになるかもしれません。

「誰に伝えたか」「性別差」などは未分析
今回の研究では、
「誰に対して愛を表現したのか」(たとえば恋人か家族か友人か)や、「性別・年齢」などの違いによる効果の差については分析が行われていませんでした。
これは今後の課題とされています。
感情の変化に時間帯の偏りなし
さらに、研究チームは「朝・夜」や「平日・週末」といった時間帯による感情変化の違いについても確認しました。
その結果、感情の変化は一日のどの時間でも一貫して見られたことがわかっています。
「モデルが個人ごとの感情パターンに合っていた」ことも確認済み
本研究では、数理モデル(連続時間確率モデル)を用いて、ひとりひとりの感情の変化を再現可能なかたちで捉えていました。
そしてそのモデルが、実際のデータにしっかり合っているか(モデルフィット)も検証済みで、再現性と信頼性の高い結果となっています。
主な結果まとめ
| 観察項目 | 結果 |
| 愛の表現(思いやりや感謝) | 「愛されている感覚」に約1.7時間影響 |
| 「愛されている感覚」→「愛の表現」方向 | ほとんど影響なし |
| 感情の“慣性”(気持ちの持続性) | 愛を表現したときの方が持続しやすい |
| 効果の個人差 | 人によって効果の強さはバラバラ |
| 時間帯による偏り | なし(全時間帯で一貫) |
| モデルの信頼性(フィット) | 個人の感情データにきちんと適合 |
研究の結論:「愛を与えること」が、自分を満たす
この研究から得られた最大の結論は、
「人に愛情を示すこと」が、その後の「自分の感情」にもプラスの影響を与える
ということです。
つまり、「愛されること」よりも
「愛すること」「思いやりを伝えること」こそが、自分自身を“愛されている”と感じさせてくれる
――という、これまで感覚的に語られてきた考え方に科学的な裏づけが与えられました。
しかも、その効果は一時的な気まぐれではなく、
感情の流れを時間軸で細かく分析したうえでも確認された、継続的かつ一貫したものだったのです。

【礼次郎の考察とまとめ】:「愛を伝える」は、自分の心のケアでもある
正直に言えば、私はこれまで「人に優しくする」ということを、どこか“他人のため”の行為だと思っていました。
でもこの研究を読んで、自分から「ありがとう」「嬉しいよ」と伝えることが、実は“自分の心を整える行動”でもあるのだと気づかされました。
とくに注目すべきは、自分が人に優しくしたあと、その余韻が長く心に残っていたという点。
一方で「愛されたと感じたこと」は、案外すぐに消えてしまう。
この違いは、人との関係において“自分ができること”に目を向けるヒントになるのではないでしょうか。
こうした結果を見て改めて思ったのは、
まさに「先出しの精神」の大切さです。
つまり、相手からの反応を期待して待つのではなく、まず自分から気持ちを伝えることで、感情の循環がはじまるということ。
この“与えることが先”というシンプルな姿勢こそが、実は自分を助ける一歩でもあるのだと、あらためて感じました。
私たち日本人は、日常的に気持ちを言葉にする文化があまり強くないぶん、「表現する愛」が不足しがちかもしれません。
でも、「先に伝える」ことで、結果的に自分の心も満たされるというのは、忙しい毎日のなかでもすぐに試せる、大きなヒントだと思います。
気持ちが沈んでいるときこそ、相手のことを考えて、小さくても優しい言葉をかけてみる。
その行動が、自分を少しラクにしてくれるかもしれません。

締めのひとこと
「誰かを想うこと」は、自分自身を大切にすることにもつながっている。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。
私、礼次郎がこの夏にお世話になった方への贈り物に選んだのがこちら。
茨城県の“知る人ぞ知る”焼き芋メーカー「かいつか」さんの【紅天使】冷凍焼き芋です。
これはもう、天然スイートポテト。
甘み・ねっとり感ともに極上。
「夏に焼き芋?」と思われるかもしれませんが、
冷蔵庫で冷やしてから食べるとまさに“ひんやりスイーツ”。
だまされたと思って、ぜひ一度ご賞味ください!


コメント