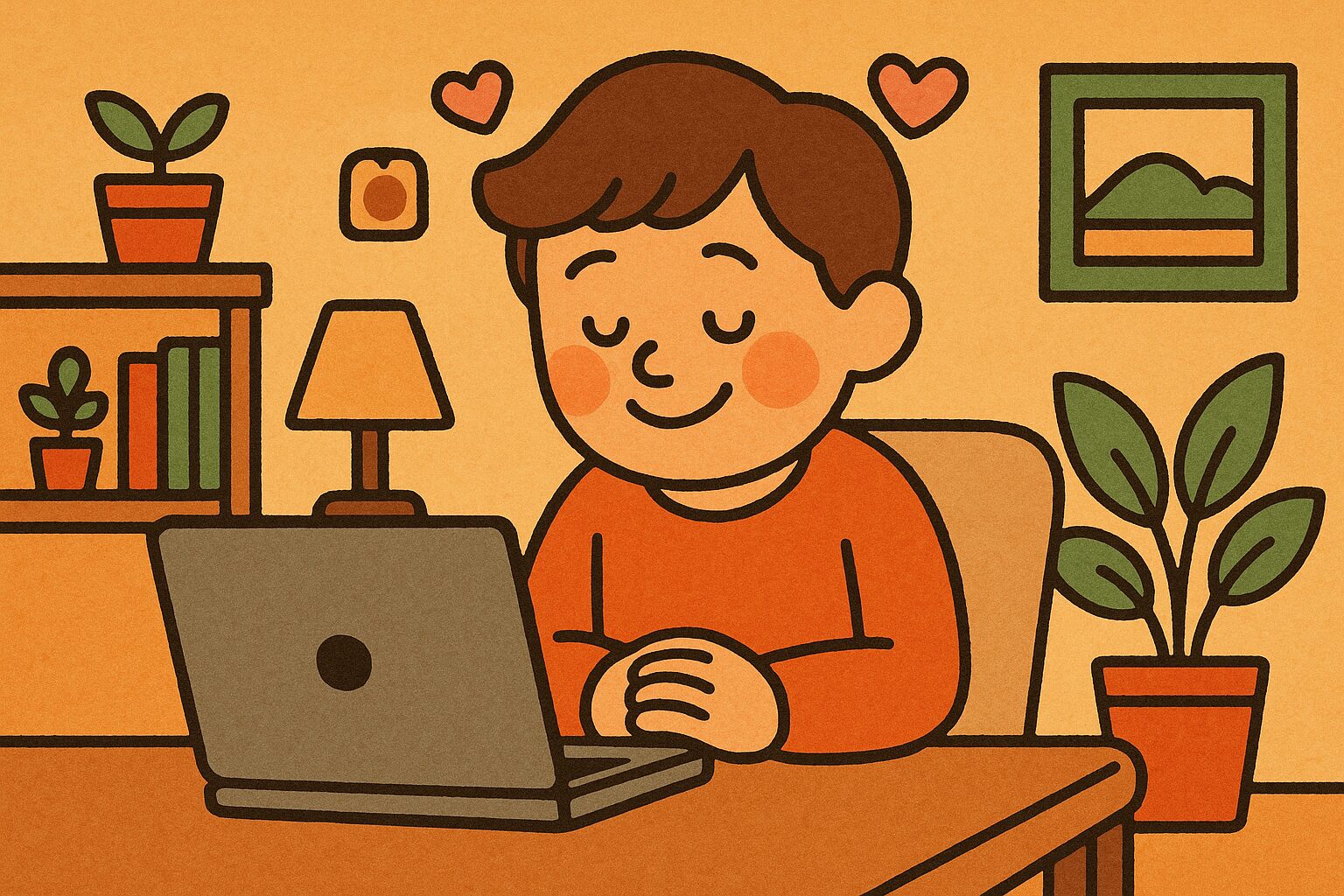
結論「『ひとり笑い』は“変”じゃない。むしろ、心に効く“セルフケア”だった。」
この記事はこんな方におすすめ
✅なんとなく気分が落ち込むことがある
✅家でひとりで笑う自分がちょっと変かも…と不安になる
✅「笑いは健康に良い」と聞くけど、一人で笑うのはどうなんだろう?と思っている
✅メンタルを整える“新しい習慣”を探している
時間のない方・結論だけサクッと知りたい方へ
🔴疑問:「ひとりで笑う」人って変じゃない?
🟡結果:文献調査のうち26%が「ひとり笑いは心に良い影響がある」と報告。
🟢教訓:思い出や動画などで自然に笑うことが、自分を癒やす“心のセルフケア”になりうる。
🔵対象:1970〜2024年に発表された120件の多国籍文献を調査(イギリス中心)

はじめに
皆さん、こんにちは!
ふとした瞬間、昔のテレビ番組や漫画を思い出して、つい一人でクスッと笑ってしまったこと、ありませんか?
私は子どものころから、漫画やテレビの内容を思い出して一人で笑っていると、よく親に「大丈夫?」と心配されたものです。
周りに誰もいないのにニコニコしていたり、ふと笑ってしまったりすると、「あの人ちょっと変かも…」なんて思われるんじゃないかって、気になったことはありませんか?
小説や映画の中でも、ひとりで笑う登場人物が「狂気の象徴」のように描かれる場面って、意外と多いですよね。
そんなふうに、“ひとり笑い=不気味”というイメージが、私たちの心のどこかに刷り込まれている気がします。
でも実は、その「ひとり笑い」こそが、心の健康を保つヒントになるかもしれません。
本日ご紹介するのは、イギリスのメンタルヘルス専門雑誌『Discover Mental Health』に掲載された、「ひとり笑い」の効果を科学的に検証した研究です。
今回はその研究をもとに、ひとり笑いが私たちの心にどう作用するのかをやさしく解説していきます。

自己紹介
こんにちは! 某県の大規模病院で外科医として約20年の経験を持つ「医学論文ハンター・Dr.礼次郎」です。
海外の権威ある医学雑誌に掲載された論文を一編ずつ読み解いた、
生の「一次情報」をもとに、医学に詳しくない方にもわかりやすく解説しています。
日々、皆さんに信頼できる医療情報をお届けします!

今回読んだ論文
“Liberating the mental health and wellbeing benefits of laughing alone: a new taxonomic model and scoping review for future research”
(ひとり笑いのメンタルヘルスとウェルビーイング効果を解き放つ:新しい分類モデルと今後の研究のためのスコーピングレビュー)
Discov Ment Health. 2025 Apr 28;5(1):63.
PMID: 40295448 DOI: 10.1007/s44192-025-00183-9
掲載雑誌:Discover Mental Health(ディスカバー・メンタルヘルス)【イギリス】 2024年4月
研究の目的
この研究が目指したのは、「ひとり笑い」が私たちの心と体にどんな影響を与えるのかを明らかにすることです。
これまで「笑い」は人と一緒に行う“社会的なもの”と考えられてきました。
一方で、「一人で笑う」という行動は、ちょっと変わっているとか、精神的に不安定なサインと見なされることもありました。
でも実は、日常の笑いのうち1割以上が“ひとりの状態”で起きているというデータもあります。
そこでこの研究では、ひとり笑いの実態とその意味を探るために、過去50年にわたる多くの文献を集めて分析し、
さらに「どんな種類のひとり笑いがあるのか」を分類するための新しい枠組みも提案しました。
研究者たちは、
「ひとりで笑うこと」が本当におかしな行動なのか?
あるいはむしろ心の健康にとって大切な行為なのではないか?
という問いに正面から取り組んだのです。

研究の対象者と背景
今回の研究は、ひとつの実験や調査ではなく、「スコーピングレビュー」と呼ばれる手法で行われました。
研究チームは、1970年から2024年までに発表された英語の文献を分析対象としました。
これらの文献には、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパ諸国など、さまざまな国や文化に基づく記述が含まれており、研究対象も国際的に多岐にわたります。

ただし、すべてが英語で書かれているという点から、欧米圏の文化的な価値観が色濃く反映されているとも言えます。
本研究の中心は欧米に偏っているため、「ひとりで笑う」ことに対する文化的な価値観の違いには注意が必要です。
たとえば日本では、「人目を気にする」「空気を読む」文化が強いため、公的な場での“ひとり笑い”は誤解を生みやすいかもしれません。
その一方で、自宅やプライベート空間でのひとり笑いを「自分への癒し」として取り入れる発想は、むしろ日本人の感覚に合っているとも言えます。
この研究は、そうした文化差を超えて、ひとり笑いをポジティブに見直すきっかけになるかもしれません。
研究の手法と分析の概要
研究チームは、「スコーピングレビュー」という手法を用いて、過去50年以上にわたる文献の分析を行いました。
これは、あるテーマについて過去にどのような研究や議論があり、全体の傾向やどんな視点が足りていないのかを整理するための方法です。
実験結果を統合する「メタアナリシス」とは異なり、研究の全体像を広く見渡すのが目的です。
具体的には、以下の手順で調査が行われました。
・検索対象データベース:PubMed、Web of Science、EBSCO、Google Scholar、JSTOR など複数を使用
・キーワード検索:“solitary laughter”, “solo laughing”, “laughing alone” などの組み合わせを使用
・文献数:初期に488件がヒットし、その中から内容を精査して最終的に120件を採用(うち83件が学術論文)
残りの37件には、小説や詩、エッセイ、自伝、哲学書、映画や演劇の評論なども含まれています。
これは、「ひとり笑い」が実際の行動だけでなく、創作物の中でどのように描かれ、理解されてきたかも重要な情報源と考えたためです。
たとえば、小説の登場人物が一人で笑う場面や、映画の印象的な“ひとり笑い”のシーンなども分析対象に含まれています。
選ばれた120件はいずれも英語で書かれたもので、「ひとり笑い(solitary laughter)」に関する具体的な描写があることを条件に選定されました。
研究チームは、それぞれの文献に登場する“ひとり笑い”がどんな場面で起きているのか、またそれがポジティブ(心に良い)、ネガティブ(異常視される)、中立的なのかを丁寧に分類していきました。

さらに研究の中心成果として、新たに「Solitary Laughter Model(SLM)」という分類モデルを開発。
収集した文献の記述を以下の4つのタイプに整理し、“ひとり笑い”にはさまざまなバリエーションがあることを明らかにしました。
ひとり笑いの4分類(Solitary Laughter Model)
| 分類名 | 状況のイメージ | 具体例 | メンタルへの影響 |
| 完全な単独笑い | 完全に一人、誰とも関わらない | 昔の思い出を思い出して一人で笑う | 自己充足、内面的な快さを得やすい |
| 公的な単独笑い | 人前だけど、誰とも共有していない | 電車でスマホ動画を見て笑う | 誤解されやすく、不安や羞恥を伴うことも |
| 補助付き単独笑い | 道具や音声を使って一人で笑う | 笑いヨガ、録音した笑い声を聞いて笑う | セルフケアや瞑想として使われる例も多い |
| 社会的単独笑い | 誰かを思い浮かべながら笑う | SNSや手紙のやりとりを思い出して笑う | 他者とのつながりを感じやすく、安心感がある |
このように、「ひとり笑い」は単に“変な行動”ではなく、その背景や動機によって心理的な意味合いも異なるという多面的な性質を持っていることが見えてきました。

研究結果:実はポジティブだった“ひとり笑い”のイメージ
これまで「ちょっと変かも?」「心の病気のサイン?」と誤解されがちだった“ひとり笑い”。
しかし今回の研究では、その多くがポジティブまたは中立的に描かれていることが明らかになりました。
研究チームは、120件の文献を以下の3つの評価に分類しました。
| 評価の種類 | 件数 | 割合 |
| ポジティブ | 49件 | 約41% |
| 中立的 | 44件 | 約37% |
| ネガティブ | 27件 | 約22% |
さらに、「ひとり笑いのタイプ」ごとの特徴も見えてきました:
✅️完全な単独笑い:昔の思い出などを思い出して自然に笑う行動。→ 心を落ち着けたり安心感につながる
✅️社会的単独笑い:誰かとのやりとりを思い出して笑う。→ 孤独感を和らげる効果がある
✅️補助付き単独笑い:笑いヨガなど、意識的に笑う練習。→ ストレス軽減・気分のリセットに活用されている
✅️公的な単独笑い:公共の場で一人で笑ってしまう。→ 誤解や不安の原因になることもある
なお、研究チームが最終的に分類・集計したデータによれば、
全体の26%にあたる事例で「ひとり笑い」が明確にポジティブな心理的影響を及ぼしていたことも明らかになりました。
これは単なる印象論ではなく、研究に基づいた定量的な知見であり、「ひとり笑い」が心の回復や安定に寄与する具体的な証拠のひとつといえます。

文学・映画の中の“ひとり笑い”がもつ意味
興味深いのは、創作物における“ひとり笑い”の描かれ方です。
小説や映画では、ひとりで笑う人物が「狂気」の象徴として描かれることはむしろ少なく、
感受性の豊かさや深い思索の象徴として扱われているケースが多数ありました。
たとえば、日記を読み返してふと笑う登場人物は、「思い出を大切にできる人」「人生の機微を感じられる人」として描かれています。
これは、ひとり笑い=内面の豊かさを映し出す行動という新たな視点を提供してくれます。
“笑う場面”の背景感情がカギになる
同じ「ひとり笑い」でも、そのときの感情や思い出の文脈によって、大きく意味が異なることも分かりました。
・ある人は、懐かしい友人とのエピソードを思い出して笑い → 心が温かくなる
・別の人は、失敗談や人生の皮肉を笑い飛ばして → 自己受容につながる
つまり、「笑い」という行動の奥には、記憶・感情・人間関係といった豊かな背景が隠れているのです。
研究の結論
このレビュー研究が示したもっとも重要な結論は、
「ひとり笑いは“変”な行動ではなく、私たちの心を守る自然で健康的な行為である」
という点です。
・ひとり笑いは、多くの場合ポジティブな意味合いを持ち、メンタルヘルスの支えになりうる
・笑いは、人と一緒にいるときだけでなく、“ひとり”でも十分に癒しの効果を持つ
・“ひとりで笑う自分”を恥じる必要はない。むしろそれは、自分自身とつながる瞬間かもしれない
特に印象的なのは、「公的なひとり笑い(Public Solitary Laughter)」に関する知見です。
このタイプの笑いは、電車の中や職場など他人の目がある場所で起きるため、誤解や羞恥、不安感を引き起こしやすいことが指摘されています。
日本のように「空気を読む」文化では、そうした負担がより強くなる可能性もあるため、“安心して笑える場”をどう確保するかが、今後の課題と言えるでしょう。
一方で、研究チームは「ひとり笑い」を前向きに活かすための新たなアプローチも提案しています。
たとえば、
・日々の自分の笑いを記録して振り返る「ひとり笑い日記」
・子どもや高齢者の“感情理解”を深めるための教育ツール
・セルフケアやセラピーにおける「自己調整」のヒントとしての応用
などが期待されており、
“ひとり笑い”は単なる行動にとどまらず、自己理解や感情調整の入口になりうることが見えてきました。
このように、
「ひとりで笑う」という一見ささやかな行為が、私たちのこころの健康を守る大切な習慣となりえるのです。
誰かと一緒じゃなくても、笑うことには確かな価値がある――この研究は、そんな力強いメッセージを投げかけています。

【礼次郎の考察とまとめ】“ひとりで笑う”って、こんなに健やかだったんだ
今回の研究を読んで強く感じたのは、
私たち日本人にとって「ひとり笑い」は、思っている以上に身近で大切な行動なのではないか、ということです。
日本には「人前で変に思われないようにふるまう」という文化的圧力があります。
そのため、電車の中や職場などで「つい笑ってしまう」と気まずくなったり、
逆に家で一人で笑っているのを誰かに見られて「恥ずかしい」と感じてしまう人も多いかもしれません。
でもこの研究は、
“ひとり笑い”は決しておかしいことではなく、むしろ心の回復力とつながっている
と教えてくれます。
特に印象的だったのは、
「完全な単独笑い」や「社会的単独笑い」が、記憶や感情、安心感、自己受容といった、わたしたちの深い部分を支えている
という点。
たとえば、
・ふと昔のことを思い出して笑ってしまうこと。
・誰かの声や言葉を思い出してじんわり笑うこと。
そういう瞬間があるだけで、
「ああ、自分はちゃんとつながっていたんだ」
と思えることってありますよね。
また、笑いヨガやセルフケアとしての“ひとり笑い”は、他人と比べず、自分自身とだけ向き合える癒しの時間とも言えます。
他人の目を気にせず「今ここ」の自分をそのまま笑えるって、実はとても自由で贅沢なことなのかもしれません。
締めのひとこと
ひとりで笑える自分も、じつはとっても強くて優しい。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!
もし本記事が参考になったら、他の記事もぜひのぞいてみてください。
これからも皆さまの知的好奇心を満足させられる情報をお届けできるよう努力していきます。
本ブログでは、Pubmed、医中誌、Clinical Key、ヒポクラ、m3、日経メディカル、ケアネットなどの信頼性ある医療情報サイトを参考に、論文の検索・選定を行っています。
記事の内容は、筆者自身が論文を読み解き、わかりやすく要約・執筆しています。


コメント